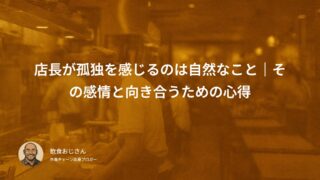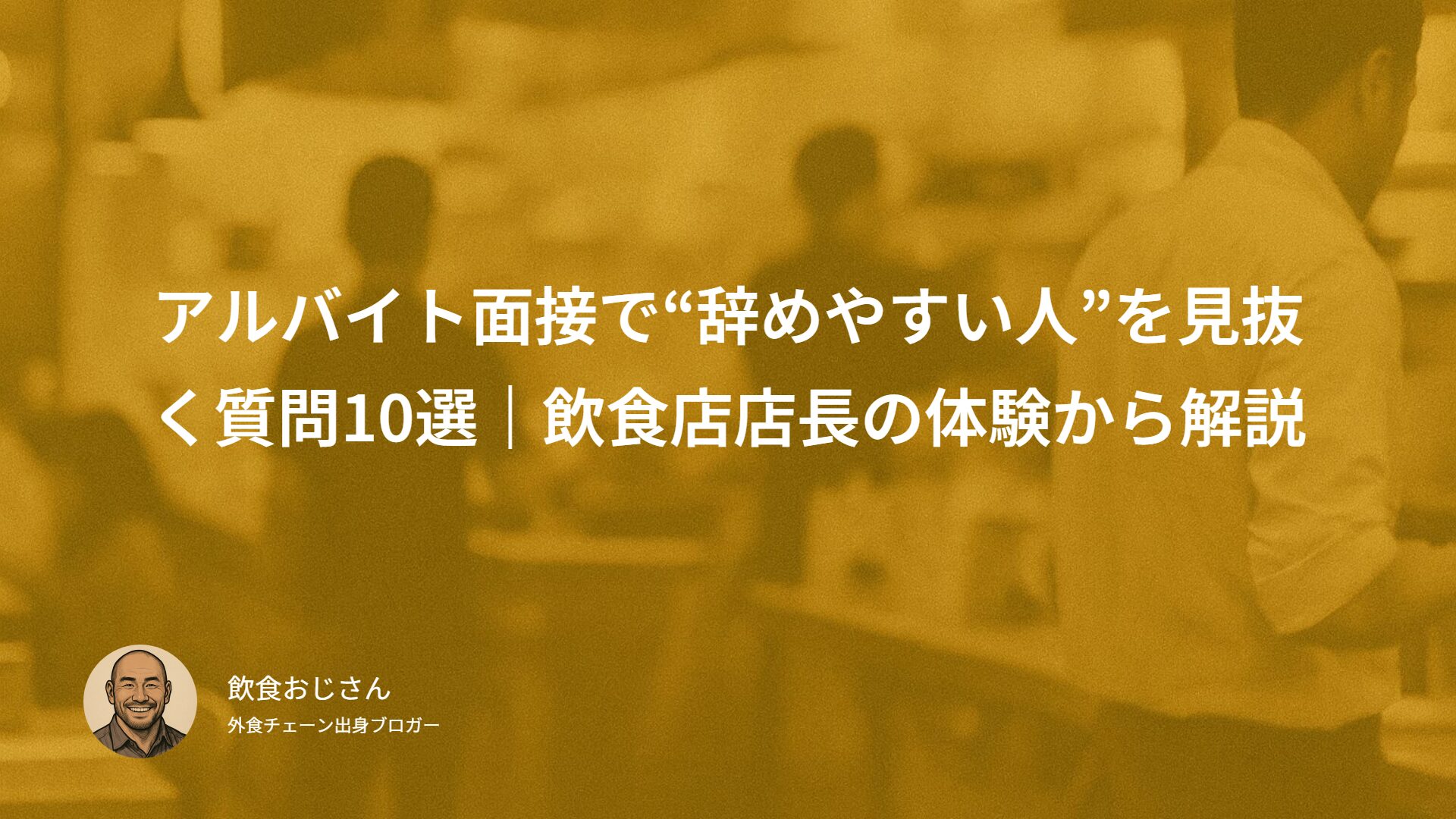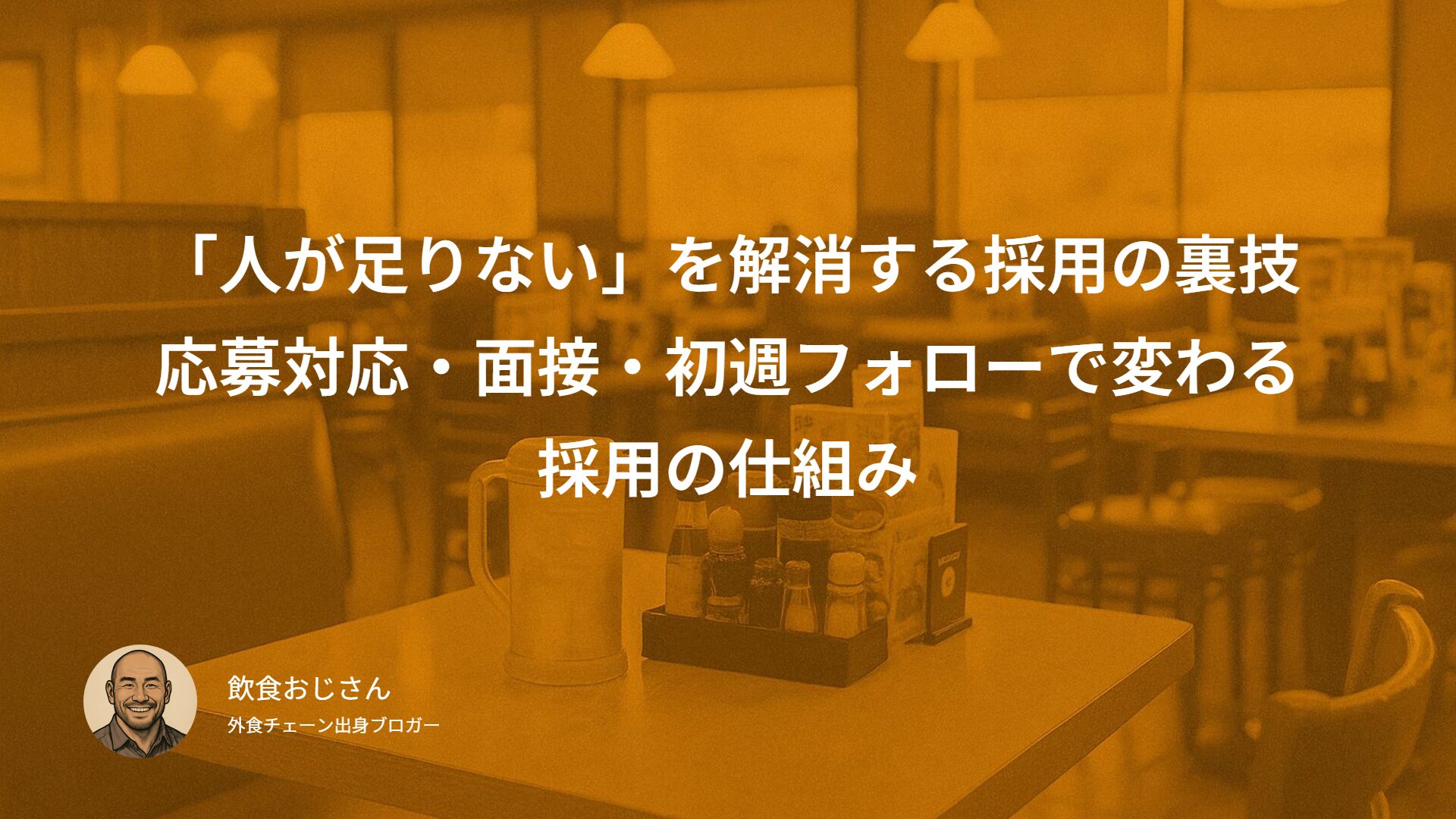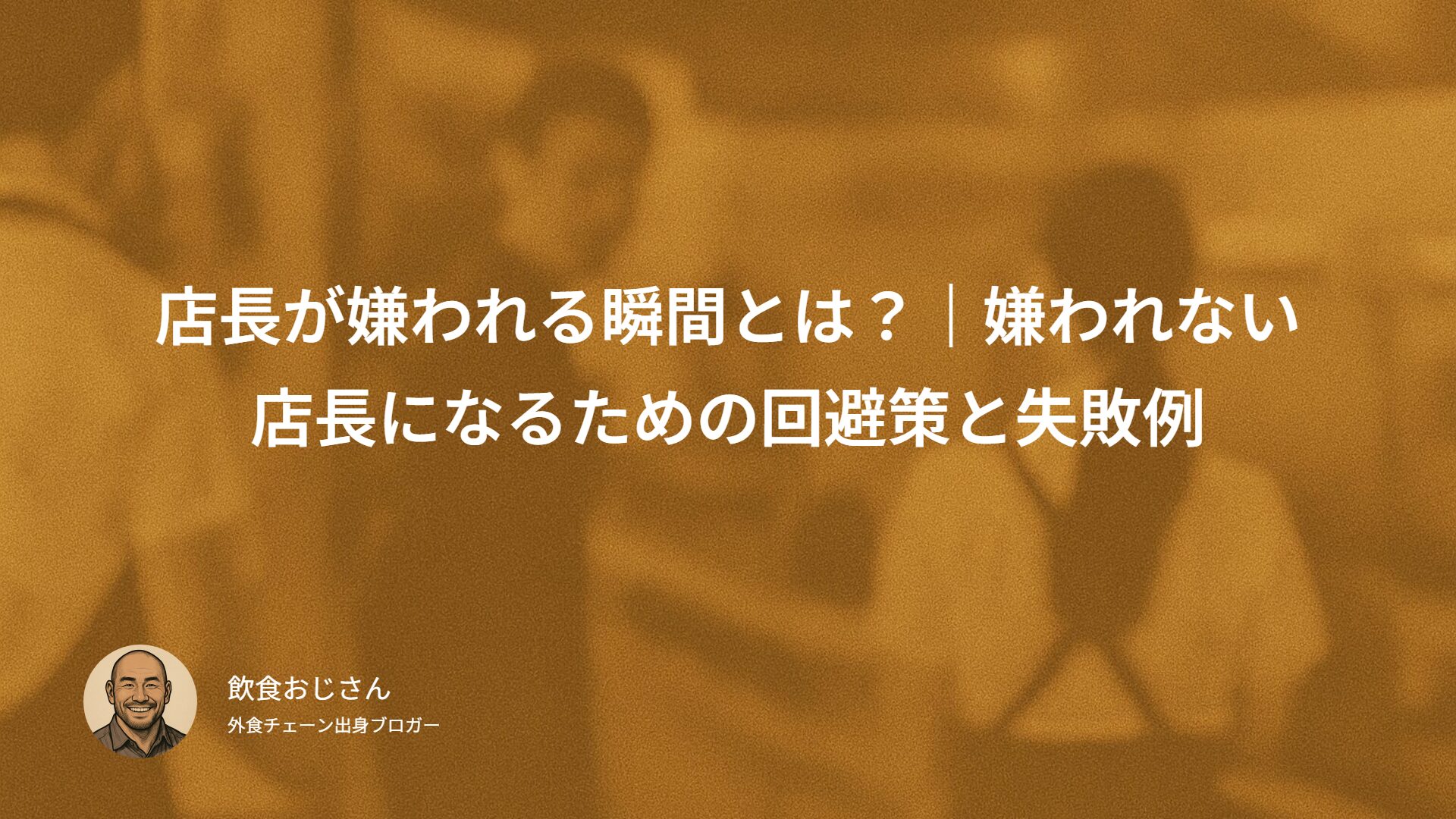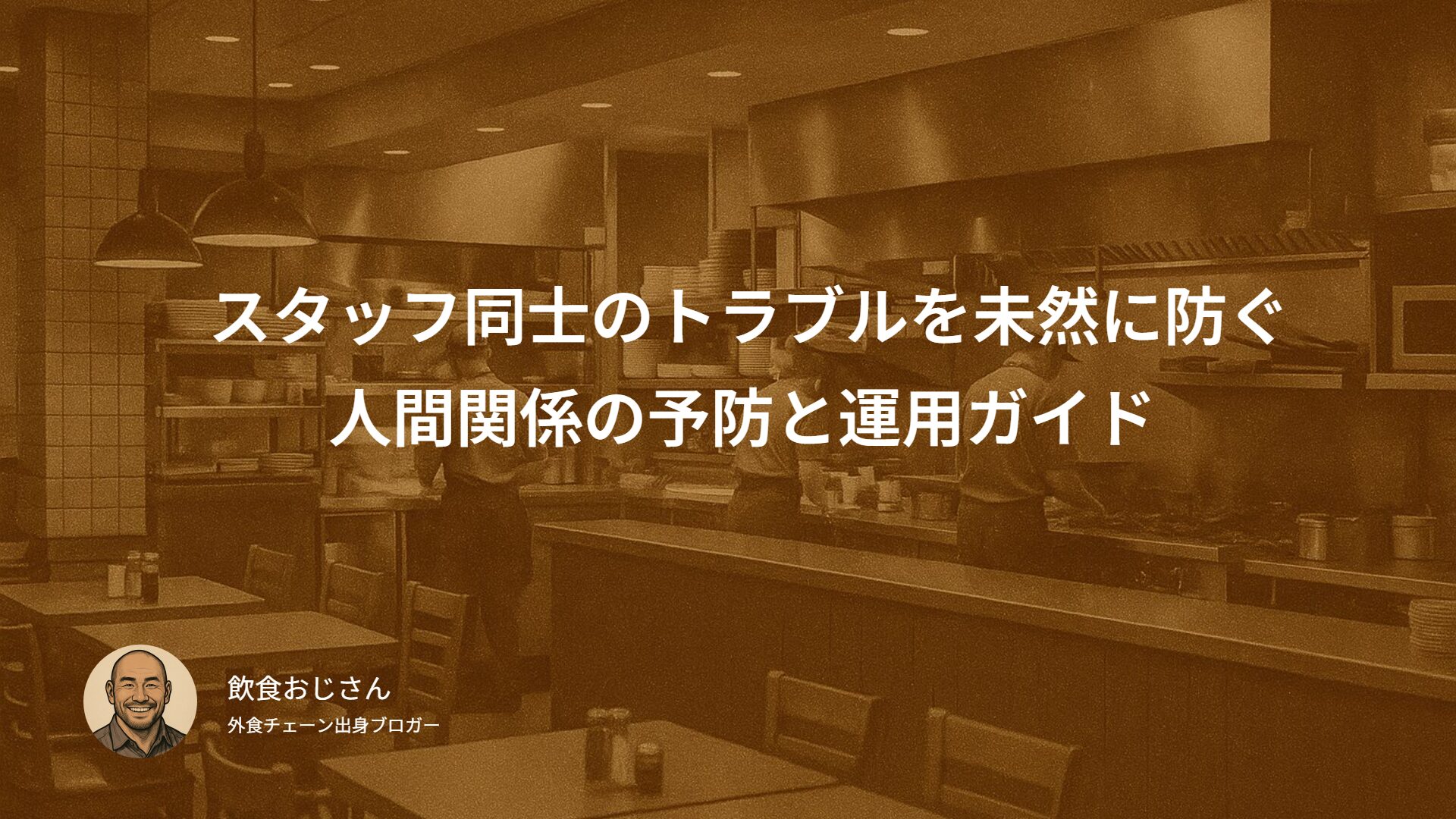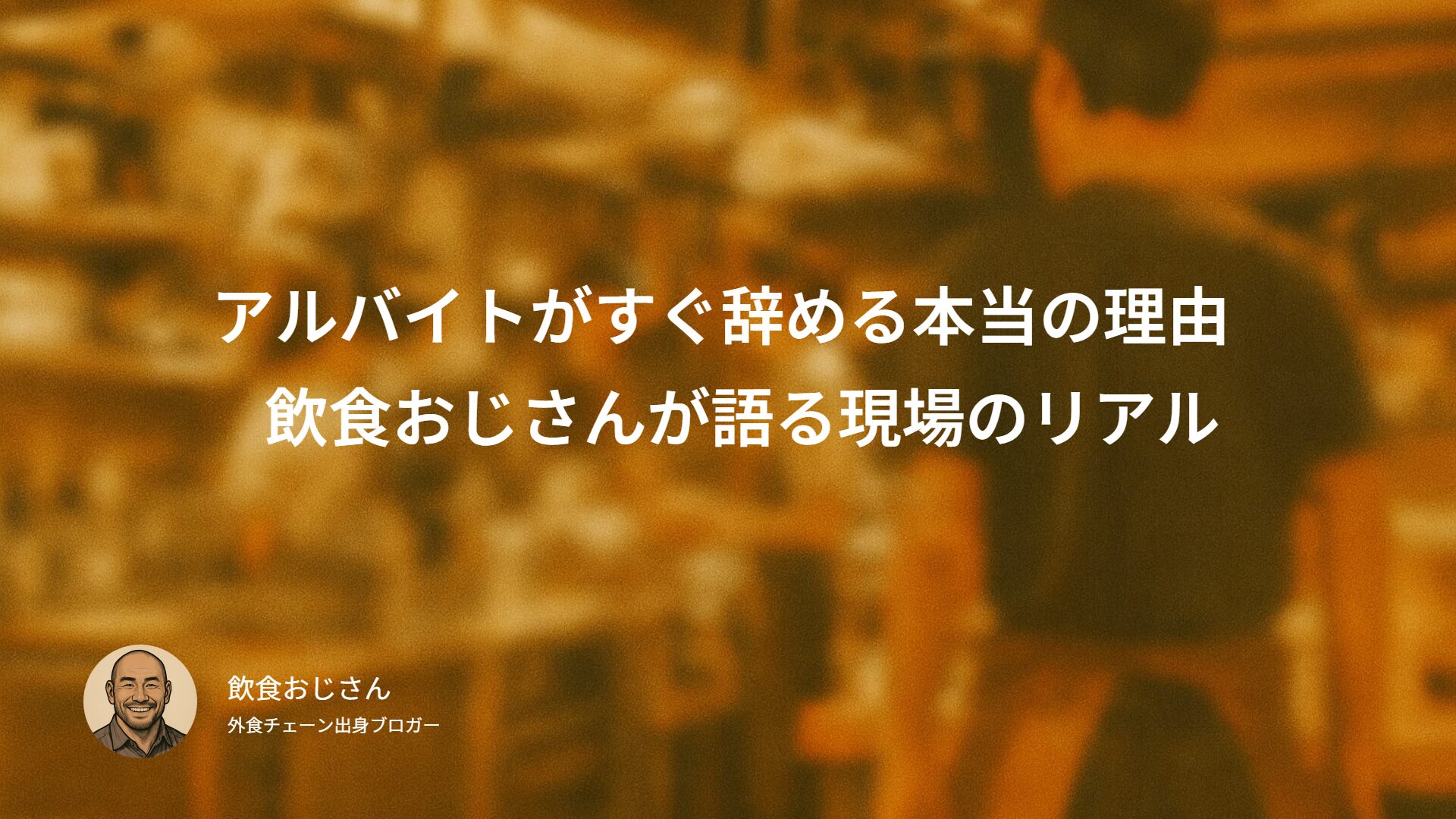想定外の退職から見える「店の弱点」 信頼していた人が辞めた本当の理由
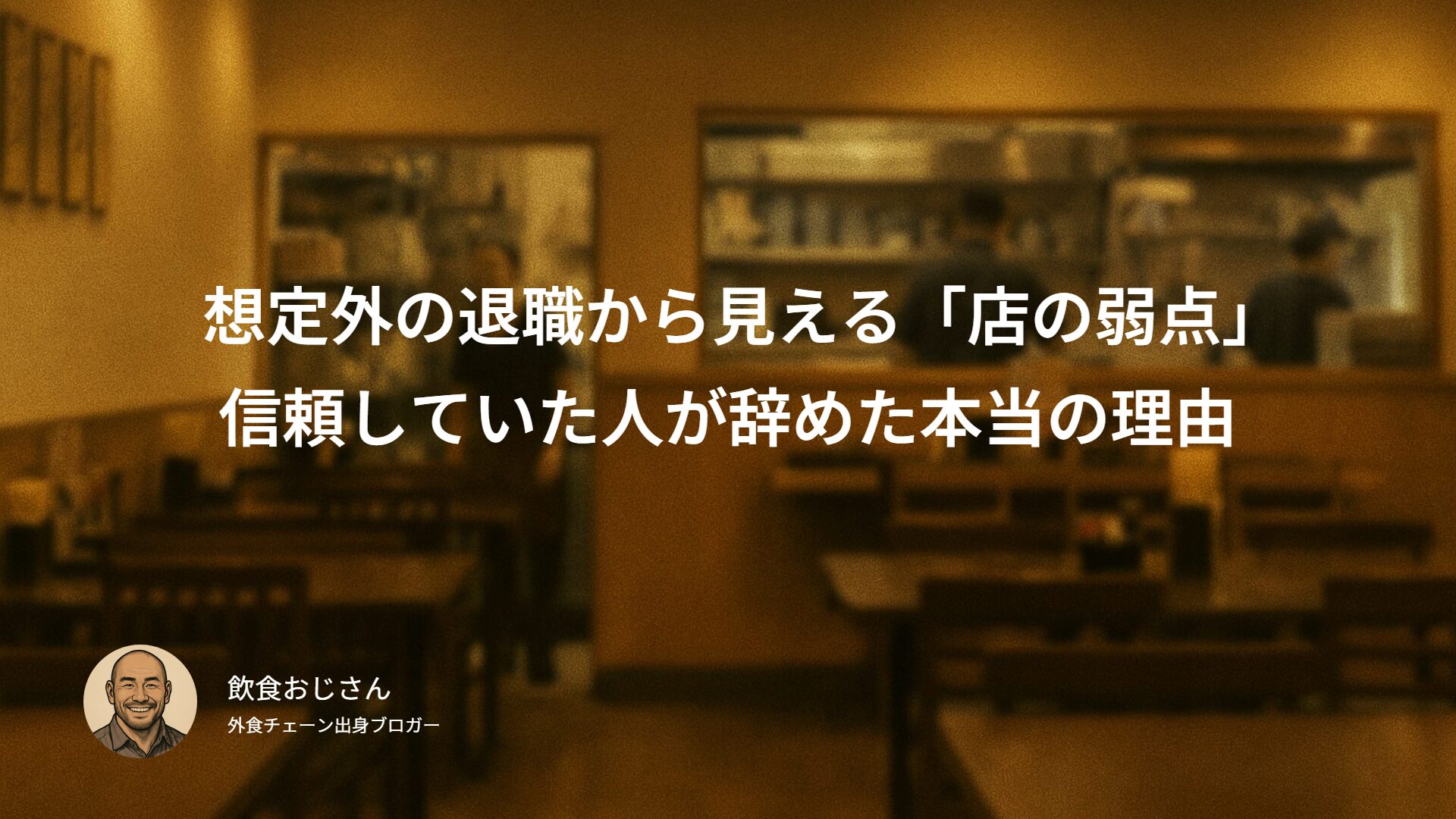
「まさか、あの子が辞めるなんて」
そう感じた経験はありませんか?
普段から真面目で、チームの中心だったスタッフが突然退職を申し出る。店長としてはショックが大きく、「何が悪かったのか分からない」まま時間だけが過ぎてしまう――。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗の運営に取り組んできました。

実は、こうした“想定外の退職”こそが、店の仕組みやマネジメントの見えにくい弱点を教えてくれます。
辞めた人を責めるのではなく、「なぜ気づけなかったのか」を考えることが、次の定着への第一歩です。
この記事では、“信頼していた人が辞めた理由”を手がかりに、店のどこに改善の余地があるのかを整理し、次のスタッフが“続く環境”をつくる方法を解説します。
✅ この記事を読むメリット
- 想定外の退職が起きる本当の構造がわかる
- 店の「見えない弱点」を見抜く視点を学べる
- 離職を“定着改善”につなげる手順がわかる
まさか辞めるとは思わなかった——“想定外の退職”の衝撃

辞めそうに見えなかった人が、静かに限界を迎える
どの店にも「安定している」と感じていたスタッフがいます。遅刻もなく、シフトも柔軟。愚痴も言わず、周囲との関係も良好。
彼らは我慢強く、空気を読むタイプが多い。不満を言葉にせず、自分の中で処理しようとする。
店長が「大丈夫だろう」と思っている間に、心の中では静かに“限界ライン”を越えていることがあるのです。
「まさか辞める人」に共通する3つの前兆
- 会話量が減る:報告が事務的になり、雑談がなくなる
- 挑戦しなくなる:提案・改善が止まり、言われたことだけをやるようになる
- 店長との距離ができる:目を合わせなくなる、質問を避ける
これらのサインは“やる気の低下”ではなく、“信頼の摩耗”です。本人に悪気はなくても、「どうせ伝わらない」「もう変わらない」と感じていることが多いです。
退職のサインと店長がとるべき初期対応
| スタッフの変化(サイン) | 店長がとるべき初期対応 |
|---|---|
| 会話が減った | 雑談ベースで声をかける・軽く様子を聞く |
| 改善提案がなくなった | 「最近どう?」と様子を聞き、やりづらさがないか確認する |
| 距離を感じる態度になった | 忙しくても短く一言、関心を向ける |
信頼していた=任せきりだった
想定外の退職が起きる背景には、「信頼」への誤解があります。
「任せている」「自由にやらせている」と思っていたが、それは放任に近い状態になっていた。
“大丈夫そうな人”ほど、気づかれないストレスを抱えています。信頼していたなら、なおさら目を配る。それが“守る信頼関係”をつくる第一歩です。

想定外の退職の原因は“人”ではなく“仕組み”にある
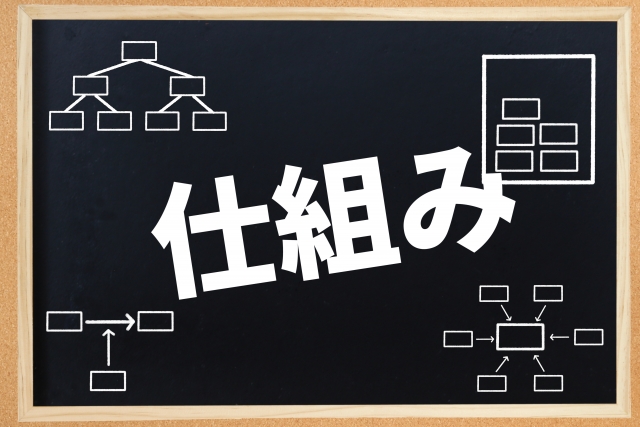
「就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が38.4%、新規大学卒就職者が34.9%である。」厚生労働省
退職理由の多くは「人間関係」より「構造の欠陥」
想定外の退職が起きたとき、多くの店長は「合わなかったのかな」「人間関係が原因だろう」と考えます。
しかし、店をよく見直すと、本質は“仕組みの疲労”にあることが多いです。
教育が属人的で、誰が教えるかによって差が出る
シフトの偏りが慢性化している
評価や期待の伝達が曖昧になっている
こうした曖昧な仕組みのまま放置していたことが、スタッフに小さなストレスを積み重ねていきます。
人ではなく、仕組みの歪みが人を疲れさせているのです。
見落とされやすい“成長機会の欠如”
長く働いてくれる人ほど、日常業務の安定だけでは満足できません。「もっと任されたい」「新しいことを学びたい」と感じる時期が必ず来ます。
しかし、店の側がそこに気づかず、同じ仕事を淡々と任せ続けてしまう。
その結果、
「この店でこれ以上成長できない」
という静かなあきらめが生まれる。
信頼していたスタッフが辞めた背景にある「仕組みの弱点」
| 表面的な退職理由 | 背景にある仕組みの弱点(例) |
|---|---|
| 教えてもらえなかった | 教育の流れが属人的・場当たり的だった |
| 人間関係が合わなかった | ポジションの偏り・役割の偏重が放置されていた |
| やりがいがなかった | 成長の機会や役割の更新がなかった |
| 相談しづらかった | 意見が言いにくい空気・一方通行の伝達文化 |
「辞めた理由」は本音と建前を分けて考える
退職面談では、たいてい穏やかな言葉が並びます。
でも、その裏には「伝えても変わらない」という諦めが隠れていることが多い。
表に出る理由は“建前”。本音は、“言っても無駄だった過去”にある。
店の“仕組み疲労”を点検する
- 仕事量が昔と変わらないのに、人員は減っていないか
- 教育手順が古いままになっていないか
- 成果の基準があいまいなまま放置されていないか
これらを見直すだけでも、スタッフが感じる「見えない不公平」は大きく減ります。仕組みを保守することは、人を守ることと同義です。
退職の原因を“性格”や“人間関係”に求めてしまうと、何も変わりません。焦点を“仕組み”に移す。それが、定着を長続きさせる唯一の方法です。

👉 退職をきっかけに店の関わり方を見直したい方は、次の記事も参考にしてください。
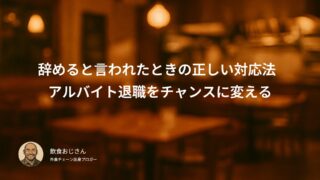
退職者分析は「定着づくり」の材料になる

✅ 辞めた理由は、次のスタッフを守るヒントになる
スタッフが辞めると、「あの人は仕方なかった」と片づけてしまいがちです。しかし、辞めたあとにこそ「何が足りなかったか」が見えてくることがあります。
たとえば、伝え方のズレや、期待していた成長機会を提供できていなかったこと。
✅ 退職理由を“仕組み”で振り返ると改善点が見える
「家庭の都合」「方向性の違い」などの言葉に安心せず、その背景にどんな仕組みの弱さがあったのかを考えてみることがポイントです。
- 教え方にバラつきがあった
- ポジションの偏りが続いていた
- 意見を言いにくい雰囲気だった
こうした構造の問題を見つければ、改善によって同じ退職を防ぐことができます。
✅「辞めた理由」は、「続けるための理由」に変えられる
辞めた人の言葉は、店のやり方を見直すきっかけになります。
- 「感謝されなかった」→小さな声かけを習慣にする
- 「これ以上成長できないと思った」→新しい役割を任せる
- 「聞いても変わらないと思った」→日常で相談のきっかけをつくる
一人の退職は、これから残る人の働きやすさをつくる材料になります。そこから改善できれば、辞めたことにも意味が生まれます。
辞めた理由は、“誰が悪いか”を決めるためではなく、“うちをもっと良くする”ために使うんです。

まとめ|信頼していた人が辞めた理由は、定着改善に最適
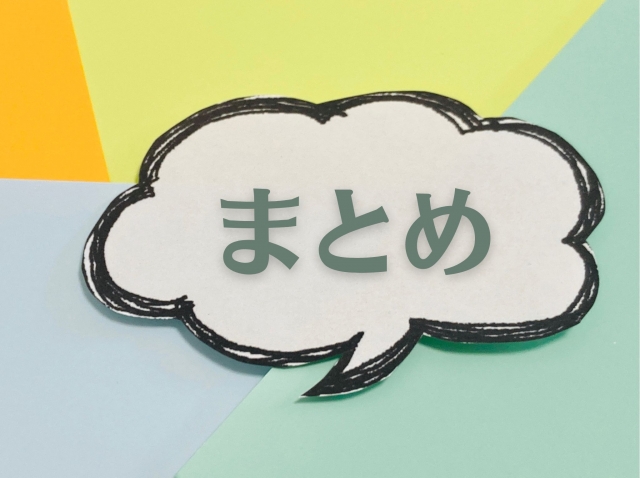
想定外の退職から学べること【定着率を高めるヒント】
- 「辞めそうにない人」ほど、ストレスを抱えやすい
- 退職の原因は、性格ではなく店の仕組みにあることが多い
- 辞めた理由は、次のスタッフを守る改善材料になる
捉え方次第で、退職は“失敗”ではなく、“気づき”のきっかけにできます。
「信頼していた人が辞めたときは、職場を見直す機会です。仕組みを変えることで、人が“続く店”に近づいていきます。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 店長としての孤独感とどう向き合えばいいか悩んでいる方は、次の記事も参考にしてください。