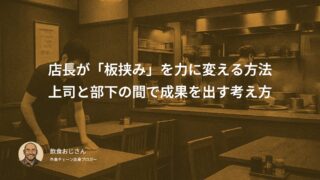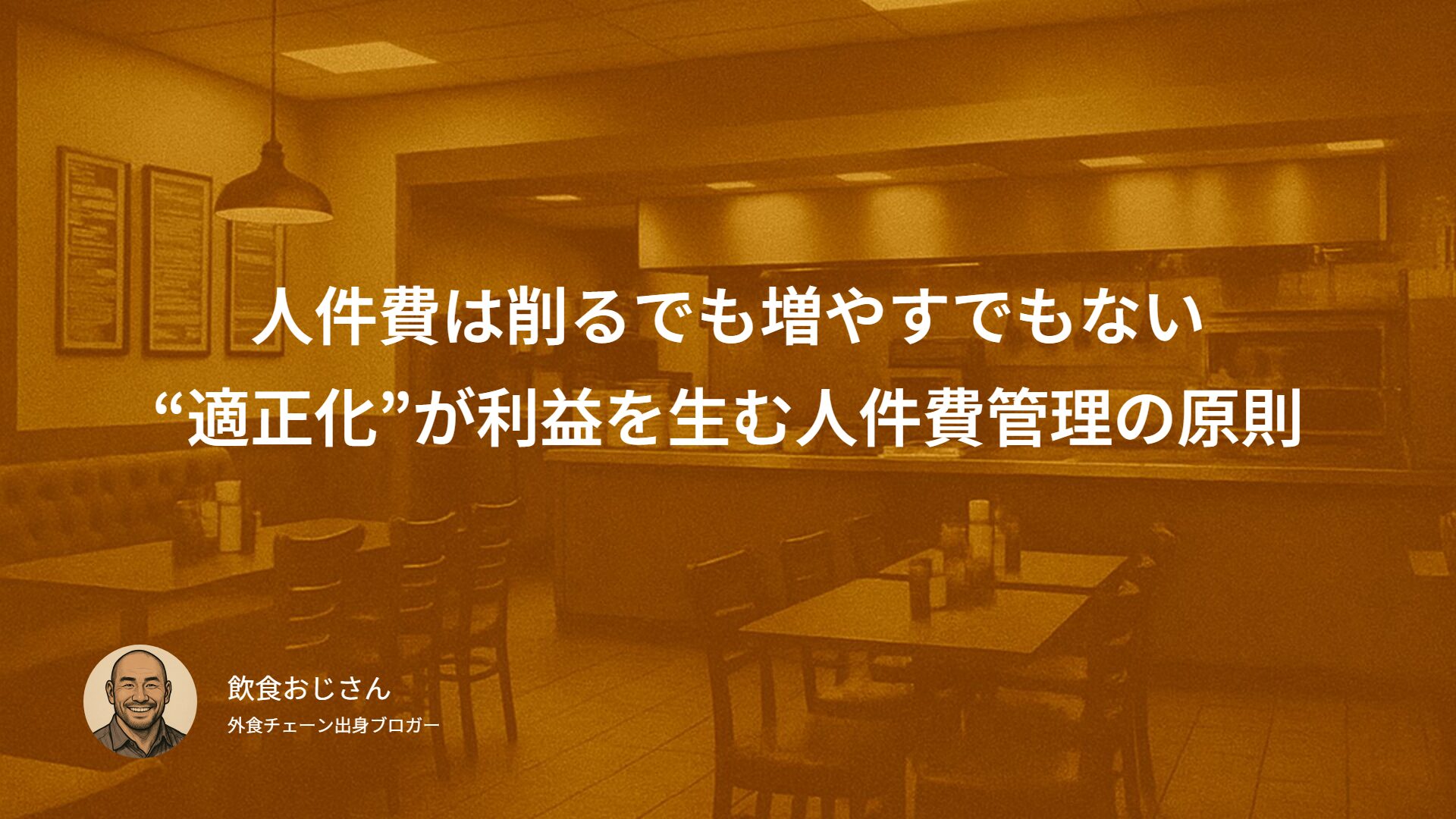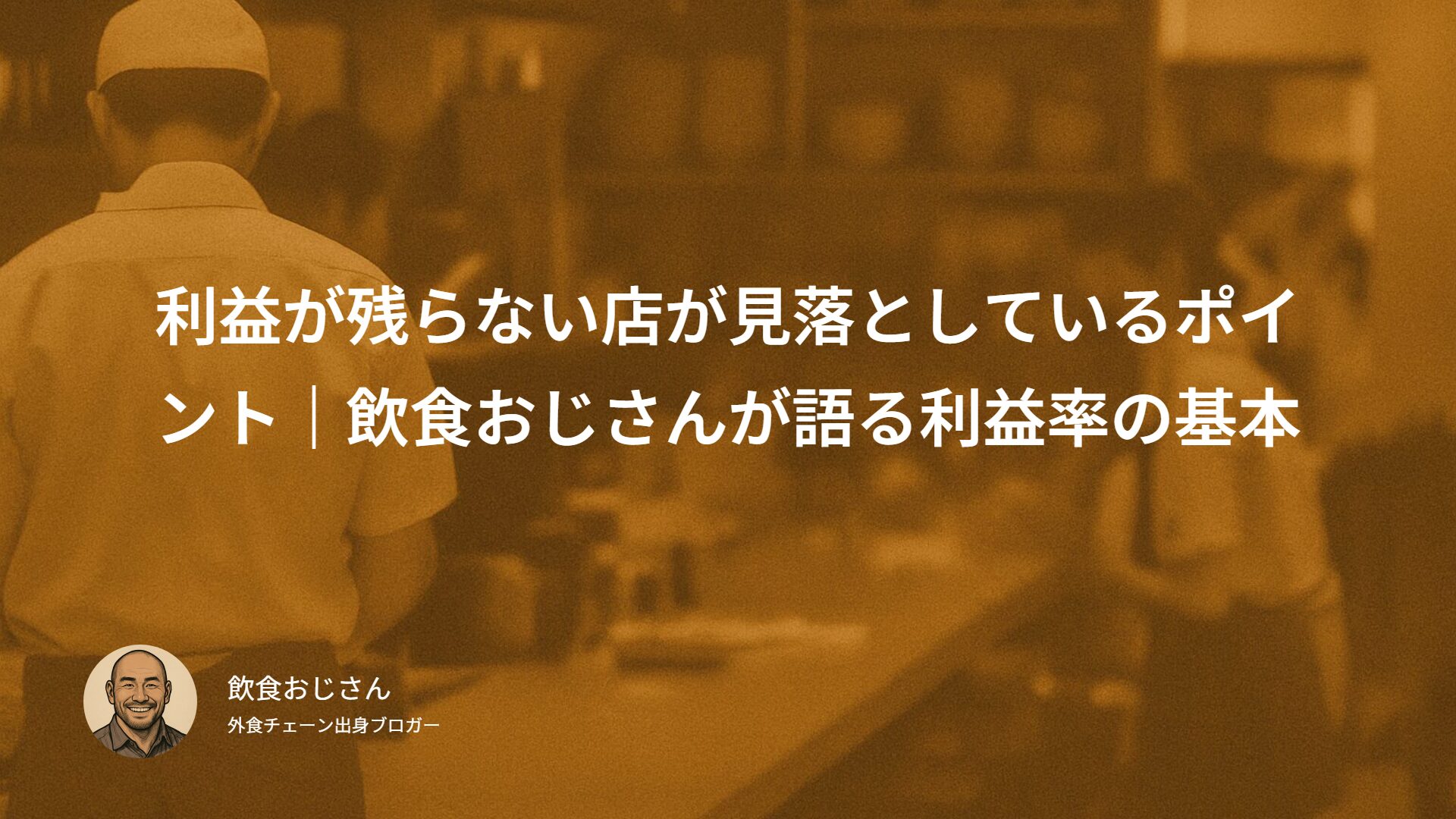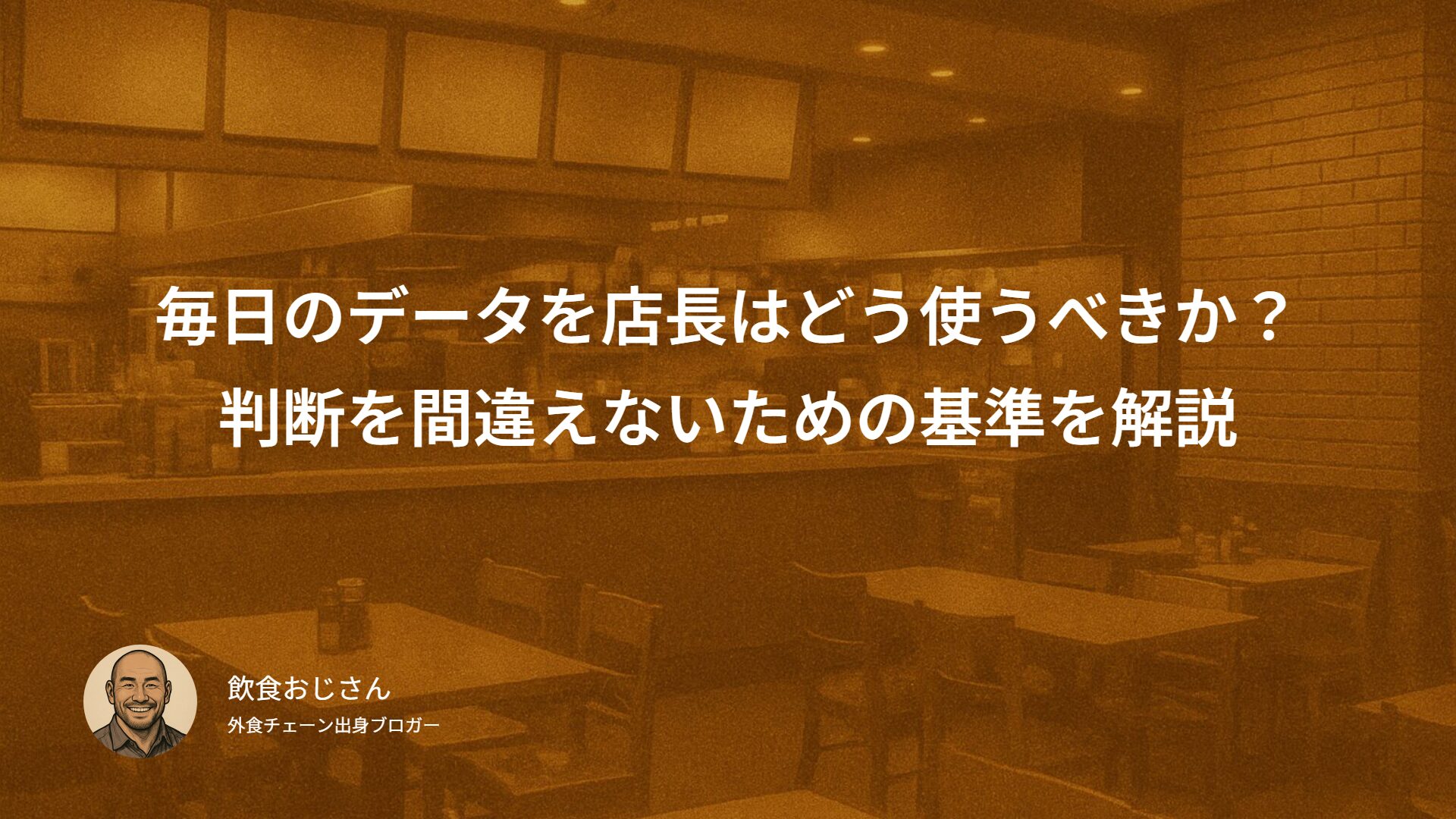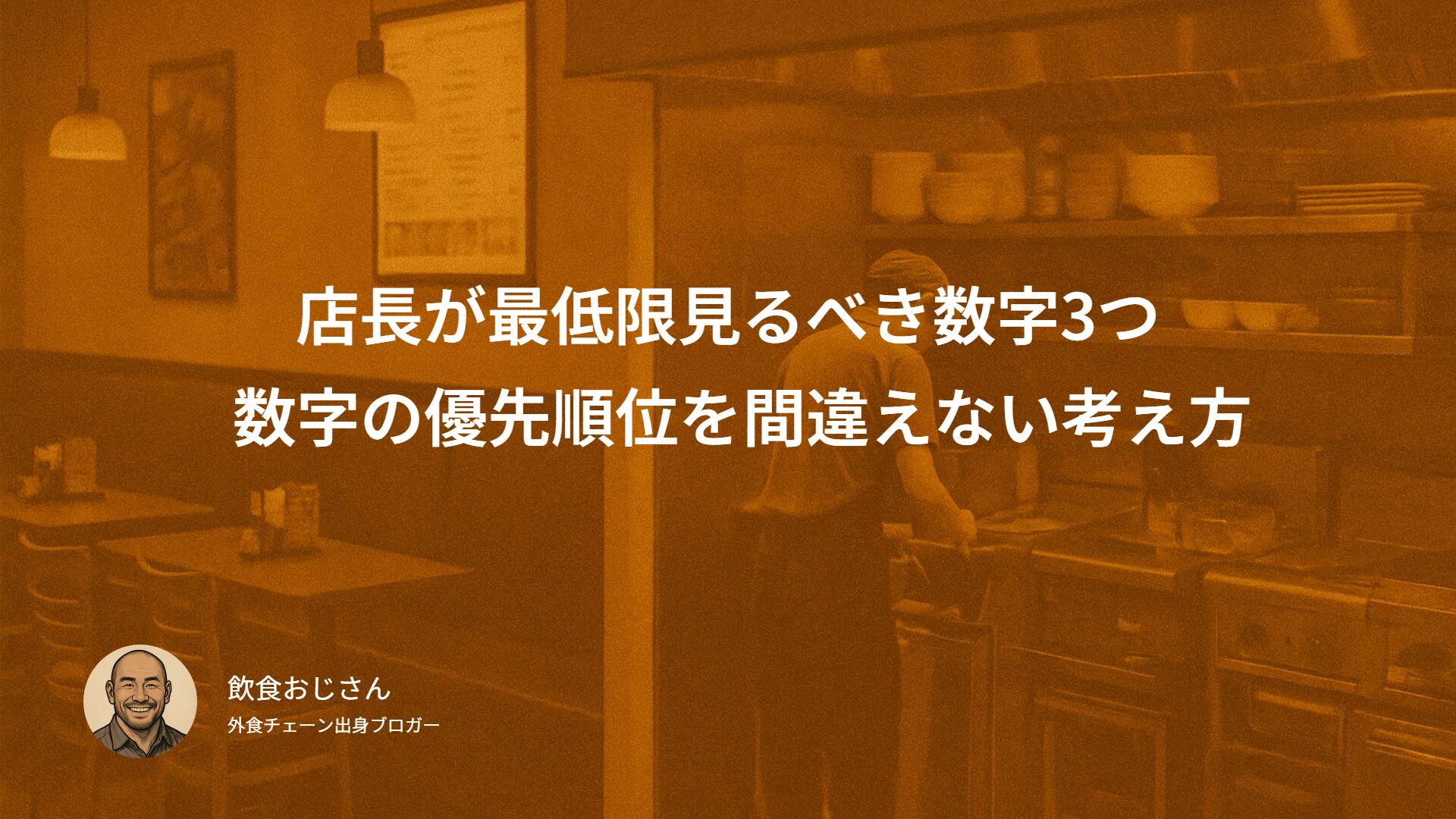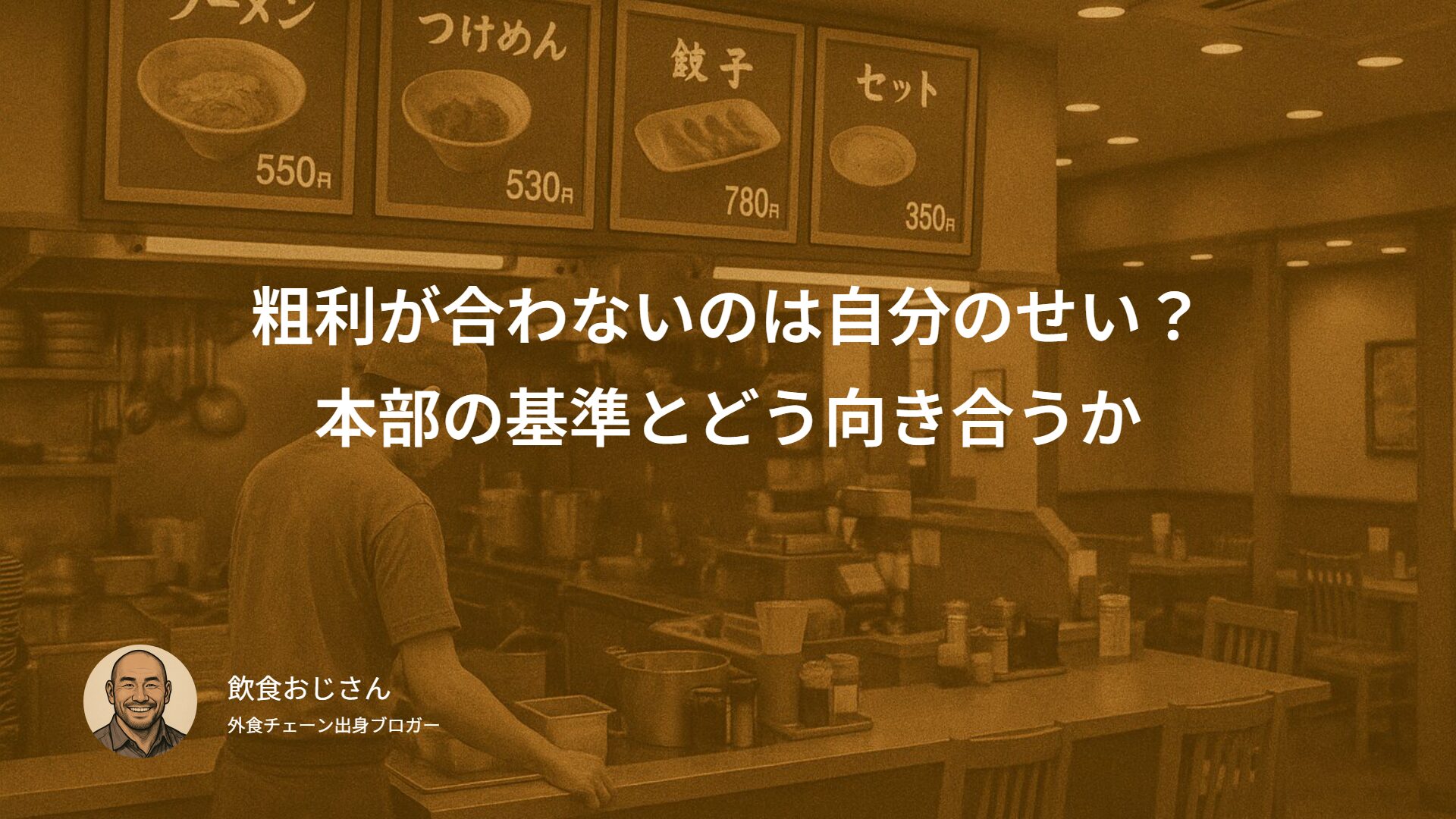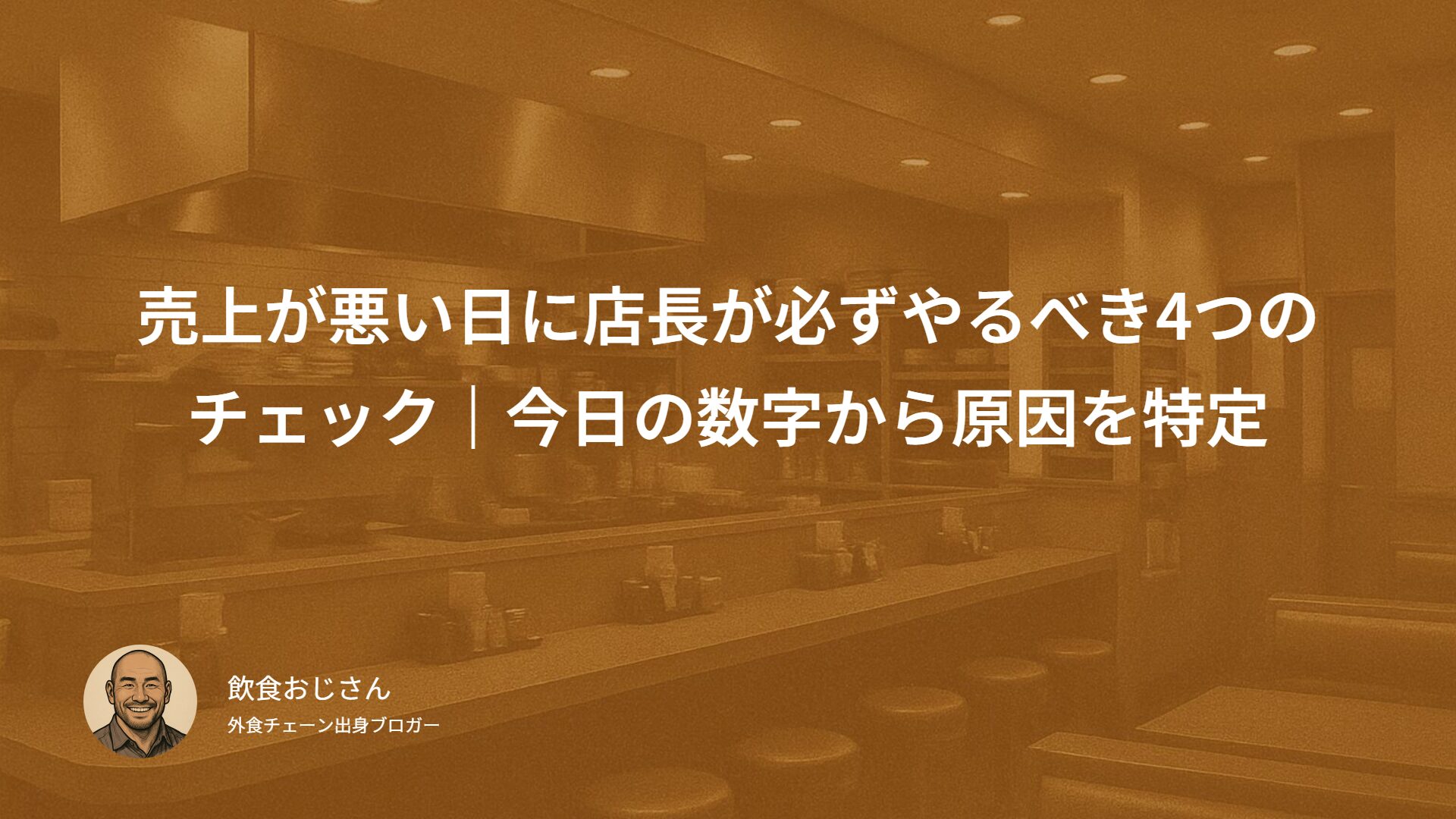評価基準の違いをどう活かす?|本部と店舗をつなぐ店長の役割
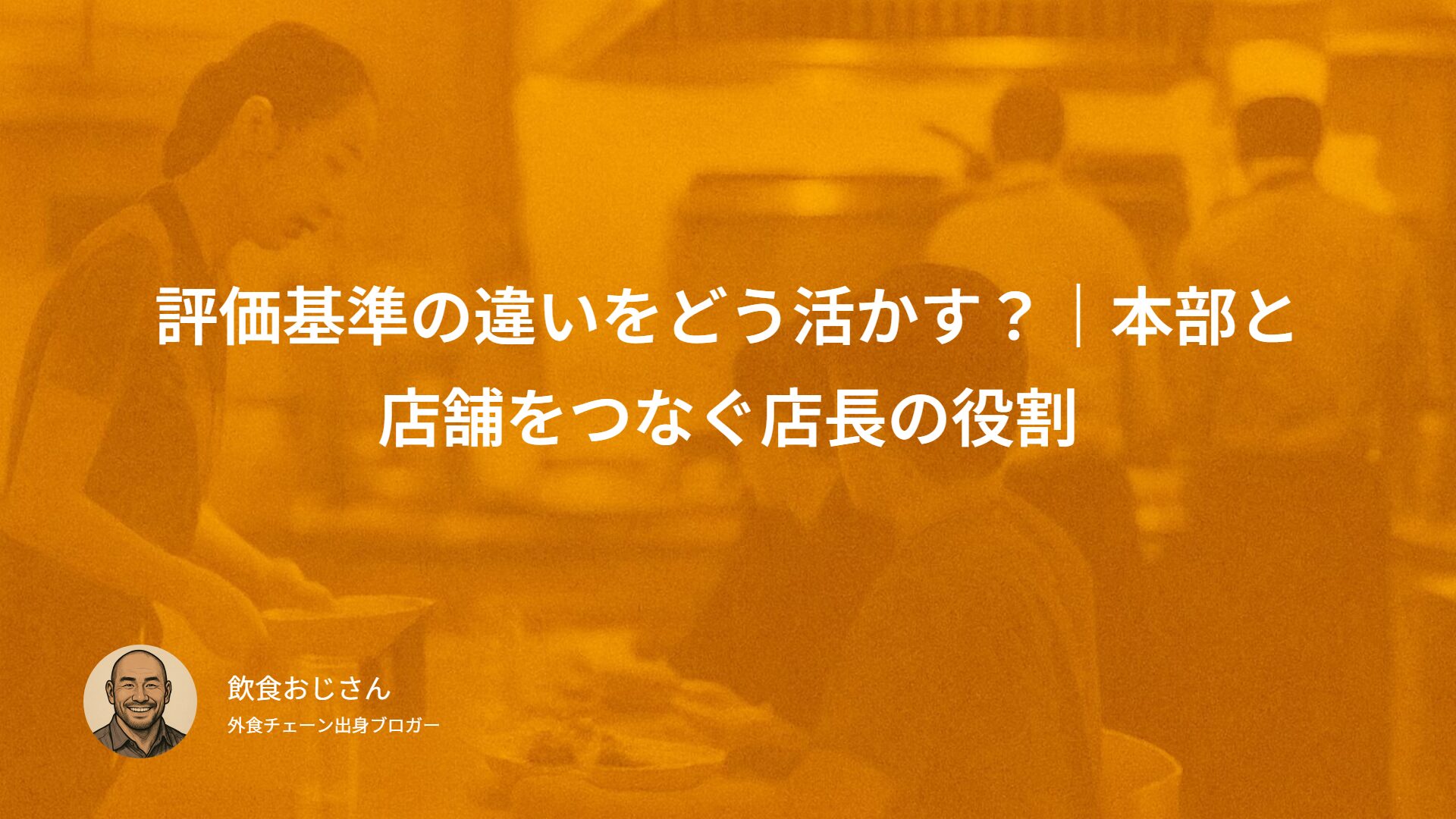
「売上や利益が伸びても今一つ本部に評価されない」
――そんな経験をしたことはありませんか?
でも、それを不満に思うのは少し違います。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗の運営に取り組んできました。

会社組織にいる以上、本部は全体の数字で評価するのが役割。現場の手応えやお客からの感謝は評価軸には入りません。それが当たり前なんです。
大切なのは、不満をこぼすことではなく数字で返すこと。
店長がやるべき本当の仕事は、数字に現れない現場の価値を守りつつ、本部の基準と現場の実感をつなげて成果を倍増させることです。
この記事では、
- 本部が何を重視して評価しているのか
- 店長が数字で返すべき理由
- 現場の価値と本部の基準を組み合わせて相乗効果を生む方法
を解説します。
最後まで読めば「評価に振り回される側」から抜け出し、「数字を武器にする店長」への一歩を踏み出せます。
本部が重視する評価基準を理解せよ

本部の物差しは「全体最適」
チェーン全体を安定して回すための「売上・利益・人件費率・粗利」など、数字でしか判断しません。
「頑張った」「店の雰囲気はいい」――これらは店長にとって大事な実感ですが、会社の評価基準には入りません。なぜなら、それは全体を比較できないからです。
評価されない=“基準を満たしていない”だけ
不満を口にする前に、自分の店の数字が「本部の物差し」を超えているかを確認するべき。
評価されないのは、本部が分かっていないからではなく、まだ結果で示せていないからです。
基準は変えられない、だから利用する
ならば逆に利用しましょう。
基準を理解してクリアすれば、誰もあなたに口を出せなくなります。
評価されるかどうかで悩むのではなく、基準を攻略すること自体をあなたの武器にするのです。
本部が評価に使う主要数字の一覧
| 評価基準 | 内容 | 本部が見るポイント |
|---|---|---|
| 売上 | 前年比・計画比 | 店舗の成長度合い、目標達成率 |
| 粗利益率 | 売上から原価を引いた割合 | 利益が安定しているか |
| 人件費率 | 売上に占める人件費の割合 | 効率的に運営できているか |
| 廃棄率 | 食材ロスの割合 | 無駄をどれだけ抑えられているか |
評価されないと感じたら、まずは基準をクリアする数字を目指しましょう。結果で示せば、自然と評価はついてきます。

店舗スタッフが大事にする基準

お客の声と笑顔が最大の成果
店舗にいるスタッフにとって、最も分かりやすいのは「お客からの反応」です。
「美味しかった」「ありがとう、また来るよ」
という言葉や笑顔は、直接の評価であり、スタッフの誇りにもつながります。
数字には残らなくても、現場を支える大きな力です。
チームの雰囲気と働きやすさ
スタッフは「売上が何%伸びたか」よりも、
「この店で働きやすいか」「仲間と気持ちよく動けるか」
を強く感じています。
雰囲気が悪ければミスや離職につながり、逆に雰囲気が良ければ自然に売上もついてくる。
現場にいるからこそ分かる“空気”が、スタッフの基準なんです。
日々の達成感と承認
「今日のピークを事故なく乗り切れた」「新人が一人前に接客できた」
――こうした小さな成功体験も現場にとっては大切な成果です。
これらは本部評価には反映されませんが、スタッフのやる気や定着には直結しています。
数字以上に「続けられる環境」をつくるための基準なんです。
スタッフが感じる“日々の成果”の例
| スタッフが重視すること | 具体例 |
|---|---|
| お客からの反応 | 「美味しかった」「また来たい」という言葉や笑顔 |
| チームワーク・働きやすさ | 仲間と協力できる、気持ちよく働ける |
| 達成感 | 忙しいピークを無事に乗り切れた |
| 成長実感 | 新人が接客できるようになった、調理を任せられるようになった |
お店で働く人は、数字も見ていますが、それ以上に“日々の手応え”を大事にする傾向があります。お客の笑顔や仲間との達成感――そうした実感が、続けて働く力になるんです。

👉 毎日の数字をどう判断に使えばいいか迷っている方は、次の記事も参考にしてください。
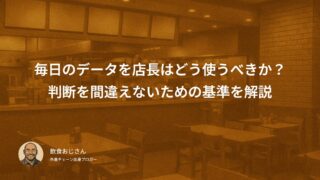
店長は“翻訳者”として相乗効果をつくる
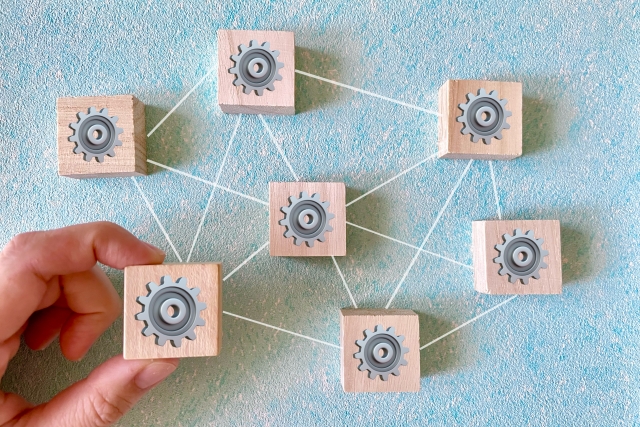
✅ 数字を“人が理解できる言葉”に変える
本部から降りてくる数字は、そのままではスタッフには響きません。「売上前年比+5%」と言っても現場にはピンと来ない。
それを
と翻訳するのが店長の役割です。
数字を日常の仕事に結びつければ、スタッフは行動しやすくなります。
✅ お店の声を“数字”に変えて本部へ伝える
逆に、店舗での工夫やお客の声は、そのままでは本部に届きません。
「雰囲気が良くなった」や「スタッフの定着率が上がった」という感覚を、
離職率の低下
アンケートの改善点
廃棄率の減少
といった数字や事例に落とし込めば、本部も評価しやすくなります。職場の価値を数字に変える“通訳”ができる店長は強いです。
✅ 両方をつないで“相乗効果”を生む
本部が重視する数字と、お店が大切にする実感。この二つを対立させるのではなく、組み合わせるのが店長の腕の見せどころです。
数字を基準にすれば方向性がブレず、実感を尊重すればチームは力を発揮する。
店長が翻訳者となることで、本部と現場の評価基準がかみ合い、結果として大きな成果につながります。
数字とスタッフの動きを結びつける流れ
店長は“数字と人”をつなぐ翻訳者。どっちか片方じゃなく、両方をつないでこそ成果は倍になりますよ。

まとめ|評価基準の違いを理解して相乗効果を生む

評価基準の違いをつなぐのが店長の役割
本部と店舗スタッフは、それぞれ異なる評価基準を持っています。
本部は数字で全体を管理し、スタッフはお客からの感謝や働きやすさを手応えとして感じる。どちらかが間違っているのではなく、役割が違うだけです。
店長はその違いをつなぎ合わせ、数字と手応えの両方を成果に変えていく存在。そのためには一方を否定するのではなく、互いを生かして相乗効果を生むことが大切です。
- 本部は「売上・利益・コスト」など数字中心で評価する
- 店舗スタッフは「お客の声・働きやすさ・達成感」を基準にする
- 店長はその違いを理解し、橋渡しをして成果を倍増させる
「自分だけが正しいと思うな。数字も手応えも役割がある。つなぐことで成果は大きくなるんです。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 上司と部下の間で板挟みになり、どう動けばいいか悩んでいる方は、次の記事も参考にしてください。