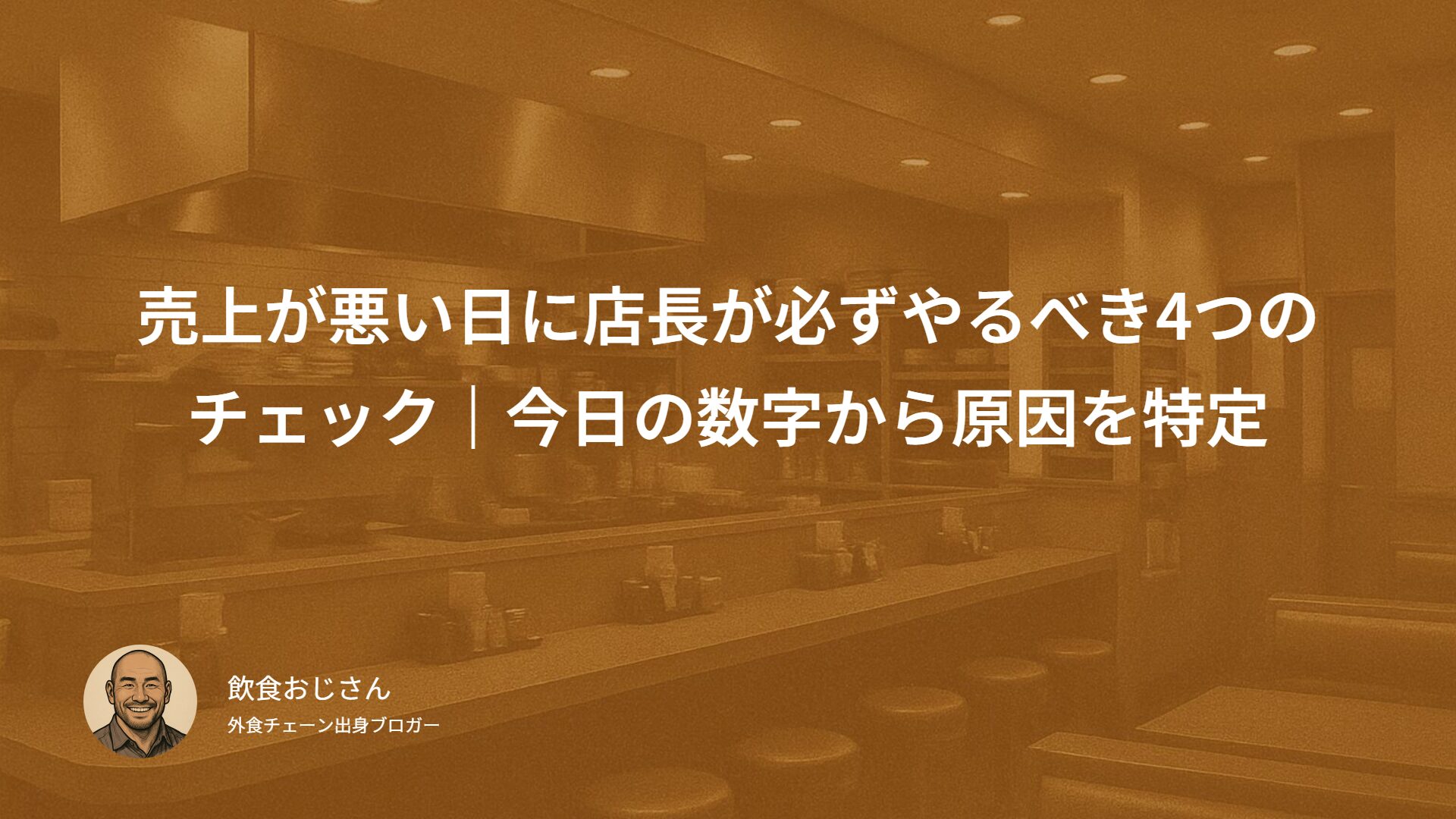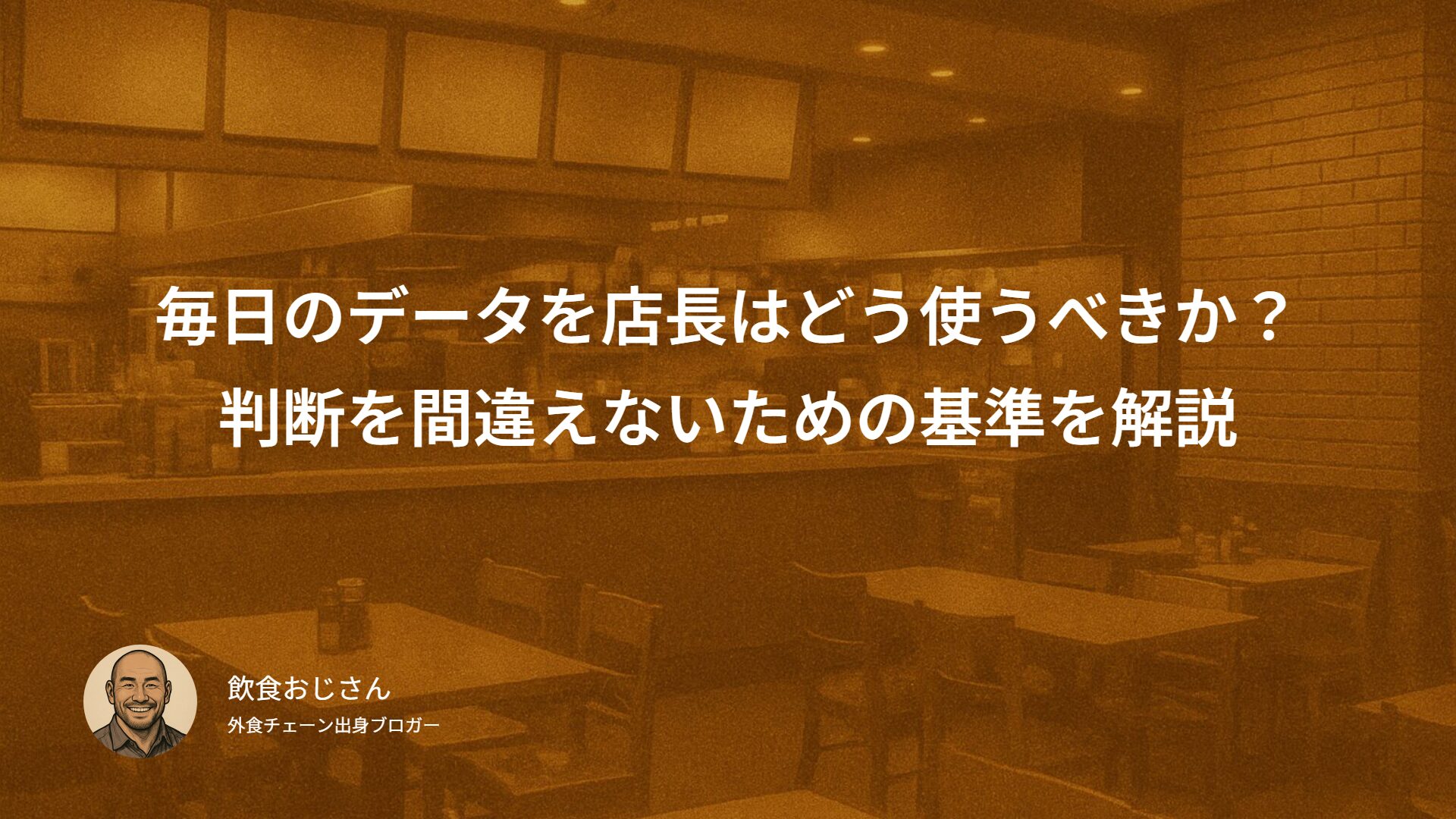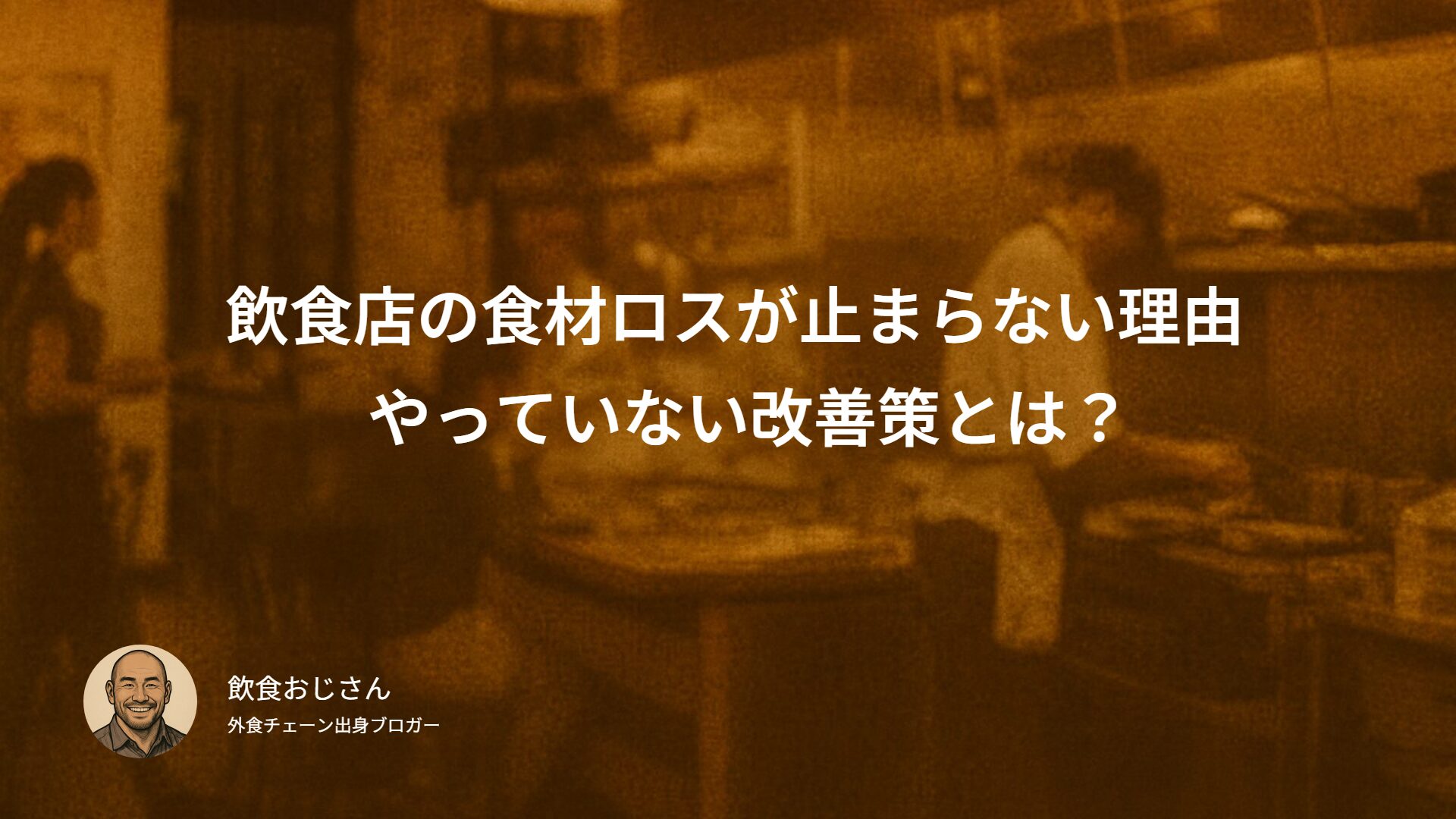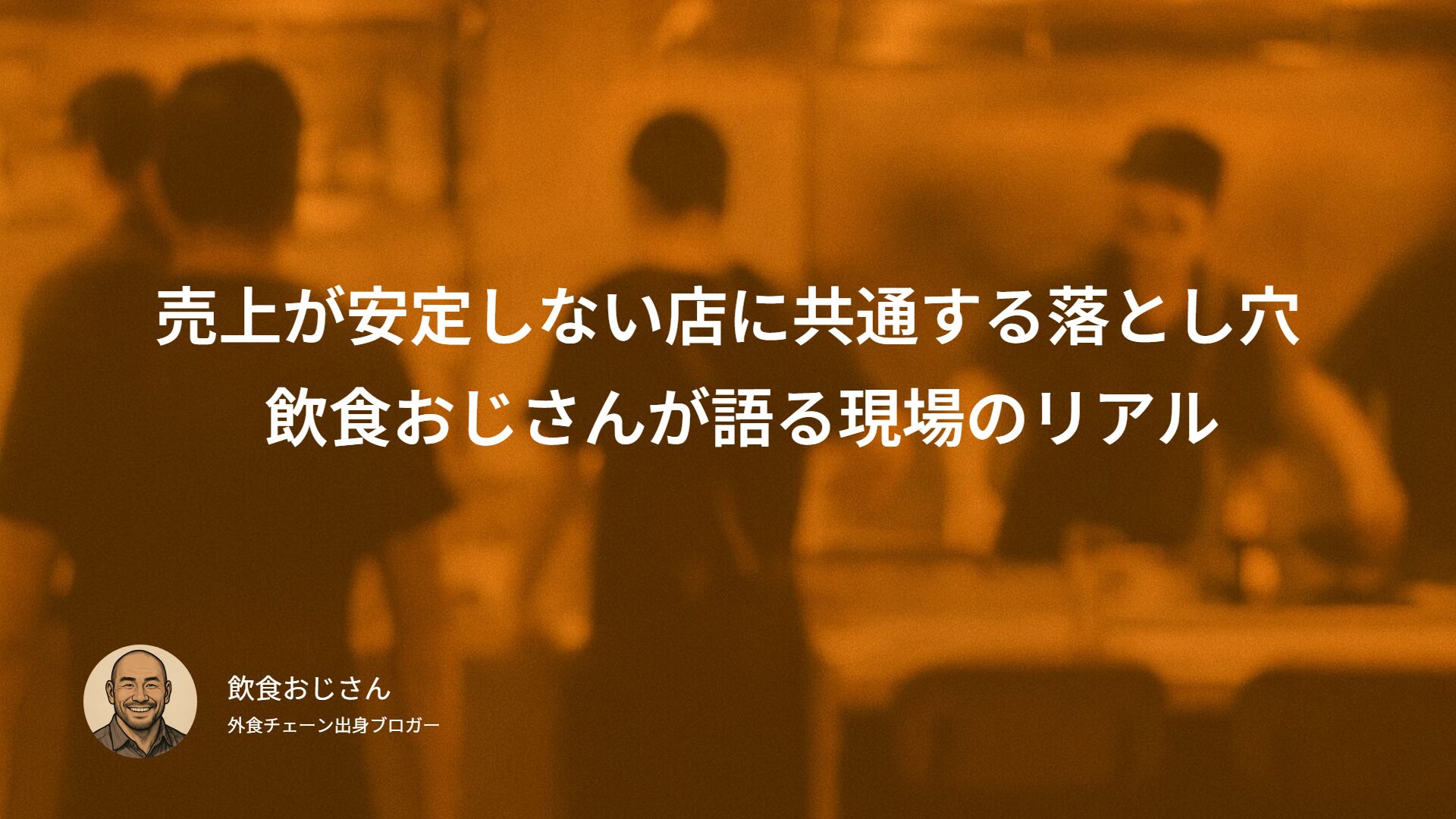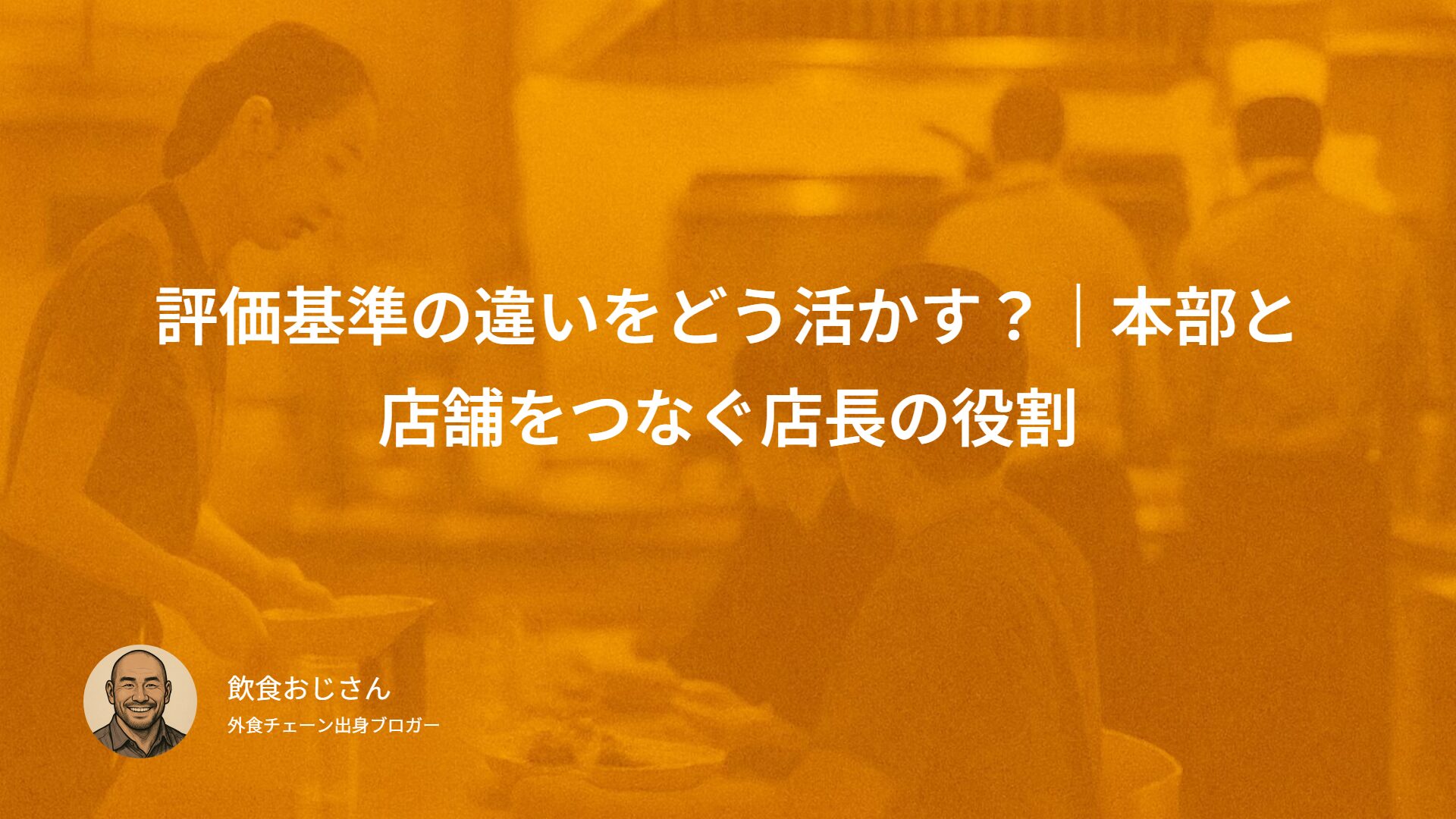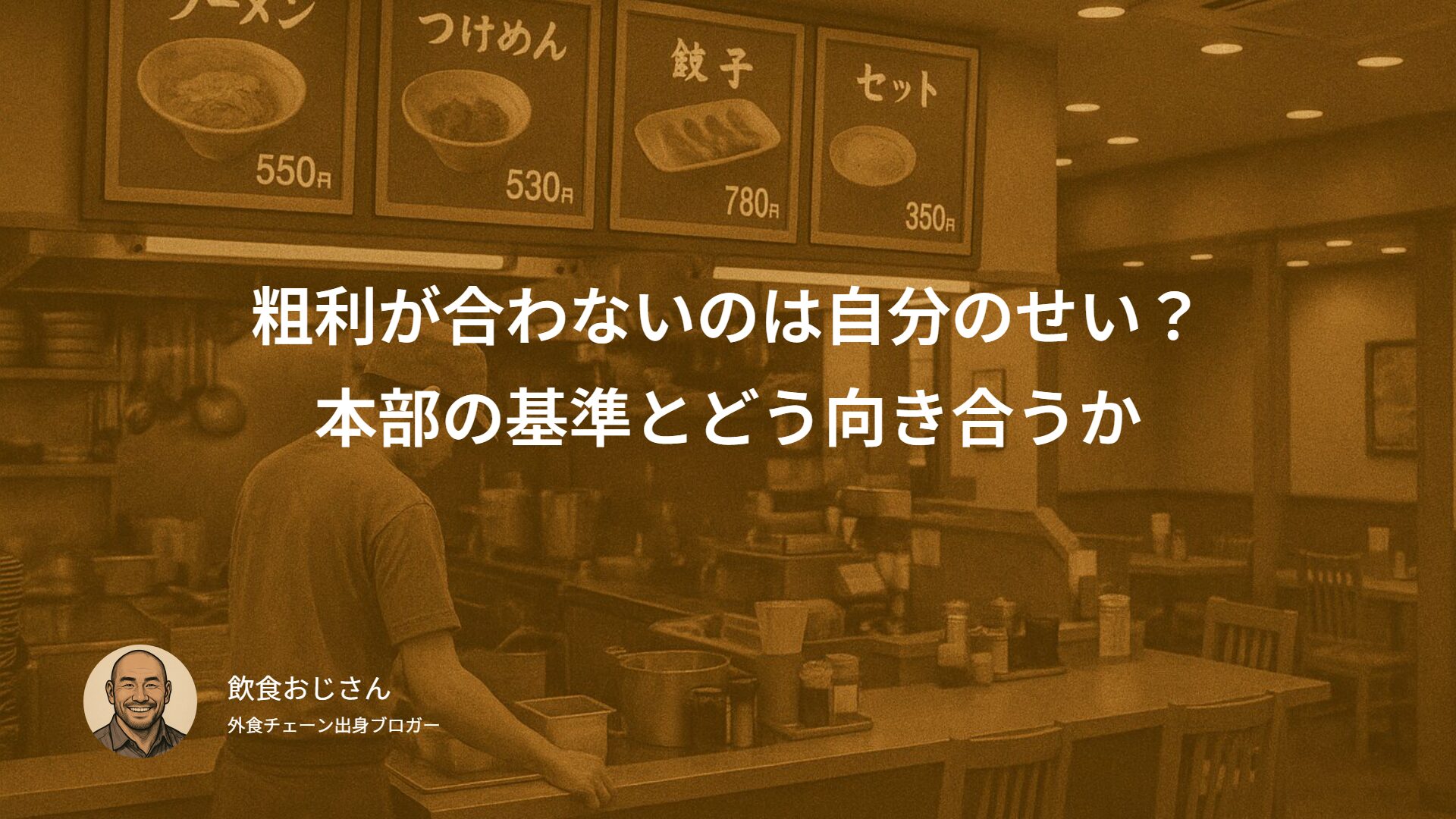店長が最低限見るべき数字3つ|数字の優先順位を間違えない考え方
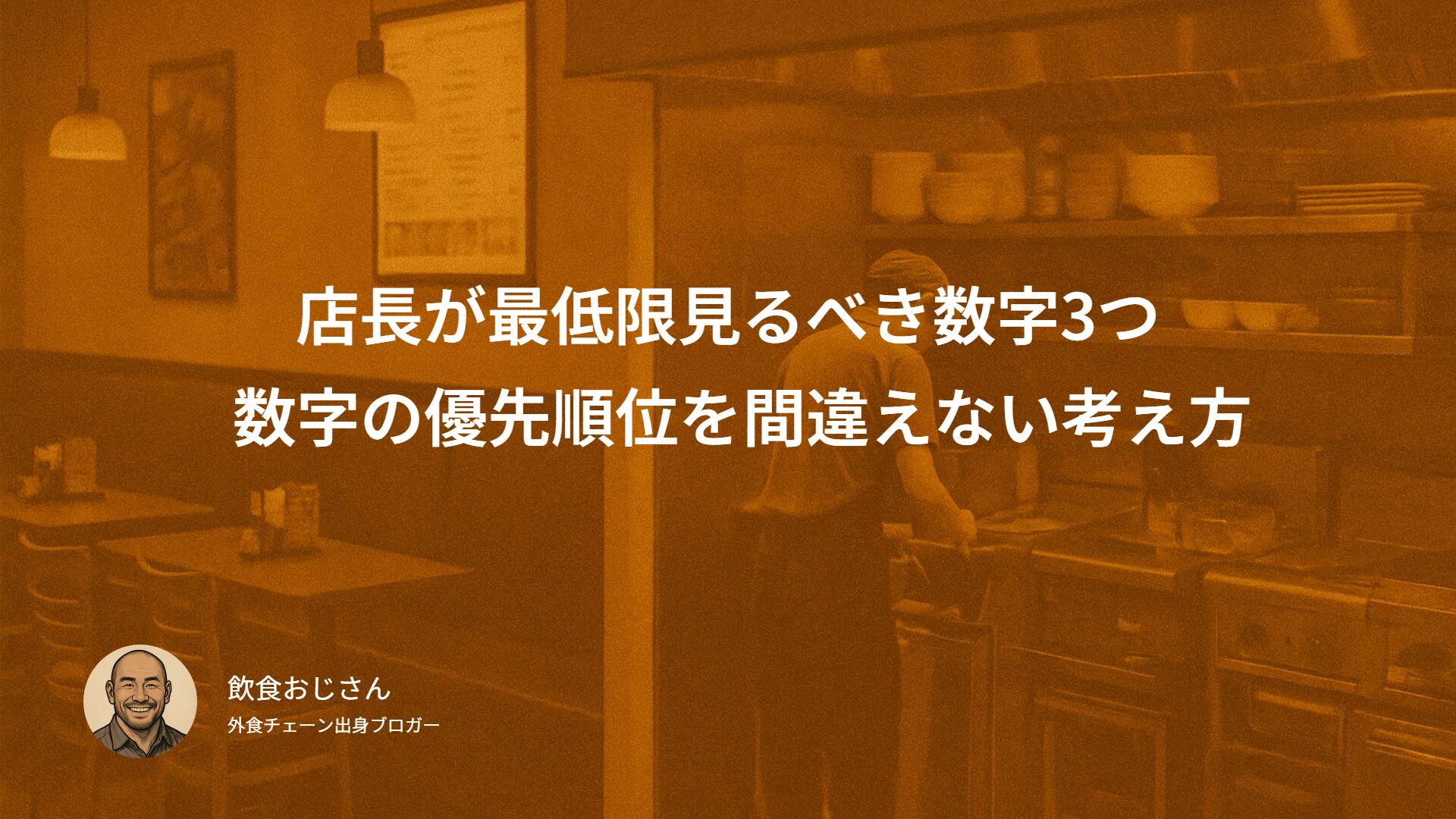
「数字が多すぎて、どこから見ればいいのか分からない」――そんな悩みを抱えていませんか?
売上、人件費、原価、客単価、粗利……。
毎日いろんな数字が報告されても、結局“何を優先すべきか”が曖昧なままになっていませんか?
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗運営に取り組んできました。

本記事では、店長が最低限見るべき3つの数字と、その正しい順番を紹介します。数字を整理するだけで、判断の迷いが減り、行動がスムーズになります。
✅ この記事を読むメリット
- 1日3分で数字を整理できる
- 判断ミスが減り、報告が明確になる
- スタッフとの共有がスムーズになる
数字は“追う”ものではなく、“使う”ものです。最後まで読めば、数字に振り回されずに判断できるようになります。
数字は“順番”で見ると判断が早くなる
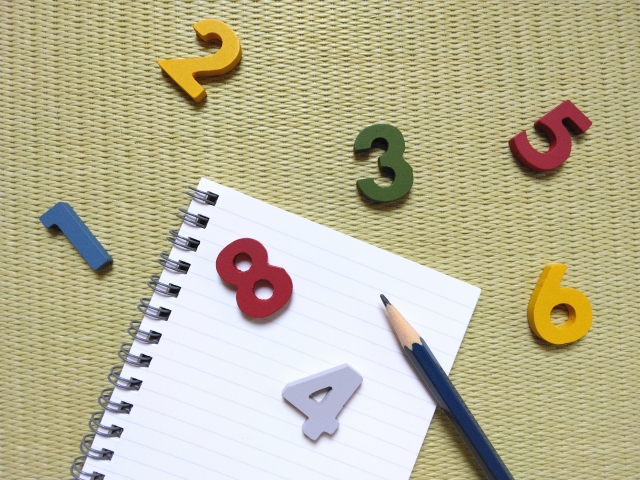
数字を見るのが苦手な店長ほど、「全部を見よう」として迷ってしまいます。
売上、人件費、原価、客単価、稼働時間……。
これらはどれも大切ですが、同時に見ると判断が止まるのが現実です。大事なのは、「どの数字から見るか」という順番です。
順番が決まっていれば、考える時間が短くなり、行動も速くなります。逆に、順番がないと「どれも気になる」状態になり、結果として手が止まります。
数字を“全部”見るほど判断が鈍る
数字は多いほど安心できそうに見えますが、実際は逆です。判断の基準が増えすぎると、どれを優先すべきか分からなくなります。
「粗利の高い商品を強化しよう」と思う人もいれば、
「人を減らそう」と考える人もいます。
どちらが正しいかは、そのときの流れの順番で変わります。数字を並べる順番を決めておけば、「今はどこを見るべきか」が明確になります。
数字の順番が“思考の流れ”を作る
数字の世界は、実は「上から下へ」とつながっています。売上が動くと、次に人件費率が変わり、最終的に粗利率へ反映される。
これを逆にすると、「結果を見てから原因を探す」流れになり、毎回の分析が後手になります。数字の流れを上から追うだけで、店の動きが“線”で見えるようになります。
数字を全部覚える必要はありません。3つの数字を、決まった順で見る。これだけで、判断スピードも報告の質も上がります。
数字の“順番”を決めるだけで、頭がすっきりします。考えるより、先に“並べて見る”ことです。

店長が見るべき数字3つとその意味

数字は「眺めるもの」ではなく、「行動を決めるための材料」です。
その中でも、店長が毎日チェックすべきなのは 売上(構成)・人件費率・粗利率(原価率) の3つ。この3つをセットで見れば、日々の判断が一気に整理されます。
① 売上(構成で見る)──動きを掴む起点
売上は「金額」ではなく「中身」で読みます。
客数
客単価
時間帯別・商品別構成比
これらを組み合わせると、お客の動きが見えてきます。
たとえば、客数が同じでも客単価だけ下がっている場合は、注文構成に変化が起きている証拠。人気メニューが偏っている、またはおすすめ商品の訴求が弱くなっているかもしれません。
売上の“中身”を見ることで、「どこにテコ入れすべきか」が明確になります。
数字の分析ではなく、“次の行動”を決めるための材料として扱う意識が大切です。
② 人件費率──“人数のかけ方”を見直す数字
人件費率は、店の“動き方”を映す数字です。高い・低いよりも、「どの時間に人をかけすぎているか」を見るのがポイントです。
たとえば、昼のピークが終わっても目的を持たずに人数を残していたり、夜のピーク時(夜のスタート時)に人が足りなくてお客さんを待たせてしまったり。
こうした時間のズレが積み重なると、働く力と数字のバランスが崩れていきます。
シフトは人数ではなく時間帯で考える。
- 売上の波に合わせて出勤・退勤をずらす
- 教育や仕込みは売上が落ち着く時間にまとめる
- 忙しい時間は1人多め、落ち着く時間は1人減らす
この調整を週に1回見直すだけでも、人件費率の変化がはっきり分かります。
③ 粗利率(原価率)──“数字の異常”を見抜く指標
粗利率は、普通に運営していれば簡単に動く数字ではありません。
メニュー構成や仕入れ単価は基本的に決まっていて、多少の廃棄やまかないがあっても、1%も動かないのが普通です。
だからこそ、粗利率が下がったときは「異常が起きている」と考えた方がいい。誤差ではなく、何かがズレています。
売上や仕入れの計上タイミングがずれている
廃棄やまかないの記録が抜けている
一部の食材が実際より多く使われている
こうした小さなズレが積み重なると、粗利率に現れます。
人件費率の1%ならシフトひとつで動きますが、粗利率の1%が下がるのは、何かが根本的におかしいサインです。
店長としてやるべきことは、「誰が悪い」ではなく「どこでズレたか」を探すこと。粗利は努力ではなく“整合性”で守る数字です。
粗利が崩れるのは、ミスか異常のサインです。焦って対策を打つより、まず“どこがずれたか”を冷静に確かめましょう。

👉 本部と店舗で考え方のズレに悩んでいる方は、次の記事も参考にしてください。

毎日3分でできる数字ルーチン

数字を“分析する時間”を作るのではなく、確認と調整の時間を毎日短く取ることが大切です。
数字は、長く考えるよりも「同じ手順を繰り返す」ことで安定します。
✅ 数字は「順番」と「目的」で見る
数字をすべて追う必要はありません。時間帯ごとに目的を決めて見るだけで十分です。
- 開店前(1分):前日までの売上を前年・前月と比較。
数字の流れを見て「今日がどう動きそうか」を予測する。 - 昼ピーク前(1分):人件費を確認。
シフトの入り方と稼働予定を見て、「このままで回るか」を判断する。 - 閉店後(1分):ロス・廃棄・報告を確認。
異常があれば原因を探り、翌日の仕込みや発注に反映する。
この流れを“毎日同じ順番で繰り返す”ことで、数字の変化に強くなります。分析ではなく、“確認の習慣”にすることが目的です。
数字を使いこなす店長の1日チェックリスト
| タイミング | 確認項目 | 現実的にできること | 数字の意味 |
|---|---|---|---|
| 開店前 | 売上:前年・前月との比較 | 昨日までの売上累計と前年比、曜日比較をざっと見る | トレンド・流れの確認(外部環境) |
| 昼ピーク前 | 人件費:当日予定・累計 | シフト人数と稼働時間、1日単位の人件費率を確認 | 日常調整(店の体制) |
| 閉店後 | 粗利:大きなロス・廃棄・報告有無 | 廃棄・返品・調理ロスの報告を確認 | 異常値・ズレの早期発見 |
✅ 数字はチームで共有してこそ意味がある
数字を1人で抱え込むより、チームで共有した方が動きが早いです。
たとえば朝礼で一言伝えるだけでも、意識がそろいます。
数字を“叱るため”ではなく、“整えるため”に共有する。それが数字を扱う店長のスタイルです。
数字は報告じゃなく“会話の材料”です。チームで共有すれば、判断のズレも減っていきます。

まとめ|数字の優先順位を決めると店が安定する
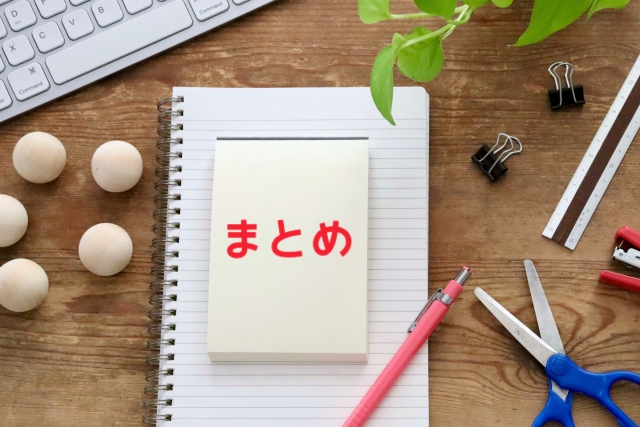
店長が見るべき数字とその順番をもう一度確認
- 見るべき数字は3つだけ:①売上(前年・前月比較)②人件費率(1日単位)③粗利率(異常値チェック)
- 見る順番が判断を決める:「売上 → 人件費 → 粗利」で考えると原因と結果がつながる
- 数字は管理ではなく確認:目的は“評価”ではなく“修正と準備”
- 人を責めずに数字で見る:数字は感情ではなく、次の行動を決める材料
数字を「追う」ではなく「使う」視点に変えるだけで、判断の迷いがなくなります。毎日のチェックが3分でも、積み重なれば店の流れそのものが安定します。
「数字は“監視”じゃなく“地図”です。どこに向かうかを決めるのは店長の仕事。数字はその道しるべになります。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 チームの基礎力を上げたい方は、次の記事も参考にしてください。