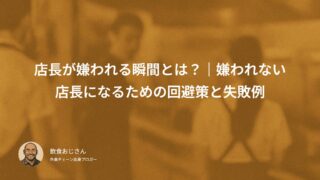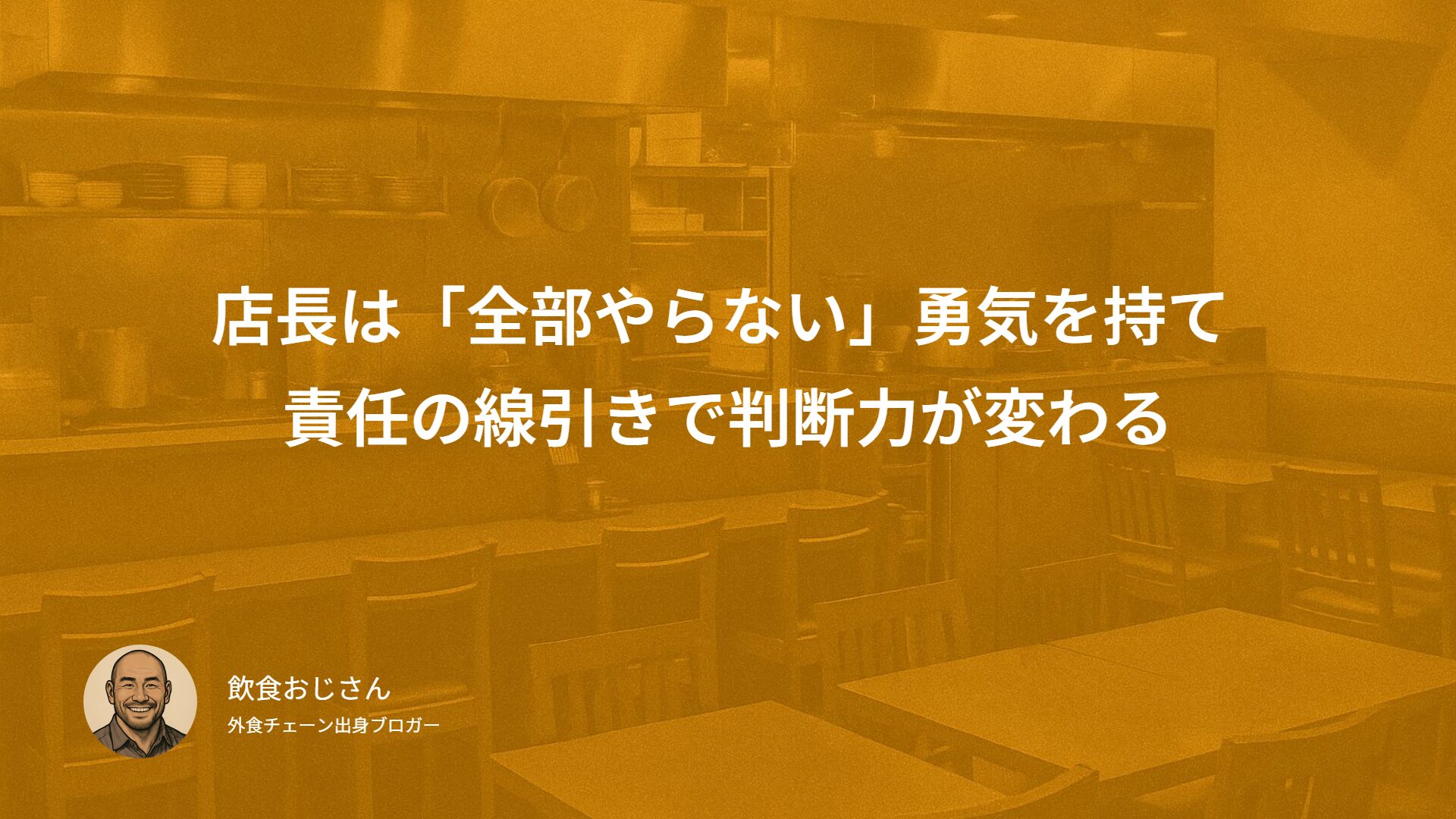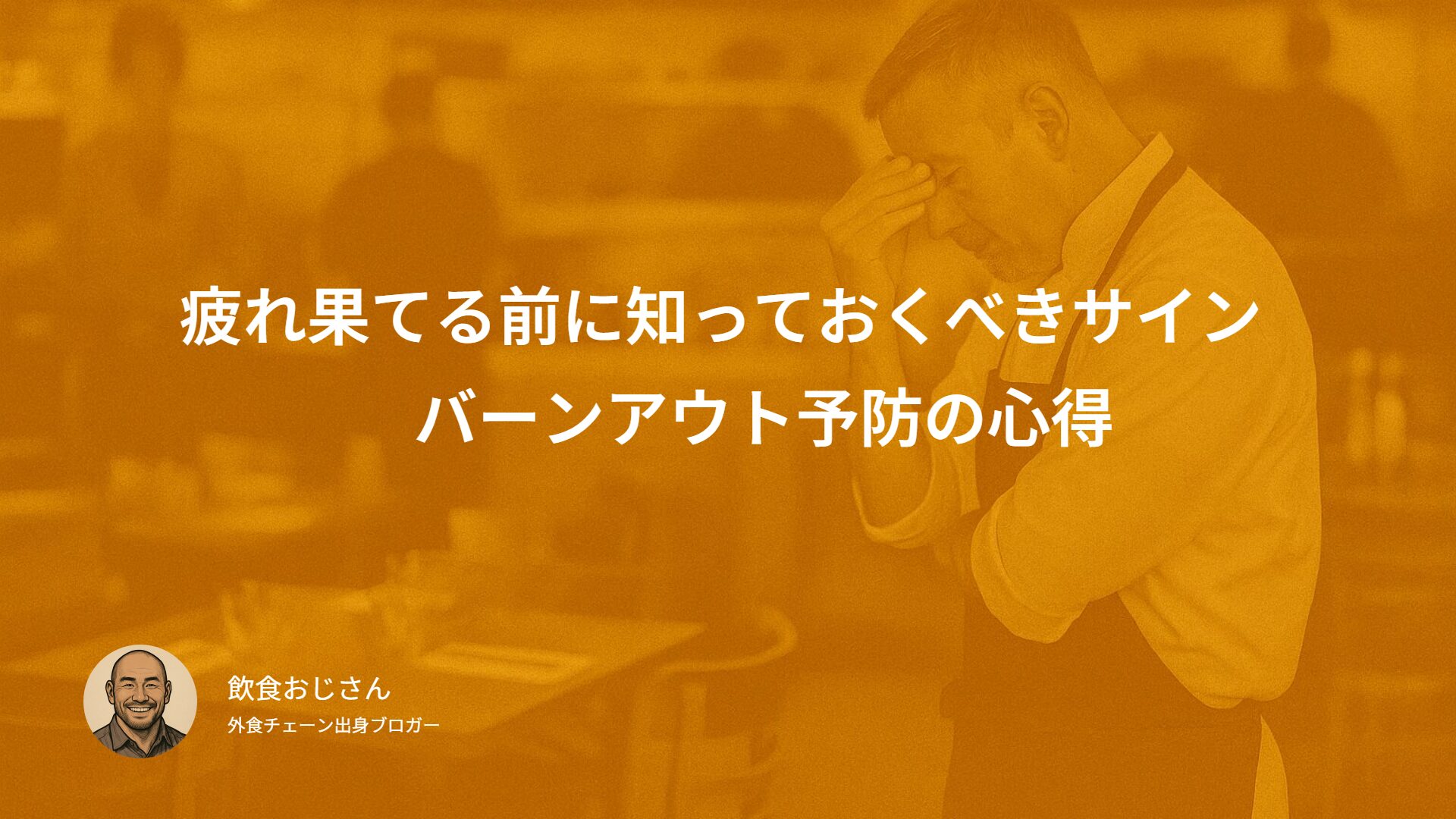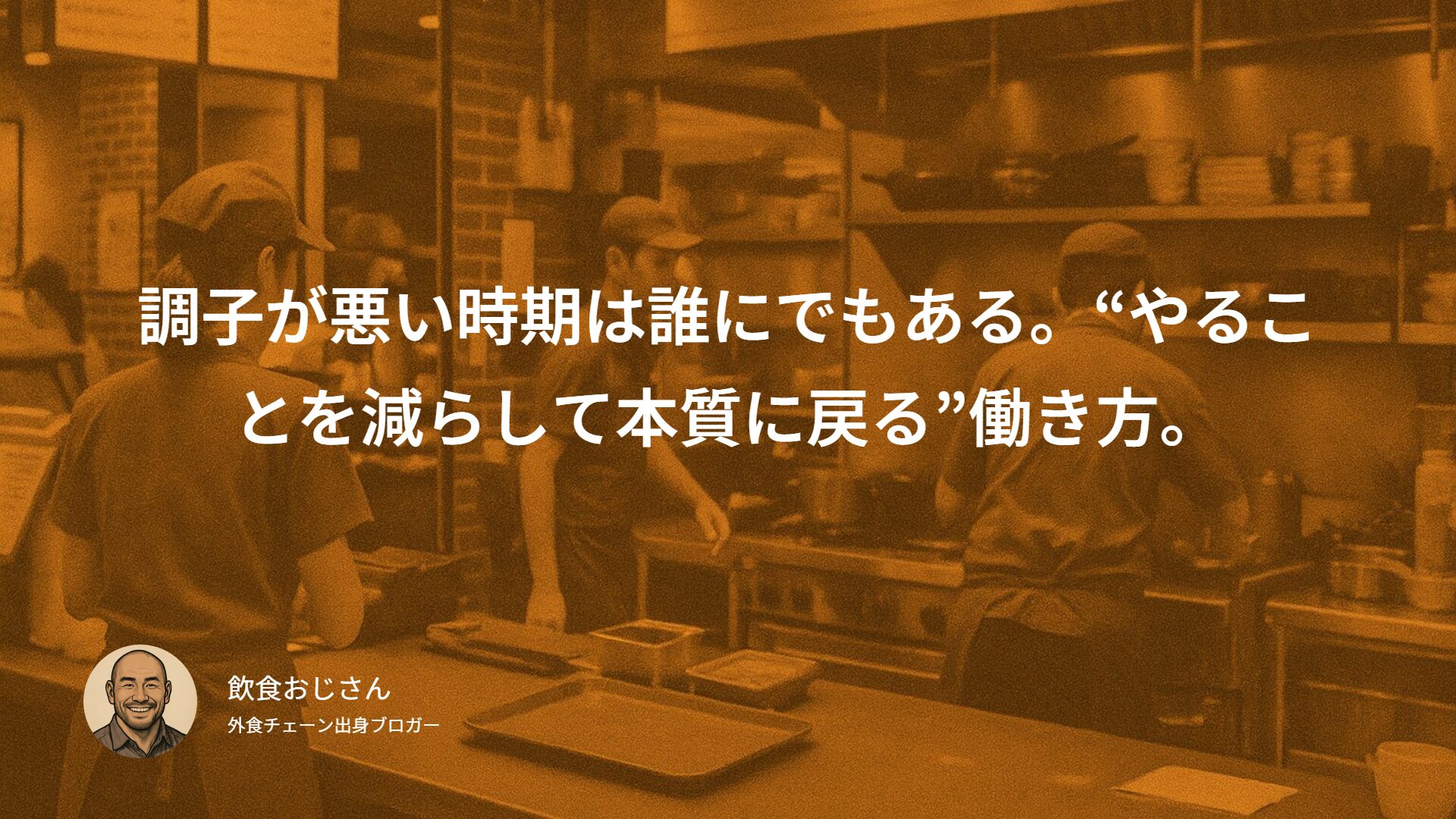状況に流されない店長の考え方|疲れているときこそ“軸”が問われる
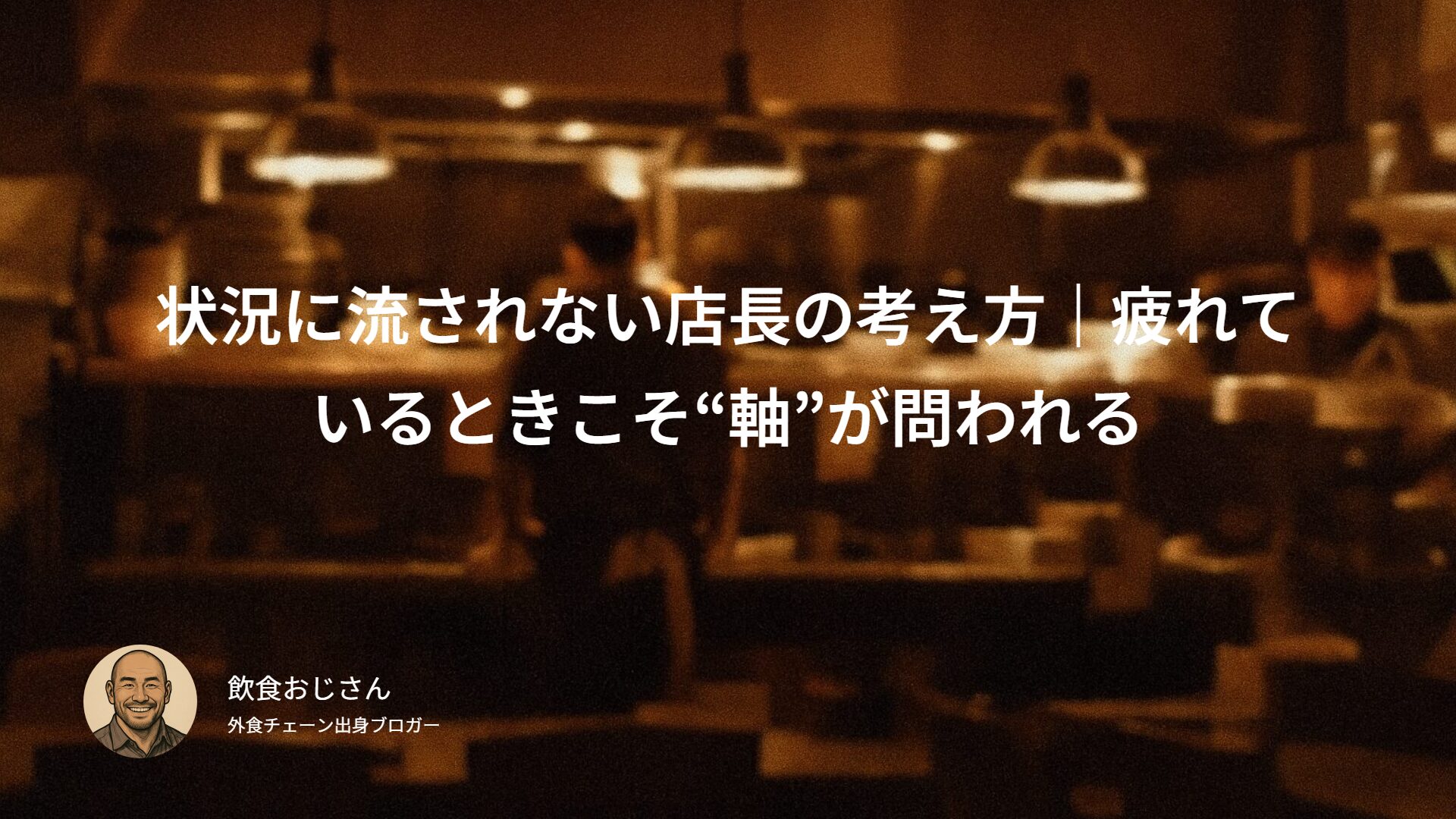
「疲れていた」
「状況が悪かった」
――そう言い訳したくなるときほど、判断の本質が試されます。
店長という立場は、どんな状況でも決めなければならない仕事です。だからこそ、「疲れているときにどう考えるか」で、結果が分かれます。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗運営に取り組んできました。

判断は体調ではなく、基準の問題です。状況に流されて判断を変える人は、どんな場面でも迷います。
一方で、基準を持つ人は疲れていてもブレない。この差が、信頼を積み上げるかどうかを決めます。
この記事では、
- 判断を状況に逃がさない考え方
- 疲れていてもブレない店長の習慣
- 判断を磨くための思考整理法
を解説します。状況を理由にしない判断こそ、店長としての“軸”になります。
判断の重さを“状況”に逃がさない

「忙しかった」「疲れてた」は事実でも理由にはならない
店を任されていると、思うようにいかない日は必ずあります。人が足りない日もあれば、体調が万全ではない日もあります。
けれど、それを理由に判断を誤った瞬間、責任の矢印が自分から外へ向いてしまいます。「状況が悪かった」と言えば一時は楽になりますが、その癖がつくと基準が曖昧になります。
状況に合わせて決めるのではなく、状況が変わっても大切にする価値を決めておくことが大事です。
その基準がある人は、疲れていても迷いが少なくなります。判断の質は環境ではなく、自分の姿勢で決まります。
判断とは“条件”ではなく“責任”の積み重ね
判断に理想的な条件などありません。完璧な情報も、十分な時間も揃うことはほとんどありません。それでも決めなければならないのが店長の仕事です。
条件が整わないと動けない人は、いつまでも判断を先送りにします。一方で、自分の責任として決める人は、結果が悪くても修正できます。
店の信頼は、正解を出すことではなく、決断を自分で引き受ける姿勢で積み上がります。
“状況が悪かった”は説明であって理由ではありません。決める覚悟を手放した瞬間、信頼は静かに削られていくのです。

軸を持つ店長がやっている3つの習慣

小さな判断でも基準を言語化する
多くの人は「大きな決断」には時間をかけますが、日常の小さな判断ほど感情で流してしまいがちです。
たとえば「今日の優先順位」や「スタッフへの一言」。この積み重ねが、店の空気をつくります。
だからこそ、どんな小さな判断にも自分の基準を言葉にしておくことが大切です。
「自分がこう思うからこう決める」と言語化すると、判断に一貫性が出ます。言葉にした基準は、迷ったときに戻る“原点”になります。
人の意見を聞いても最後は自分で決める
スタッフや上司の意見を聞くことは大切です。しかし、どんなに参考になる意見でも、最後に決めるのは店長自身です。
人の意見をそのまま採用すると、結果が悪かったときに責任を押し付けたくなります。それでは信頼を失います。
意見を聞く目的は、自分の判断を磨くためです。
さまざまな考えを取り入れながらも、最終的に自分で決める姿勢が、「この人についていこう」と思わせるリーダーシップにつながります。
状況より「店として正しいか」で考える
その場の空気や人間関係に流される判断は、一時的には楽です。しかし、長い目で見ると、店全体を迷わせます。
迷ったときこそ、
「自分に都合が良いか」ではなく「店として正しいか」を基準に決めることです。
店長の判断が店の方向を決めます。その判断が一貫していれば、スタッフは安心して動けます。
どんな状況でも「店としての正しさ」を優先する人こそ、本当の意味での“軸を持つ店長”です。
判断を誰かに委ねると、信頼も一緒に手放します。最後に決めるのは、いつだって自分です。

👉 疲れを感じたときに見逃してはいけないサインを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
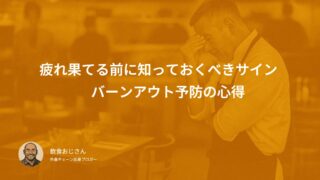
判断を鍛える思考と行動のトレーニング

✅ 考えを整える(判断の前に立ち止まる)
判断を誤る多くの原因は、「考え抜く前に動くこと」です。焦って答えを出そうとすると、判断が浅くなり、後でやり直しが増えます。
店長の仕事はスピードも大切ですが、迷ったら一度立ち止まって考える時間を取るほうが、結果的に早くなります。
考えるときは、次の3点を短く整理すると効果的です。
5分でも構いません。その短い“間”が、判断を整える冷却時間になります。急いで動く人より、立ち止まって考える人のほうが、結果的に店を安定させます。
✅ 行動に落とす(判断を小さく試す)
考えるだけでは判断は強くなりません。判断は行動の中で磨かれます。
まずは小さな判断を日常で試すことです。
スタッフへの伝え方を少し変えてみる
発注のタイミングを一歩早めてみる
自分の言葉で説明できる範囲だけを実行する
いきなり大きな決断をする必要はありません。小さな判断を繰り返すことで、「選んだ結果どうなったか」を体で覚えていきます。
これが判断を鍛える一番確実な方法です。
✅ 継続させる(判断の基準を習慣化する)
一度の成功や失敗で終わらせず、判断を振り返る習慣を持つことです。
「なぜそう決めたのか」を短く記録する
「結果はどうだったか」を客観的に書く
「次はどうするか」を1行で決めておく
振り返りは自分を責める作業ではありません。過去の自分に学ぶ時間です。判断を記録し、改善していく人は、経験の“量”ではなく質が高まります。
判断を振り返るメモを残す
判断のメモは1行で十分です。
この2行を積み重ねるだけで、判断力は確実に鍛えられます。迷ったときにそのメモを見返すと、冷静さを取り戻せます。
判断は才能ではありません。毎日の“選び方”を磨く習慣が、信頼を生むんです。

まとめ|判断に逃げない店長が信頼をつくる

判断の軸がある人は、状況が悪くてもぶれない
判断とは、状況や感情に左右されず、自分で責任を引き受ける姿勢の積み重ねです。
この記事の要点を整理します。
- 「忙しかった」「疲れてた」は理由ではなく状況
- 判断の質は環境ではなく、自分の姿勢で決まる
- 判断を鍛えるには、考える→試す→振り返るの繰り返し
- 責任を引き受ける人が、最終的に信頼を得る
判断を間違えることよりも、判断を避けることのほうがリスクです。状況が悪いときほど、基準を持ち、冷静に決める力が試されます。
「正解を出すより、信頼を積み上げる判断をしましょう。」毎日“本当に”おつかれさまです。」

👉 スタッフに嫌われない関わり方を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。