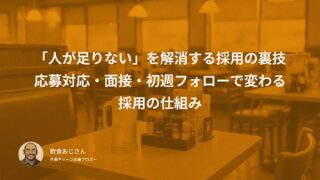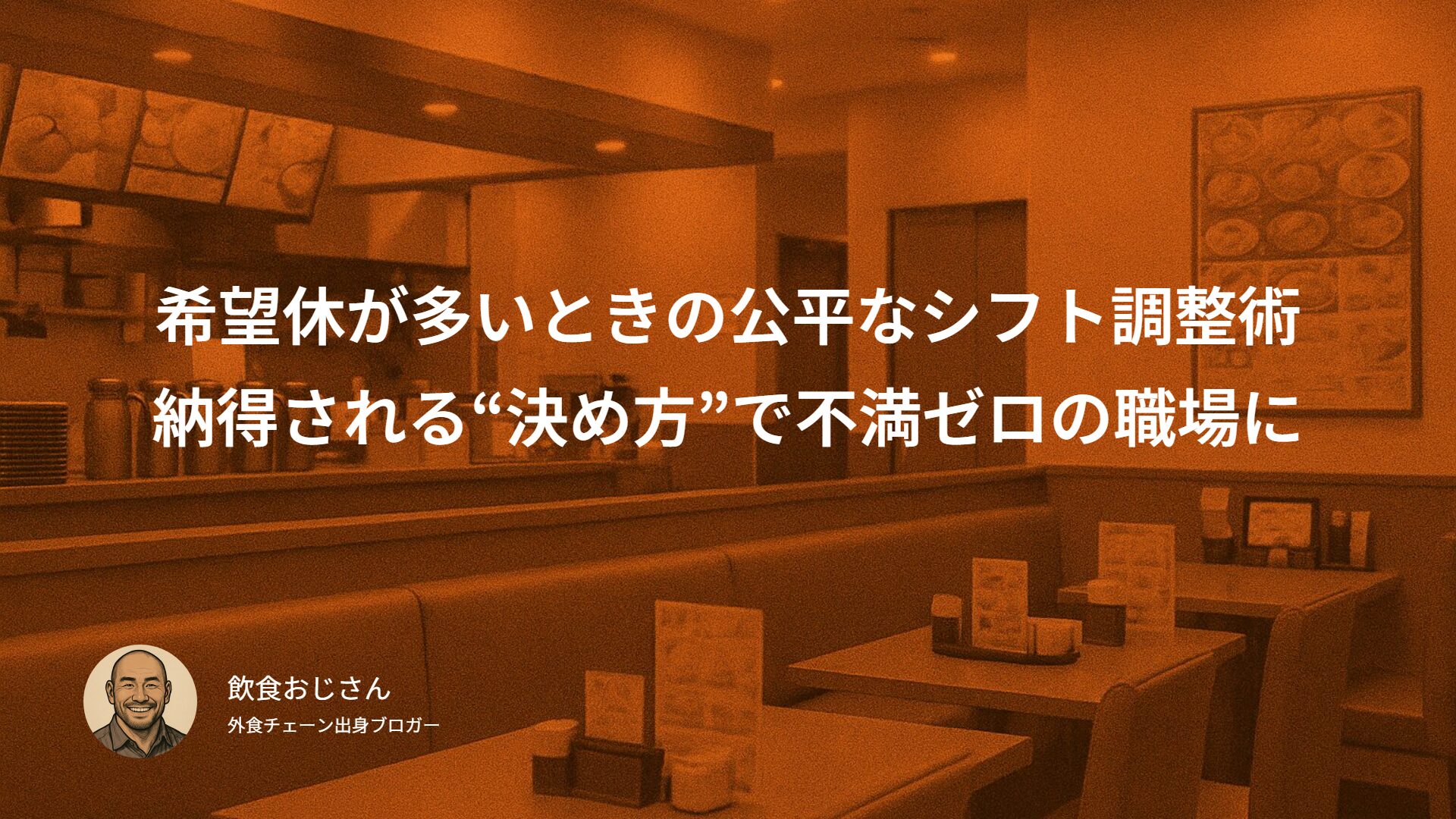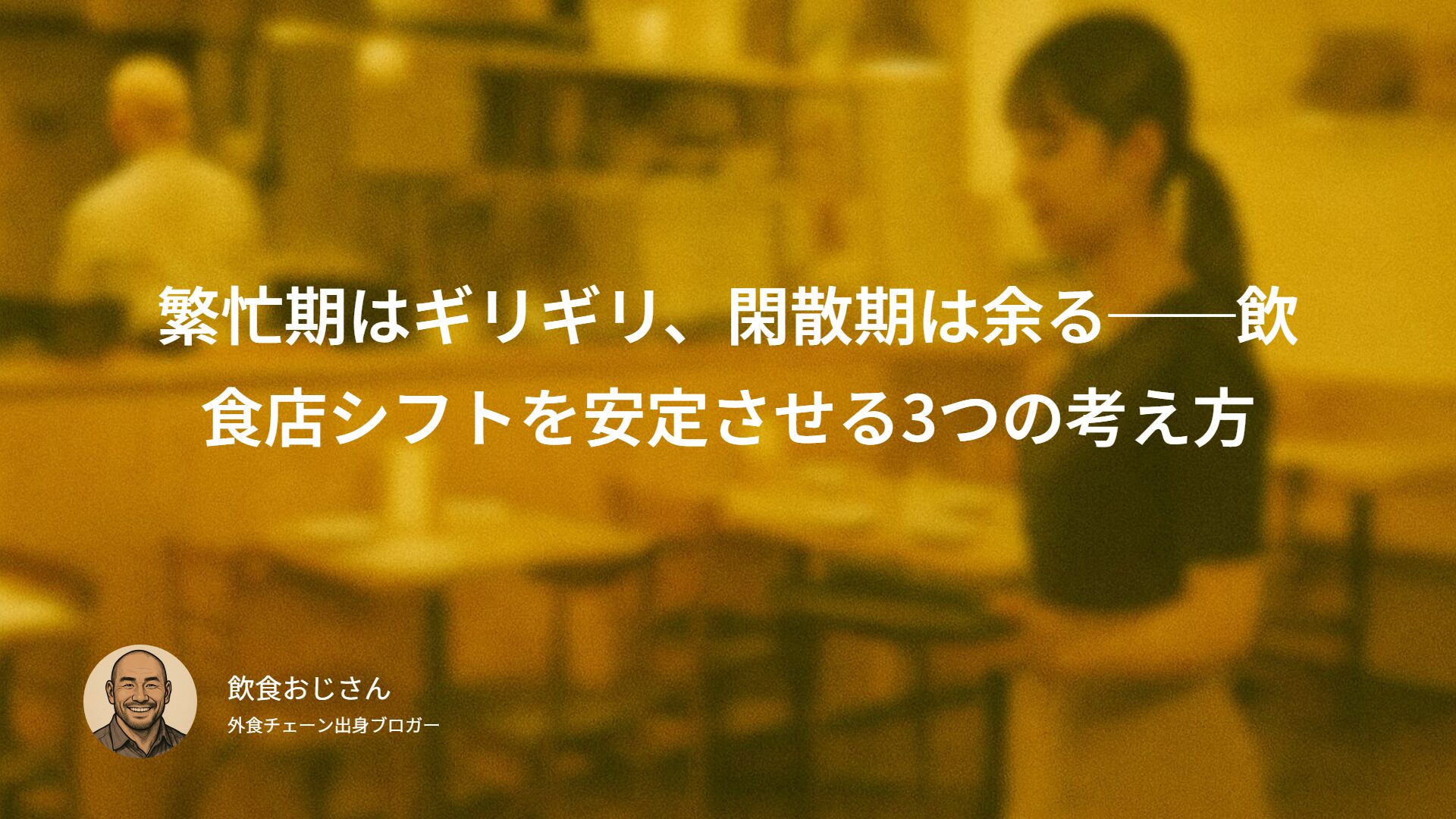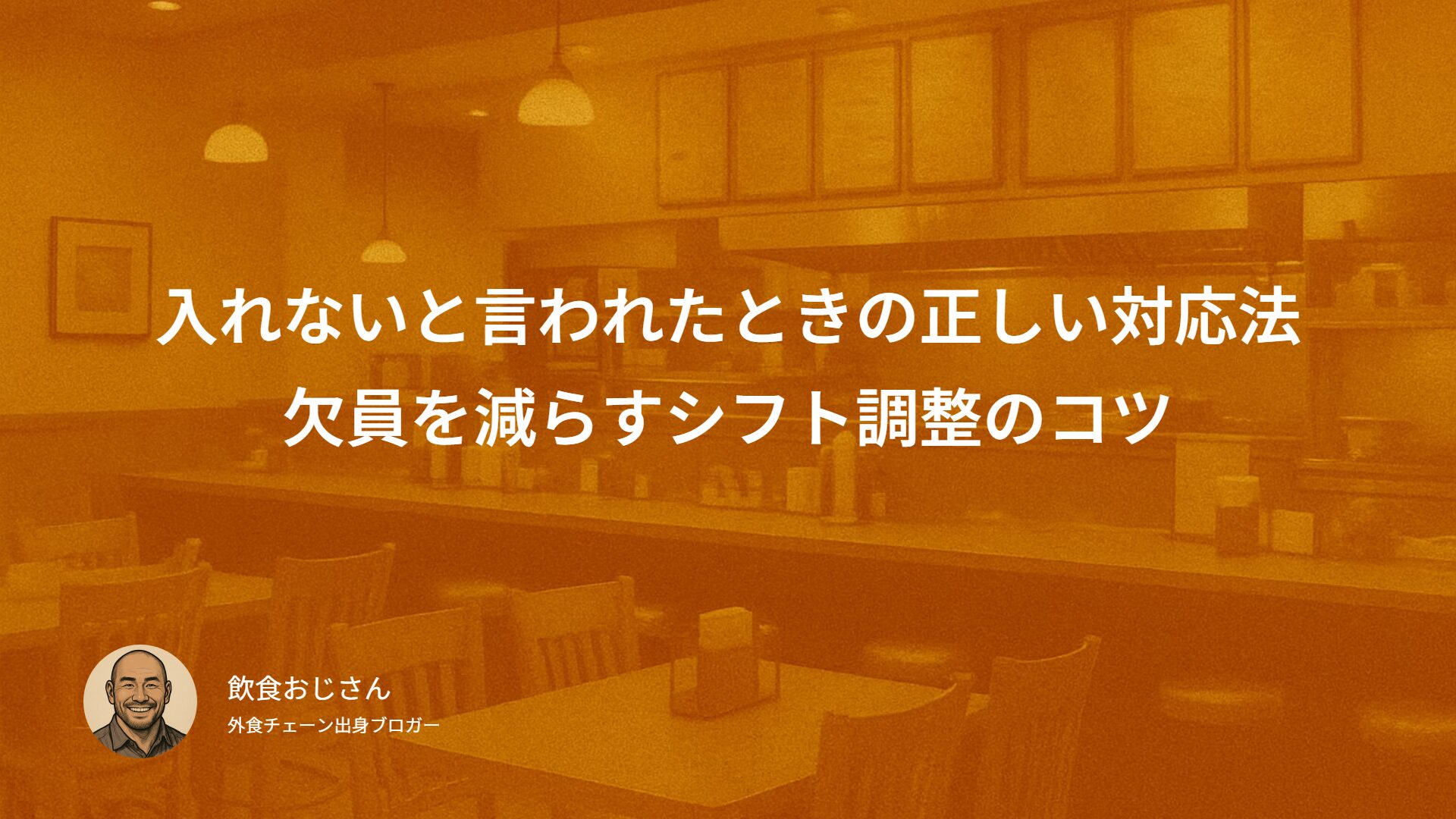シフトが毎回ギリギリになる原因と解決法|飲食店のシフト設計の基本
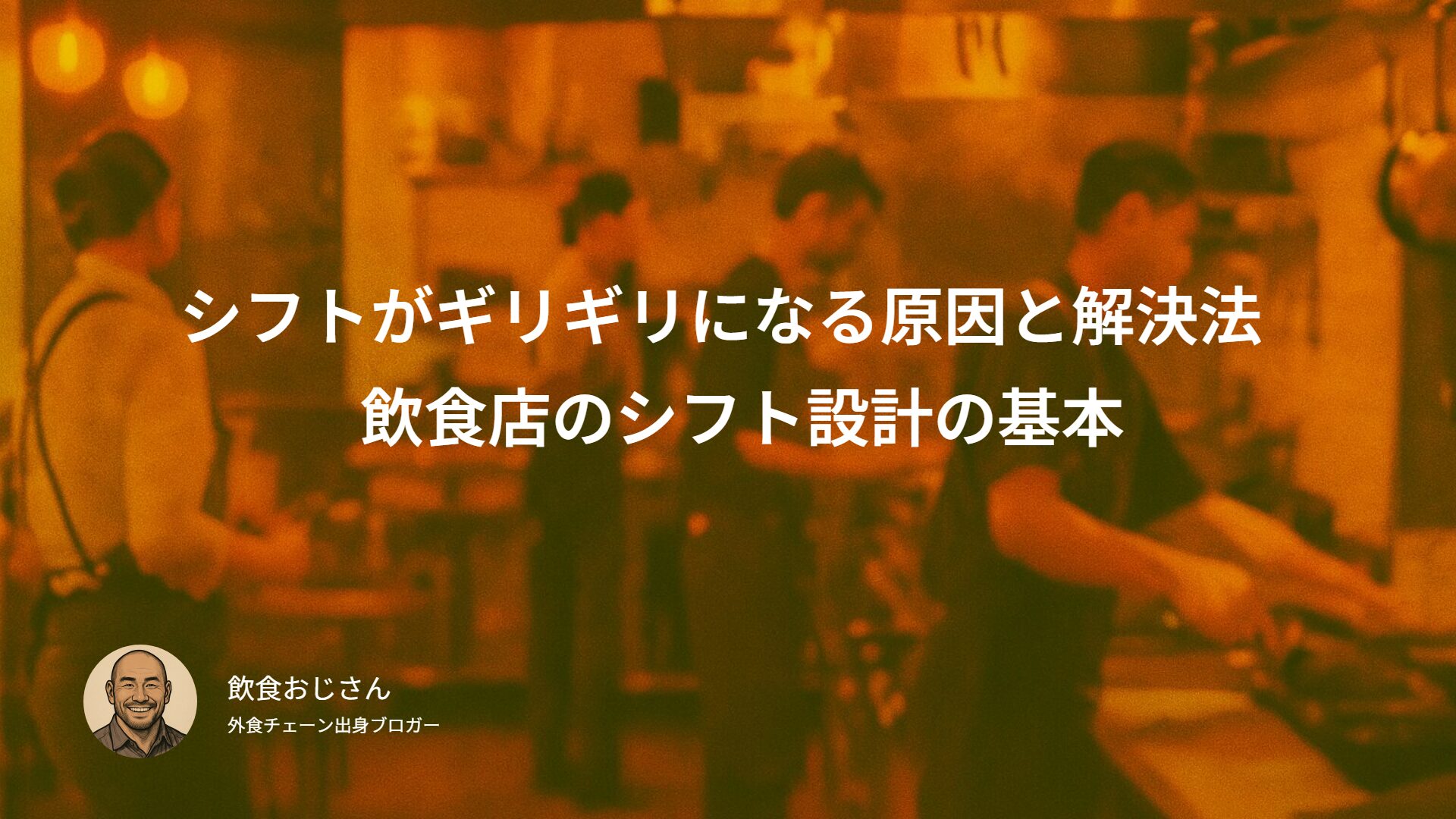
シフト表の作成が毎回ギリギリ――そんな悩みを抱えていませんか?
「スタッフの希望休が多すぎて調整がつかない」
「結局、店長が穴埋めしている」
…。多くの飲食店で同じような状況が繰り返されています。
おはようございます、“飲食おじさん” です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗経営に取り組んできました。

私自身も店長時代、シフトが完成するのは締切直前。スタッフからの追加連絡に追われ、深夜に何度も組み直した経験があります。
ですが後から振り返ると、それは“人の問題”ではなく“仕組みの不在”が原因でした。
この記事では、シフトが毎回ギリギリになる原因と、その解決法を原理原則から整理します。
✅ この記事を読むメリット
- ギリギリになる本当の原因を「人・仕組み・数字」の3視点で理解できる
- 今日からできるシフト改善の具体策がわかる
- 店長が無理せずラクになる「シフト設計の基本」を学べる
「頑張って埋める」から「仕組みで整える」へ。最後まで読めば、シフトに振り回されない店づくりのヒントが必ず見つかります。
なぜシフトはいつもギリギリになるのか

現場で繰り返される混乱
シフトが間に合わないのは、ほとんどの店で同じ“あるある”が重なっているからです。
こうした要因が重なり、店長は予定調整に追われます。
結果として、売上管理やスタッフ育成といった本来やるべきマネジメントの時間が削られてしまうのです。
本質は「仕組みの不在」
一見すると「スタッフの問題」に思えますが、実際は違います。
根っこにあるのは――
- 誰が休んでも最低限まわせる仕組みがない
- 人数配置のルールが曖昧で、毎回ゼロから考えてしまう
つまり、設計思想が欠けていることこそが最大の原因です。
現場の混乱は、人ではなく「仕組み」に起因している。ここを押さえない限り、シフトはいつまでもギリギリのままです。

原因の掘り下げ(人・仕組み・数字)

人の側面 ― 特性を無視した配置
学生はテスト期間や長期休みに左右されやすく、主婦は家庭の予定、フリーターはWワーク……。
それぞれの生活リズムや特性を無視して「とりあえず空いている枠に入れる」形で組むと、直前の欠員や不満が発生します。
仕組みの側面 ― ルール不在のゼロベース運用
多くの店で、シフト作成は「店長の頭の中」だけで進みます。
ルールやフォーマットがないため、毎回ゼロから調整することになり、無駄に時間がかかります。
数字の側面 ― 感覚頼みの必要人数
「この曜日はだいたい4人で足りるだろう」――こんな感覚だけで人数を決めていませんか?
実際には、売上や客数とリンクしていないため、人件費が膨らむ一方でピークタイムは人が足りない、というアンバランスが起きます。
厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報』によると、飲食サービス業等の平均月間実労働時間は88.6時間、所定外労働時間は5.2時間で、業界全体で労働時間の短縮が進んでいる傾向が見られる(PACOLA労務・人事ニュース)。
人の問題に見えて、実は“仕組みと数字”の問題なんです。ここを押さえるだけで、シフトの安定感は一気に変わりますよ。

シフトがギリギリになる原因の3分類表
| 分類 | 典型的な問題 |
|---|---|
| 人の側面 | 学生・主婦・フリーターなど特性を無視した配置/希望休が多くて調整不能 |
| 仕組みの側面 | シフト作成ルールがなく毎回ゼロベース/店長の頭の中だけで運用 |
| 数字の側面 | 必要人数を感覚で決めてしまう/人件費や客数と連動していない |
👉 希望休が多いときでも不満を出さずに、公平なシフトを組みたい方は、次の記事も参考にしてください。
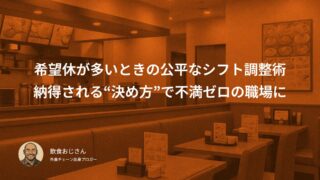
解決策|シフト設計の基本

✅ すぐにできる短期的改善
まずは、明日からでも取り入れられるシンプルな工夫です。
シフト表に「最低必要人数」を明示する
希望休は必ず“締切制”にする
欠員が出たときのために「代打リスト」を準備しておく
👉 これだけでも「最後まで人が埋まらない」状況をかなり防げます。
✅ 役割分担による中期的仕組み化
学生・主婦・フリーター、それぞれの特性を活かす配置がポイントです。
さらに、シフト作成を店長一人に抱え込ませず、副店長やリーダーも関わることで属人化を防ぎます。
✅ 数字を活かした長期的仕組み化
シフトの安定は、最終的には数字との連動が欠かせません。
例:「土日のピークは去年より客数が増えそうだから、最低ラインに1人加えるくらいの余裕を見ておく」
例:「2万円の売上が見込める時間帯は、スタッフは最低3人必要」
例:「アプリで希望休を自動集計してくれる」「穴埋めをLINEで自動通知する」
改善ステップ(短期→中期→長期)
| ステップ | 改善内容 |
|---|---|
| 短期(すぐできる) | 最低必要人数を明示/希望休の締切ルール/欠員対応リストを準備 |
| 中期(仕組み化) | 学生・主婦・フリーターを役割分担で配置/シフト作成を副店長・リーダーに分担 |
| 長期(安定化) | 売上や来客データをもとに必要人数を算出/シフト作成ツールで自動化 |
現場で実感した成功体験
私自身も「締切ルール」と「代打リスト」を導入したことで、欠員対応をほとんどスタッフ同士で解決できるようになりました。
結果として、店長が穴埋めで走り回るゼロの状態を実現。
シフトに追われなくなった分、スタッフ教育や売上分析に時間を割けるようになり、店舗全体の安定につながりました。
完璧を目指す必要はありません。短期→中期→長期と、一歩ずつ“仕組み”を積み上げれば、シフトは必ず安定しますよ。

まとめ|飲食店のシフト設計を安定させるポイント

現場で押さえるべき3つの視点
- シフトがギリギリになるのは「人の問題」ではなく「仕組み不在」
- 人・仕組み・数字の3視点で設計すれば混乱は減る
- 完璧より「仕組みの積み重ね」がチームを強くする
シフト管理は、店長の勘や気合いでなんとかするものではありません。
“再現性のある仕組み”を持つことで、店長の負担もスタッフの不安も大きく減らせます。
「シフトが崩れるのは仕組みがない証拠。小さなルール化を積み重ねれば、必ず安定しますよ。」毎日“本当に”おつかれさまです!

👉 人手不足を解消して、応募から定着までスムーズに進めたい方は、次の記事も参考にしてください。