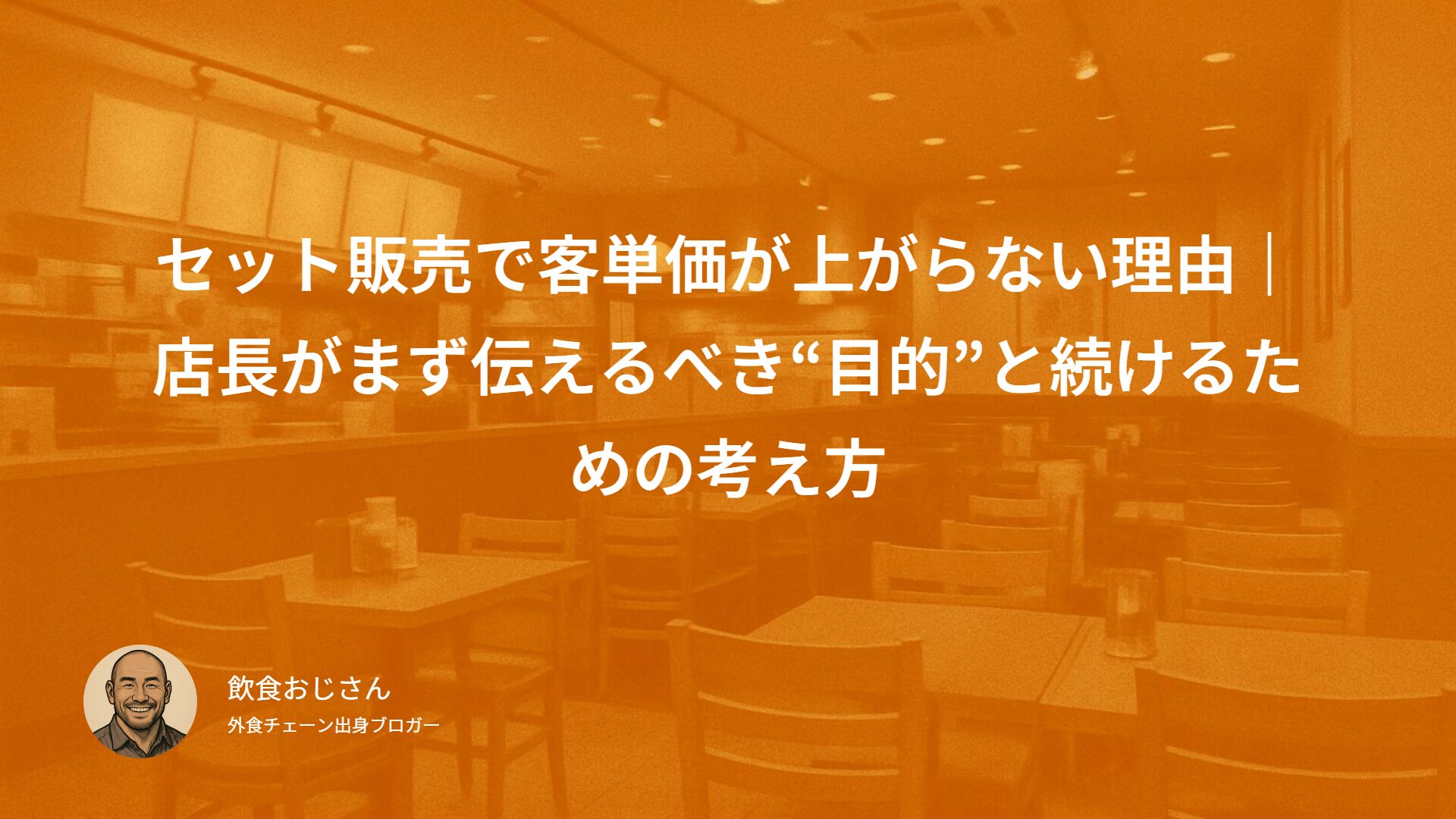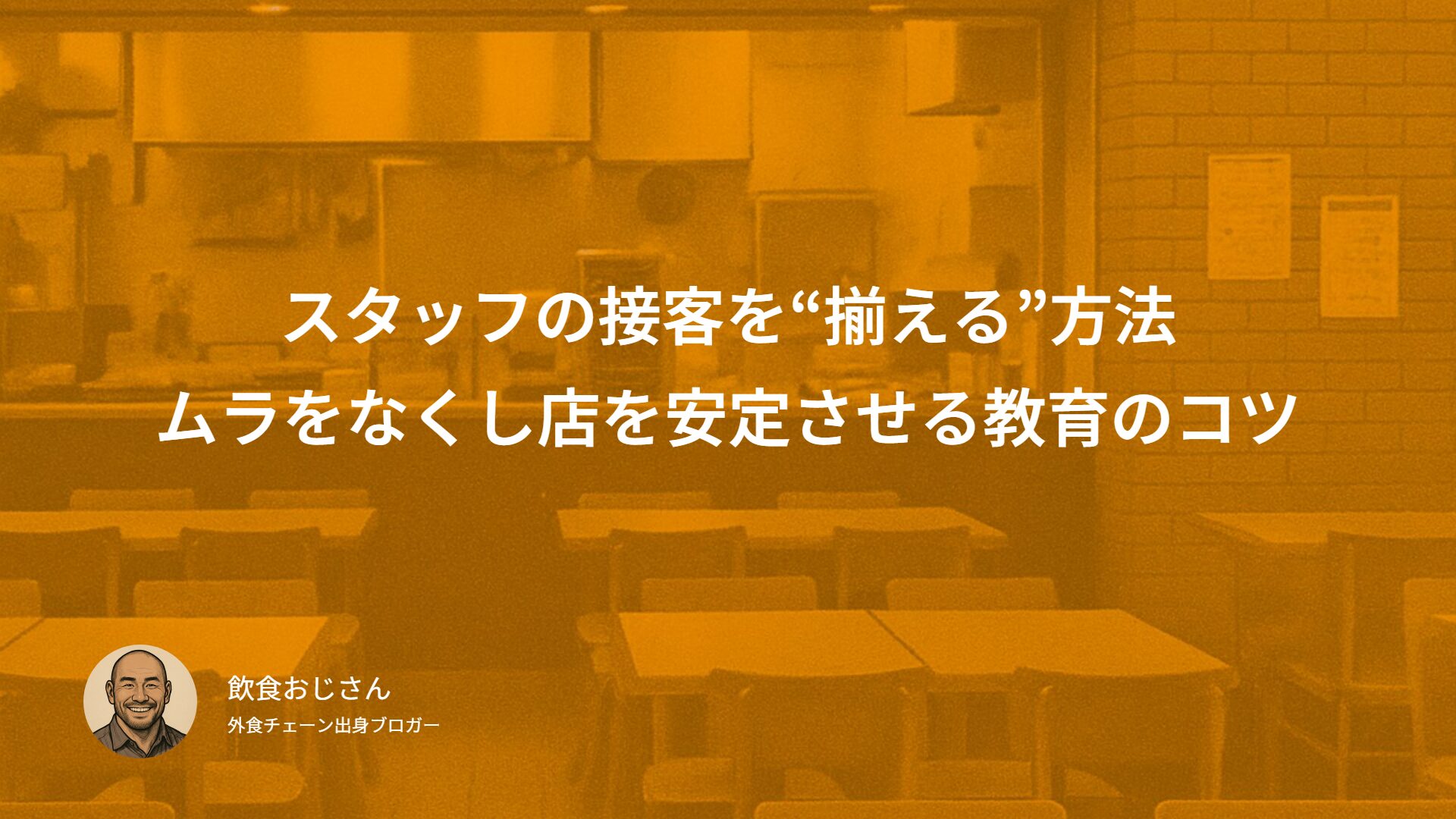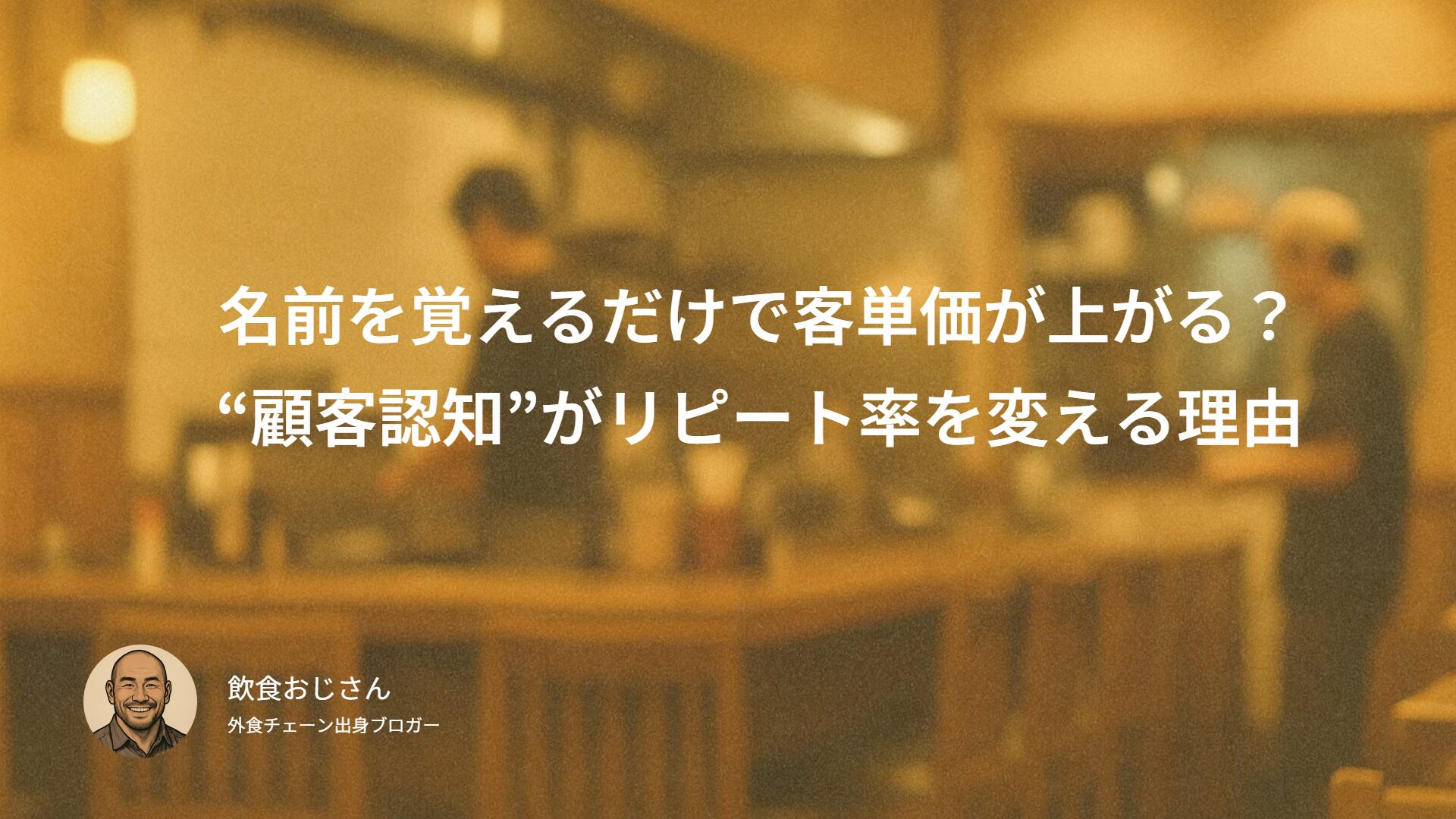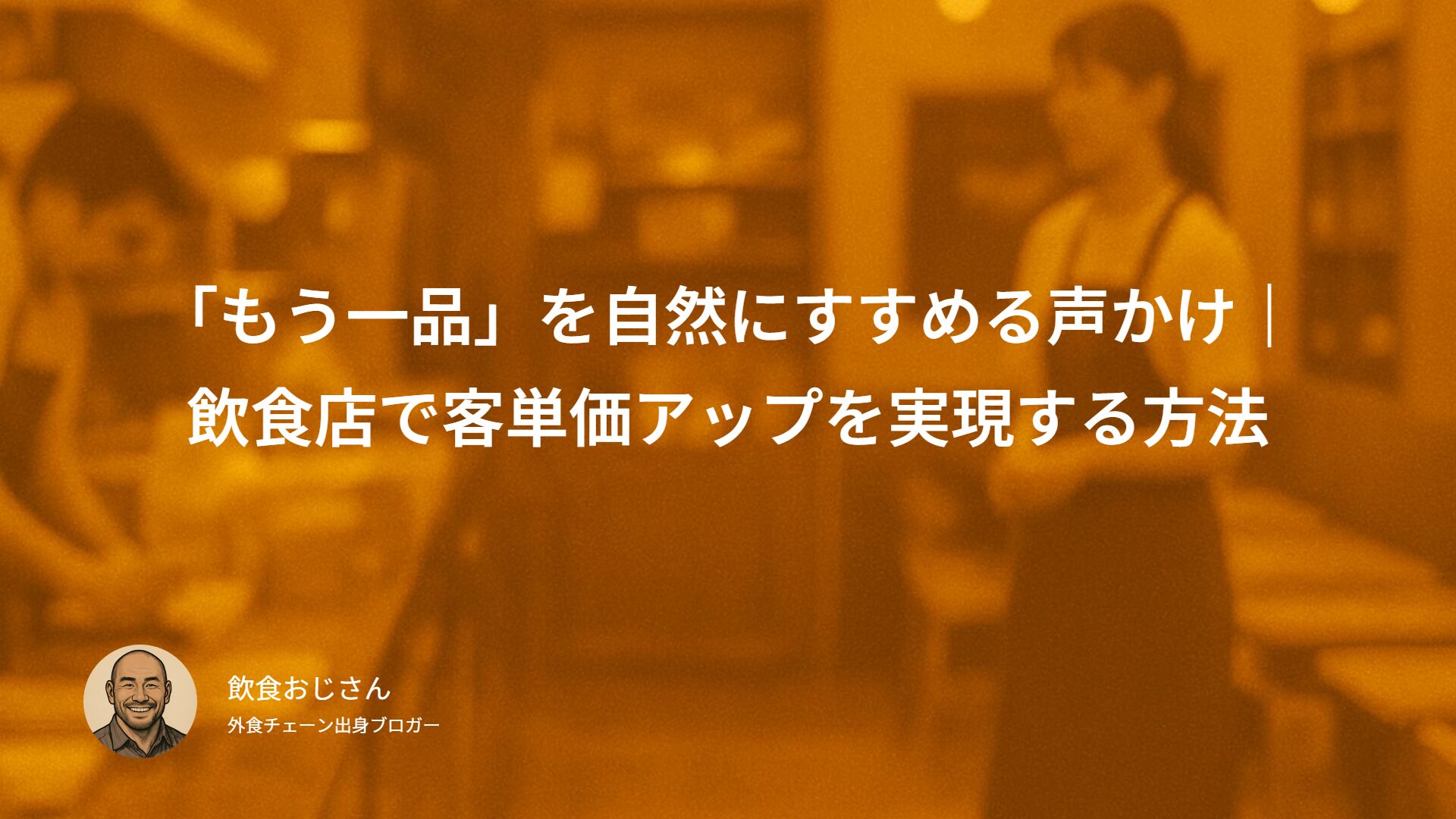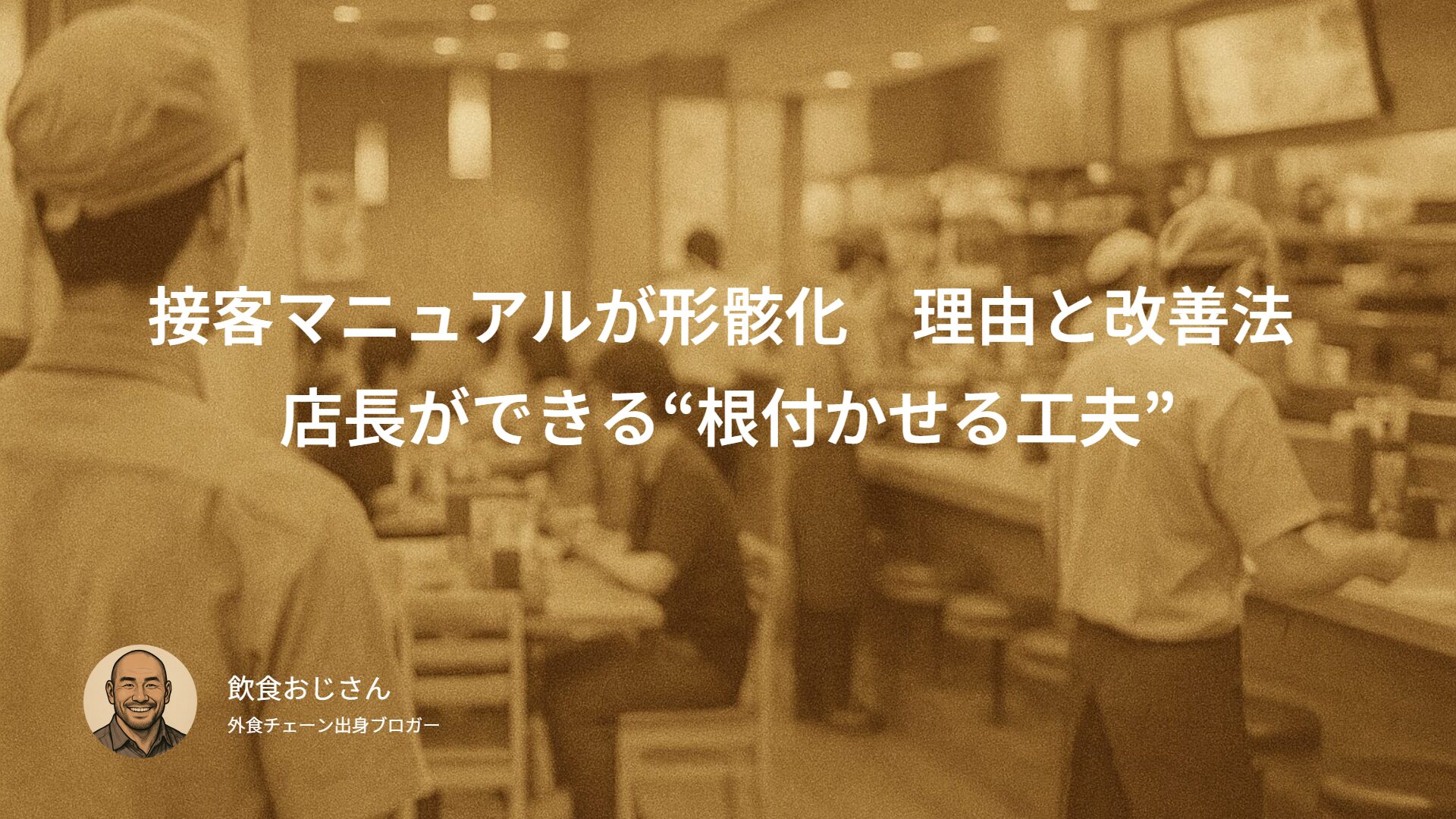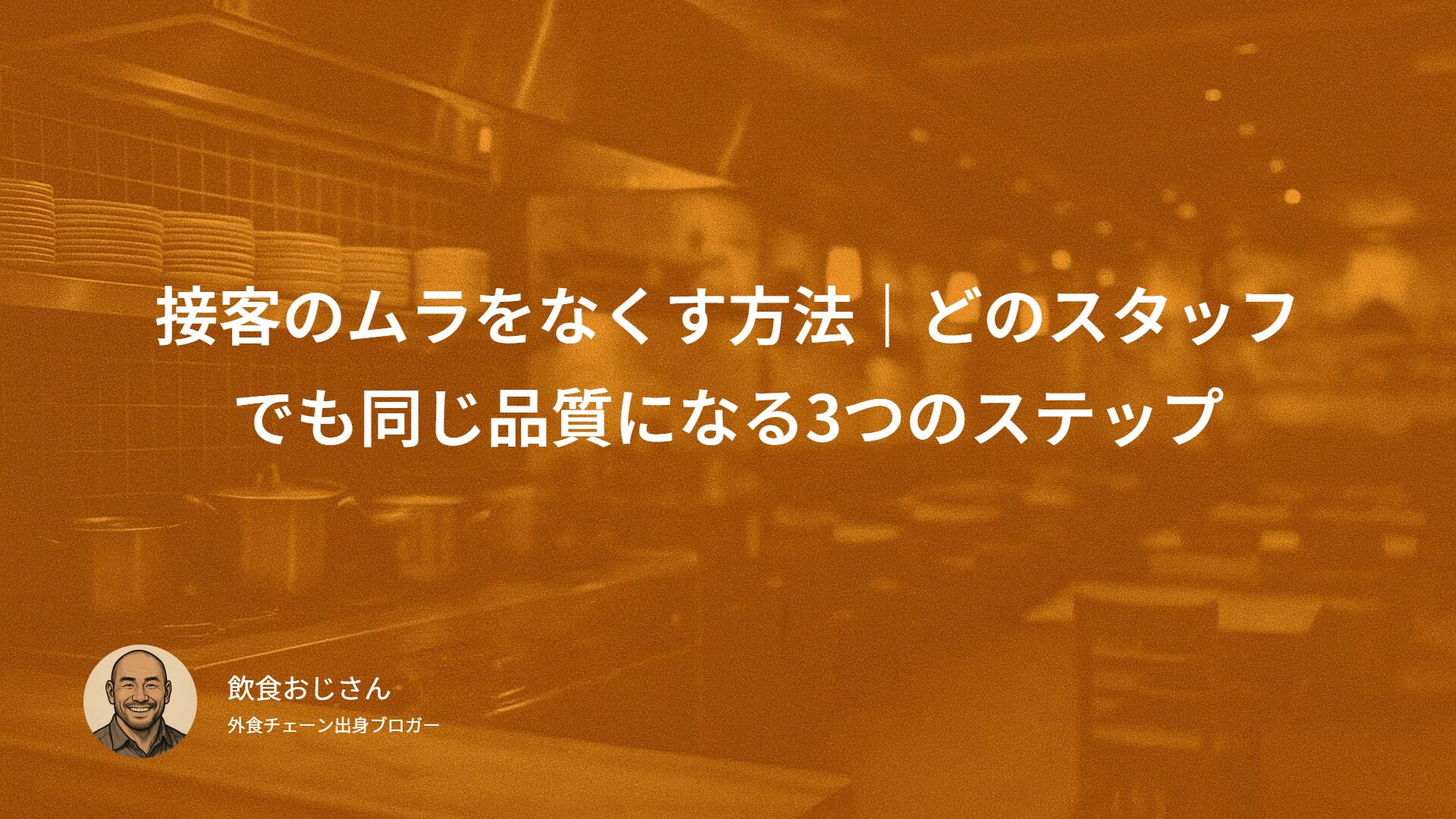ドリンクで利益を最大化する方法|飲食店が客単価を上げるシンプルな仕組み
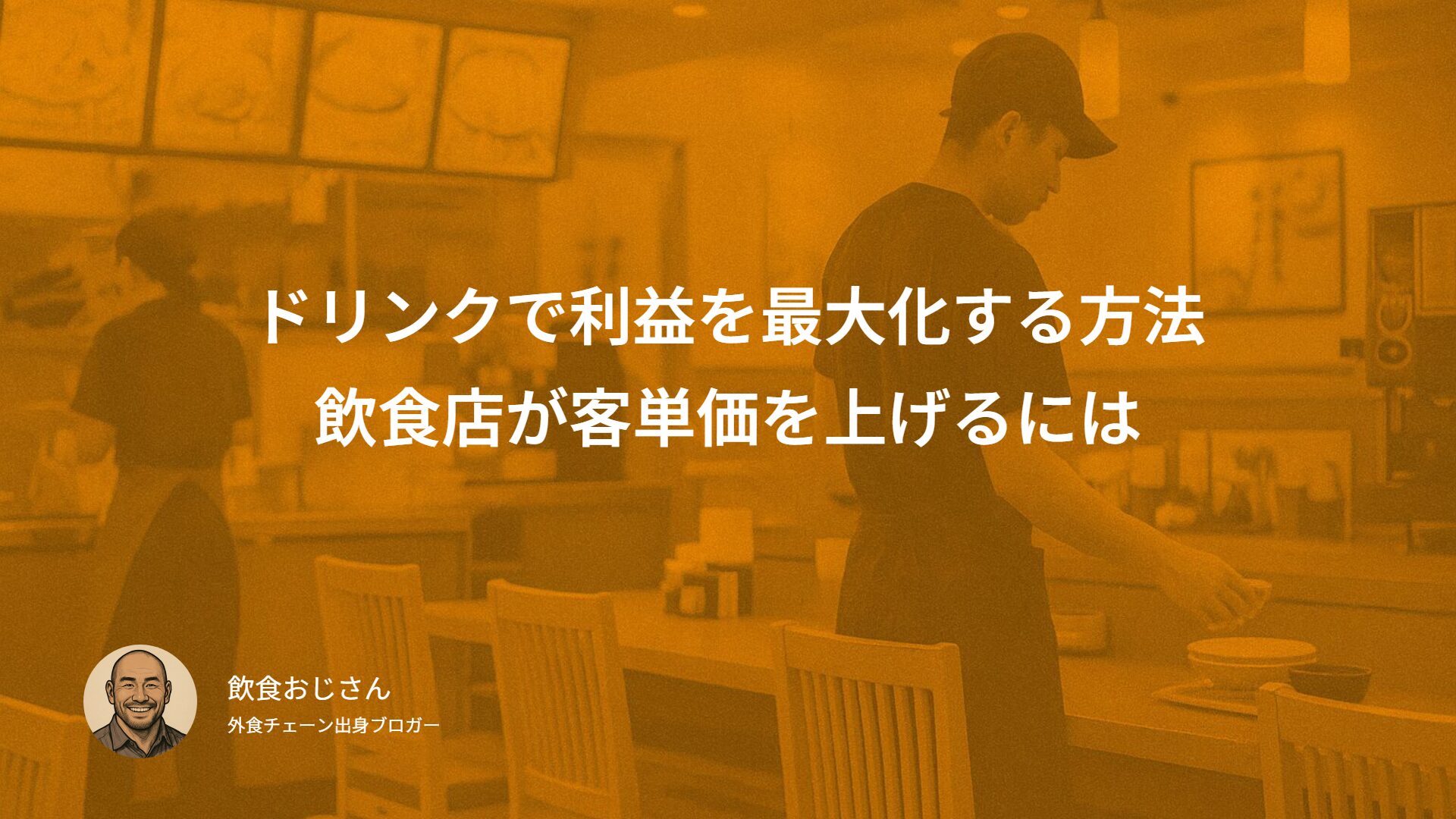
「ドリンクの利益が思うように残らない」
──そんな悩みを感じていませんか?
原価を下げても売上が伸びず、気づけば「人気メニューほど儲からない」という状況に陥るお店は少なくありません。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗経営に取り組んできました。

本記事では、ドリンクを“利益を生む設計商品”に変える方法を、メニュー構成・見せ方・提案トークの3つの視点から解説します。
✅ この記事を読むメリット
- 原価率より“粗利を作る考え方”がわかる
- 注文が増えるメニューの見せ方を学べる
- 自然に2杯目をすすめる仕組みを作れる
ドリンクを見直すだけで、売上もスタッフの提案力も変わります。読み終える頃には、「ドリンクがこんなに奥深い商材だったのか」と感じるはずです。
ドリンクの利益を決めるのは「設計」|安売りではなく感じる価値

ドリンクは、客単価と利益を同時に押し上げる“最も再現性の高い商品”です。
しかし多くの店では、仕入れやメニュー構成がなんとなく続いていて、「人気はあるのに儲からない」という状態に陥りがちです。
利益は努力ではなく設計で決まります。原価を下げるより、「どのドリンクを、どの順番で、どう売るか」を整理する方が効果的です。
飲食店で提供されるフードの平均原価率は約30%、ドリンクの平均原価率は約25%といわれています。canaeru(カナエル)
粗利をつくる考え方を持つ
原価率にこだわると判断を誤ります。重要なのは「粗利額×出数」です。
たとえば、原価率40%のハイボールが月500杯出れば、原価25%のカクテル300杯より利益が残ることもあります。
- 原価率より粗利額で見る
- 売れる数を想定して商品を組む
- 人気=利益ではないことを知る
利益を“結果”でなく“設計”で作る意識が、安定経営の出発点です。
主力3品で8割の売上を取る構成にする
メニュー全体を見直すと、売上の大半は限られた商品に集中しています。
この“主力3品”をあらかじめ決めて、そこに導線を集約させるだけで無駄な仕入れも減ります。
この3階層で構成すれば、「どれを売れば利益が出るか」が誰でも判断できます。
ドリンク構成と役割の整理表
| 区分 | 目的・役割 | 具体例 | 店長が意識すべきポイント |
|---|---|---|---|
| 名物ドリンク | 話題を作り、来店動機を生む | クラフトレモンサワー/店仕込み果実酒 | 注目を集めるためにPOP・SNSなどで露出を増やす |
| 主力ドリンク | 利益を支える中心商品 | ハイボール/生ビール/サワー類 | 出数を安定させる。スタッフ全員がすぐ出せる状態を保つ |
| サブドリンク | 常連・特定層の満足を補う | 焼酎ロック/ノンアルカクテル | 品ぞろえを維持しつつ、在庫過多に注意する |
最初の1杯と2杯目を設計する
多くの店で抜け落ちているのが“2杯目の設計”です。
最初の1杯は勢いで頼まれても、2杯目の提案がなければ客単価は頭打ちになります。
たとえば、
1杯目:定番ビール(安心)
2杯目:軽いサワーやハイボール(変化)
この流れをメニューと声かけで整えておくと、自然に「もう一杯」が生まれます。
利益は“頑張り”じゃなく“設計”で決まります。最初の1杯と2杯目を整えるだけで、お店の数字は変わります。

メニューの“使い方”で注文率は変わる|店長ができる演出の工夫

外食チェーンでは、ドリンクメニューは本部が決めるもの。しかし、「どう見せるか」「どう伝えるか」は店長の腕次第です。
同じメニューでも、置き方・声かけ・タイミングを変えるだけで出数は大きく変わります。メニューを変えられなくても、「お客さまの目と心にどう映るか」を動かすことはできます。
ドリンクメニュー全体の原価率の目安は、一般的に20%~30%と言われています(フードビジネス地図帳)
置き方とタイミングで印象を変える
メニューを開いてもらえるタイミングを作るだけで、提案の成功率は上がります。
📌 たとえば
- ドリンクメニューを料理提供前に一度見せる
- 卓上に立てて“視線の高さ”に置く
- 空いたグラスを下げるときに「こちらも人気ですよ」と一言添える
この3つを意識するだけで、自然にお客さまの視線がドリンクへ向かいます。
店長がやるべきは「見せる機会を増やすこと」。メニューそのものより、見せる瞬間を設計することがポイントです。
言葉の温度で“飲みたい”を引き出す
メニューの内容を変えられなくても、伝え方で印象は変わります。
「おすすめです」よりも、「今日はよく出てますよ」「炭酸強めでキレますよ」のように、リアルな一言を添えると説得力が一気に上がります。
💡 店長・スタッフに伝えたい実践トーク
言葉に“温度”を乗せることで、お客さまはメニューを「眺める」から「選ぶ」に変わります。
メニューは“道具”、提案は“演出”。変えられないからこそ、見せ方と声のひと工夫で売上が変わります。

👉 料理提案でもう一歩売上を伸ばしたい方は、次の記事も参考にしてください。
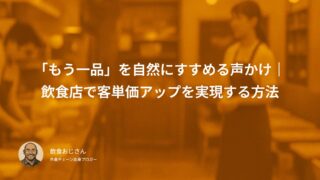
提案と提供スピードで「もう一杯」を生む

ドリンクの利益を伸ばす最大のポイントは、最初の一杯の後にあります。「もう一杯どうですか?」と声をかけるかどうかで、客単価は驚くほど変わります。
ただし、押し売りになれば逆効果。重要なのは、自然に“次の一杯”へつなぐ流れをチームで作ることです。
✅ 提案は“定型文化”で迷いをなくす
多くのスタッフは、タイミングや言葉に迷って提案できません。そのため、店長が「定型トーク」を共有しておくと行動が統一されます。
「グラス半分くらいになったら次どうされますか?」
「同じものでいきます?それとも少し軽めにしますか?」
「このあと食事が進む方に変えてみますか?」
このように選択肢を添えた提案は押しつけにならず、会話が自然に流れます。「声かけ」ではなく「確認の一言」に変えるのがコツです。
また、スタッフ全員が使えるテンプレートを持っておくと、誰が接客しても提案の質が一定になり、属人化しない売上が作れます。
✅ 提供スピードと温度が“次の一杯”を決める
2杯目が出るかどうかは、味よりも体験のテンポに左右されます。グラスが空いた後に待たされると、注文意欲は一気に下がる。
だからこそ、スピードと鮮度の仕組み化が必要です。
✔ 店長が整えるべきポイント
ドリンクが「すぐ来て冷たい」だけで、満足度は大きく上がります。この満足が“もう一杯”を呼び、自然に客単価を押し上げていきます。
提供スピードを高めるチェックリスト
| チェック項目 | 内容 | 店長の確認ポイント |
|---|---|---|
| 注文から提供までの時間 | 1分以内を目標 | 混雑時も同水準で出せるか確認 |
| 材料の配置 | 主力ドリンクの材料をサーバー周辺に集約 | 動線が短く、誰でも作業できる配置になっているか |
| グラス管理 | 冷却済み・清潔な状態で常備 | 補充タイミングを明確にしておく |
| 炭酸・氷の管理 | 炭酸抜けや氷不足の防止 | 仕込み時点で残量チェックを習慣化する |
“もう一杯”は口のうまさじゃなく、段取りのうまさ。声をかけやすくして、すぐ出せる体制を作れば、お客さまはまた頼みます。

まとめ|ドリンクで利益を最大化する考え方と店長が取るべき行動

ドリンクで客単価を上げるための3つの実践ポイント
- 利益は設計で決まる:原価より「粗利×出数」で考える
- 見せ方と声かけで注文が変わる:メニューを“使う”意識を持つ
- スピードと温度がリピートを生む:すぐ来て冷たい一杯が次の注文につながる
小さな改善を積み重ねるだけで、ドリンクはお店の利益を支える柱になります。
「利益は“設計”で決まります。メニューを動かせなくても、見せ方とスピードはあなた次第。今日の一杯が、明日の数字を変えます。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 スタッフの行動を安定させて、チーム全体の信頼感を高めたい方は、次の記事も参考にしてください。