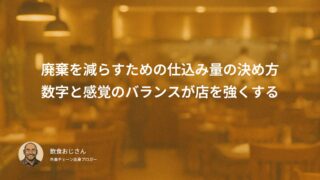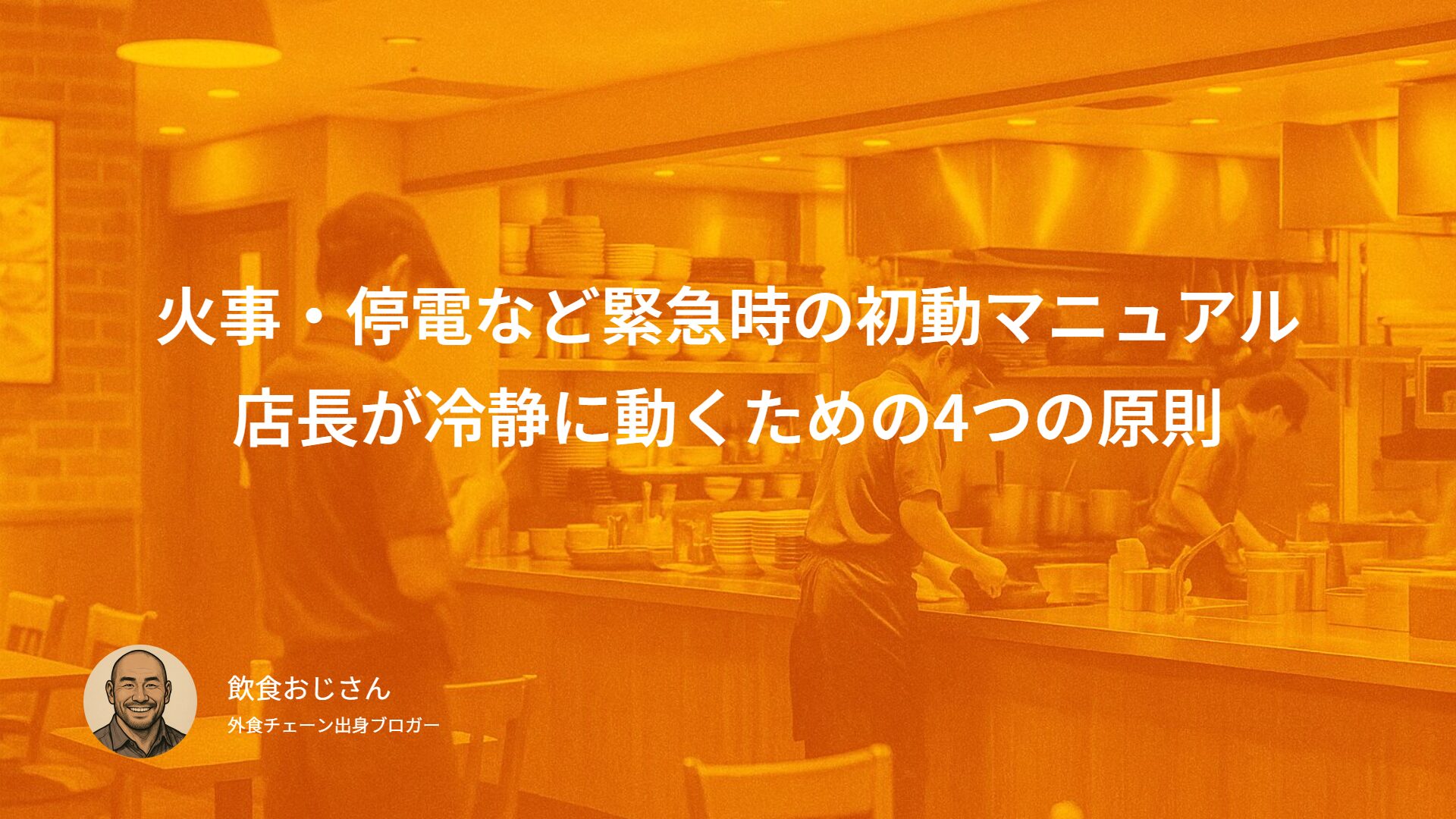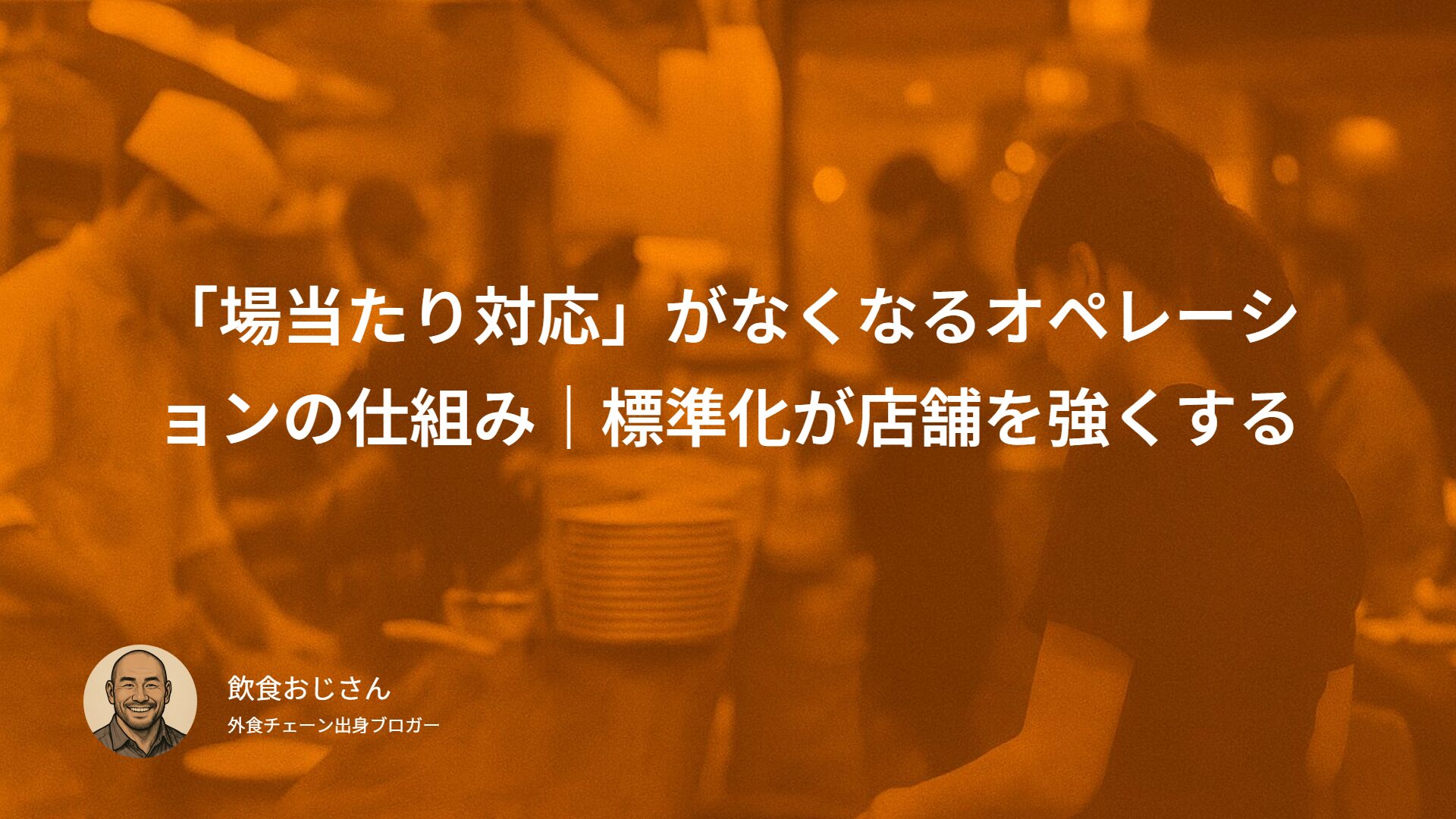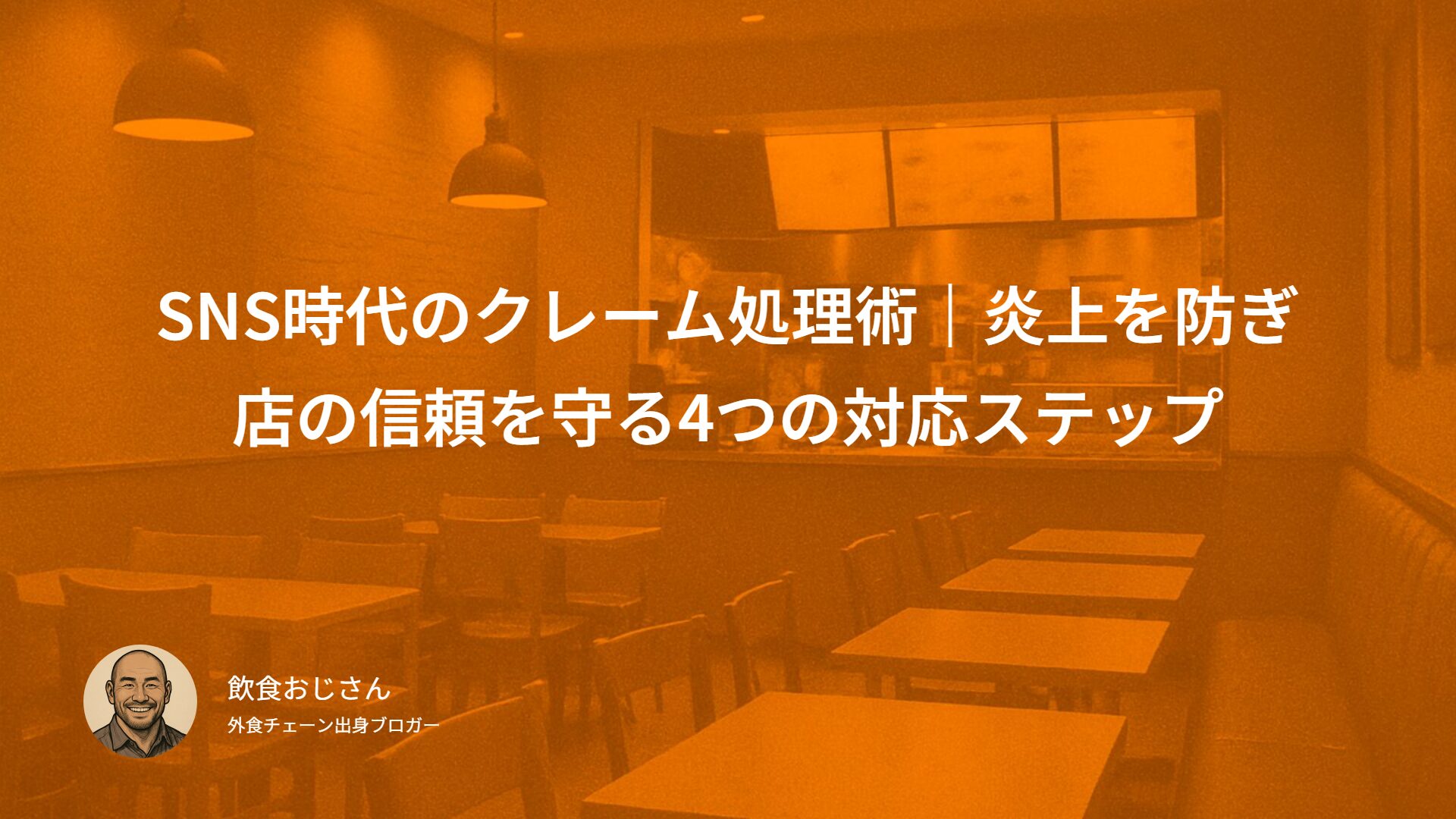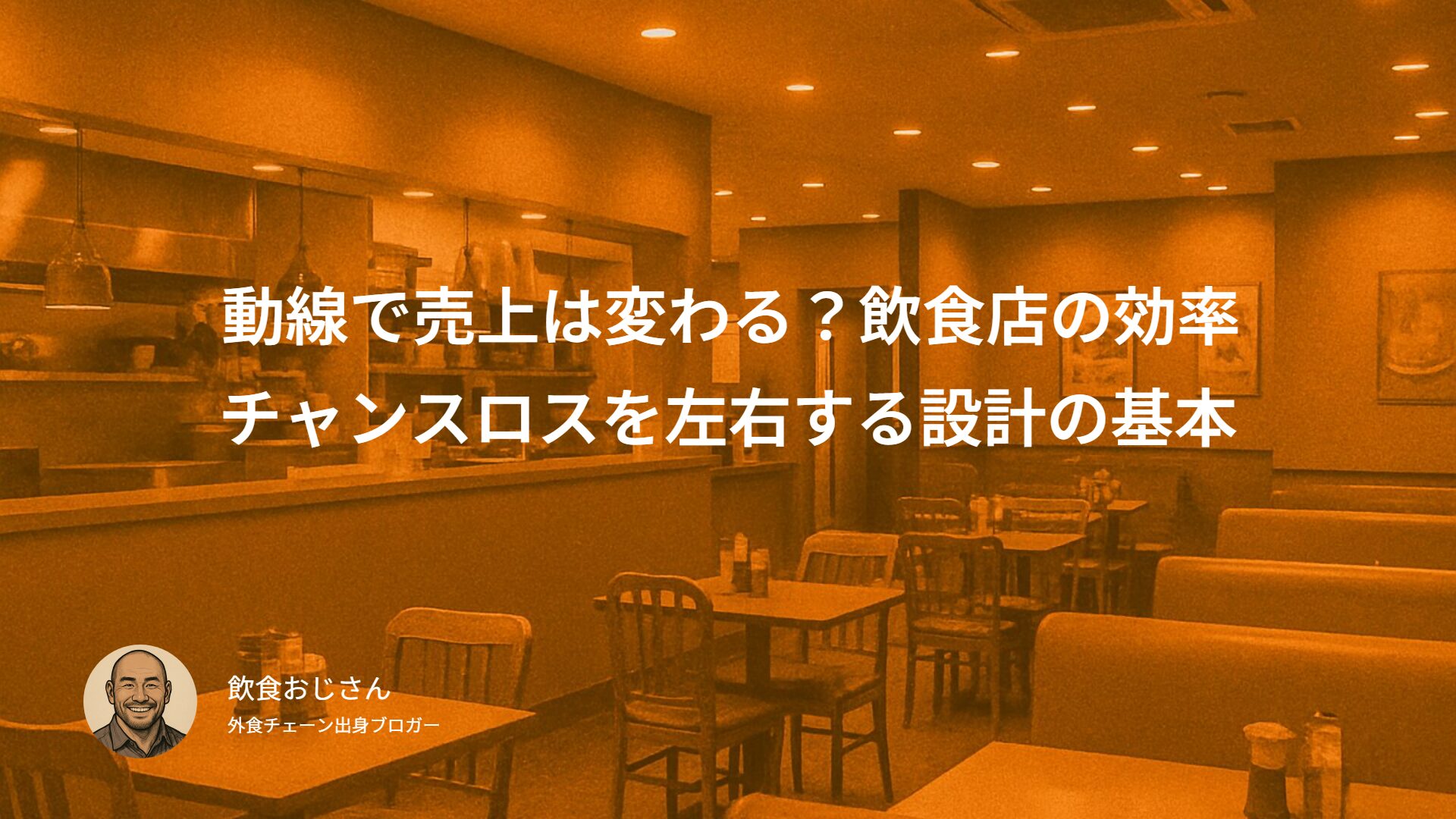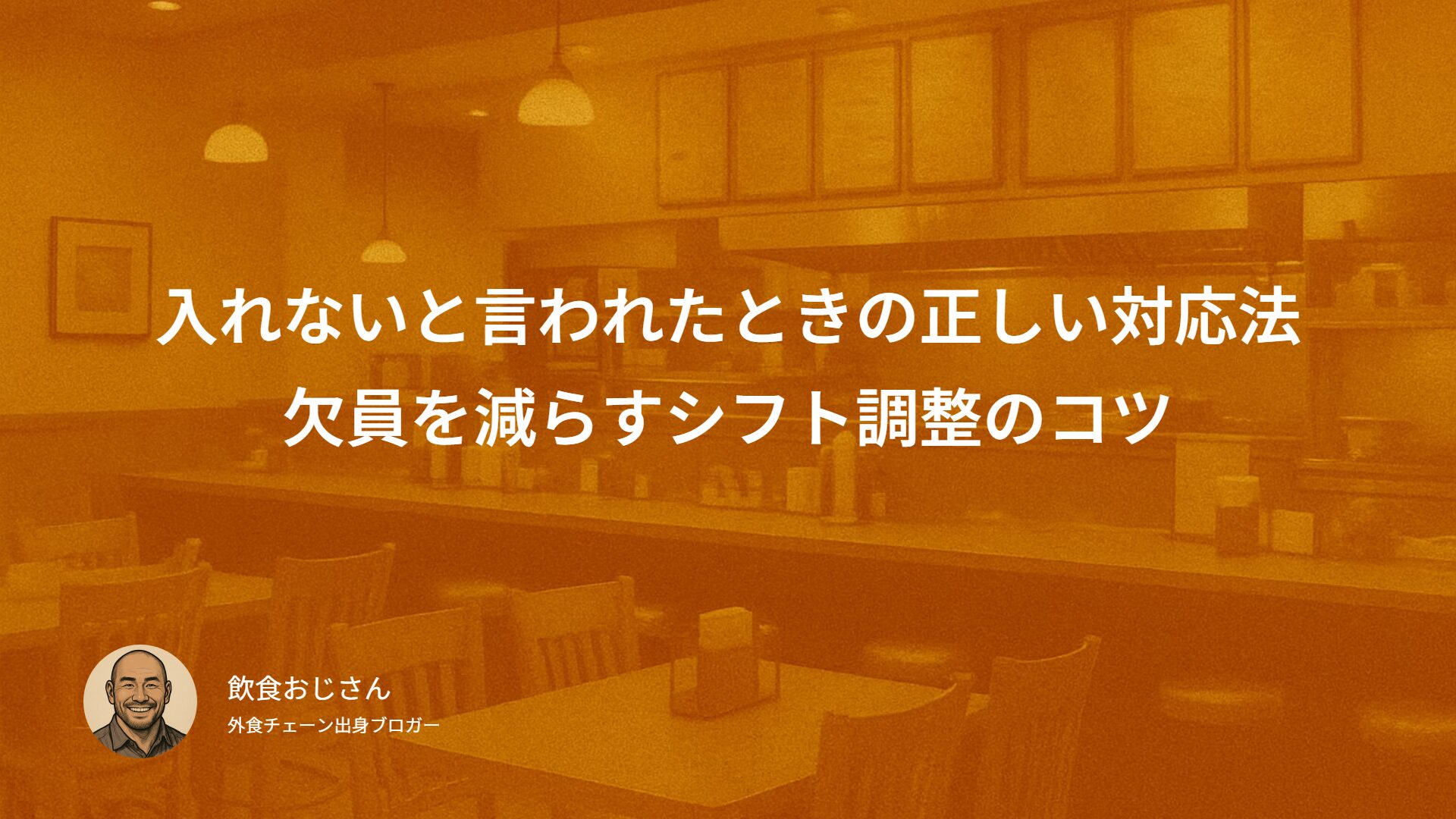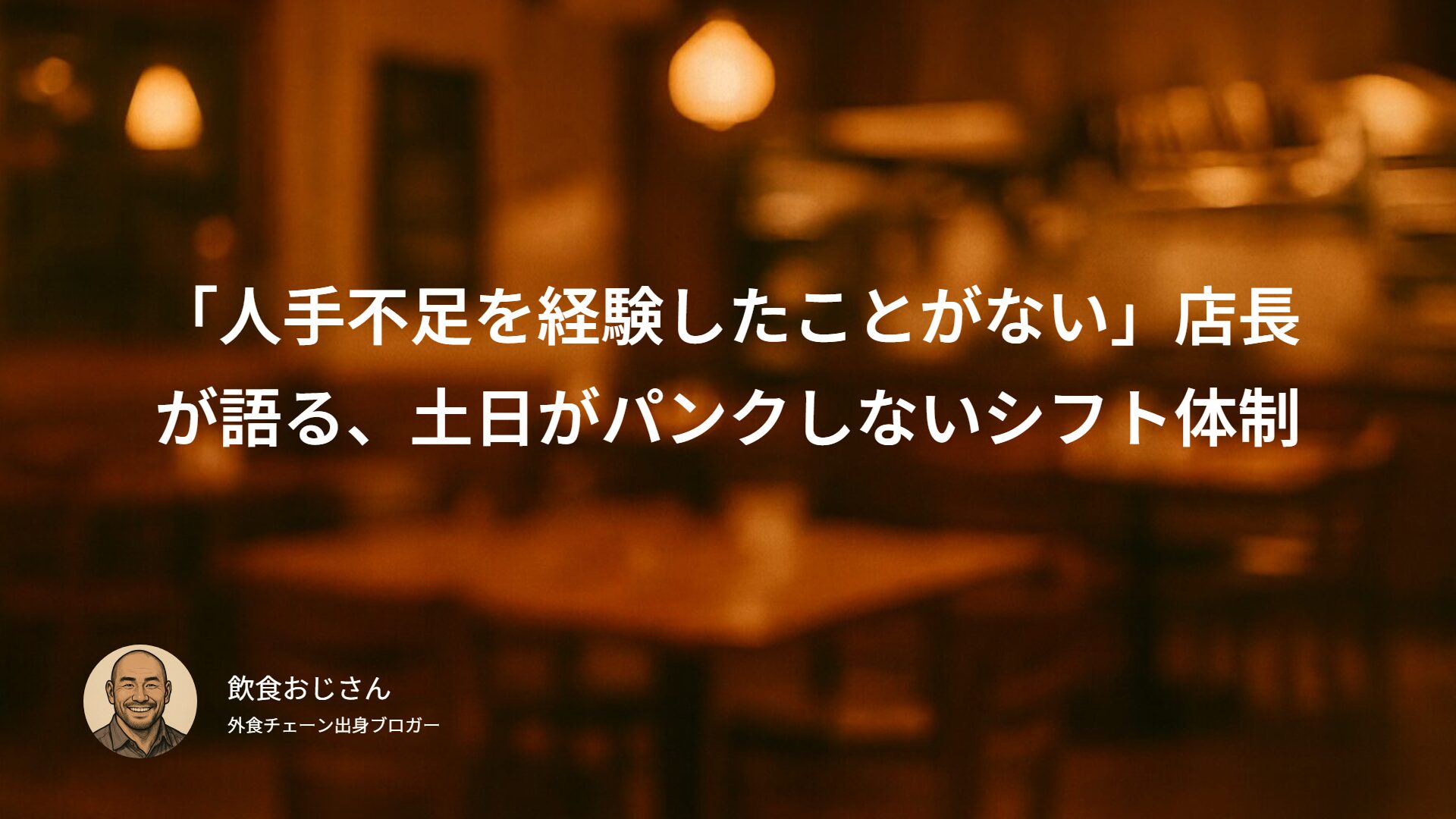平日の売上が落ちるとき、仕込みは「やらないこと」から決めるべき理由
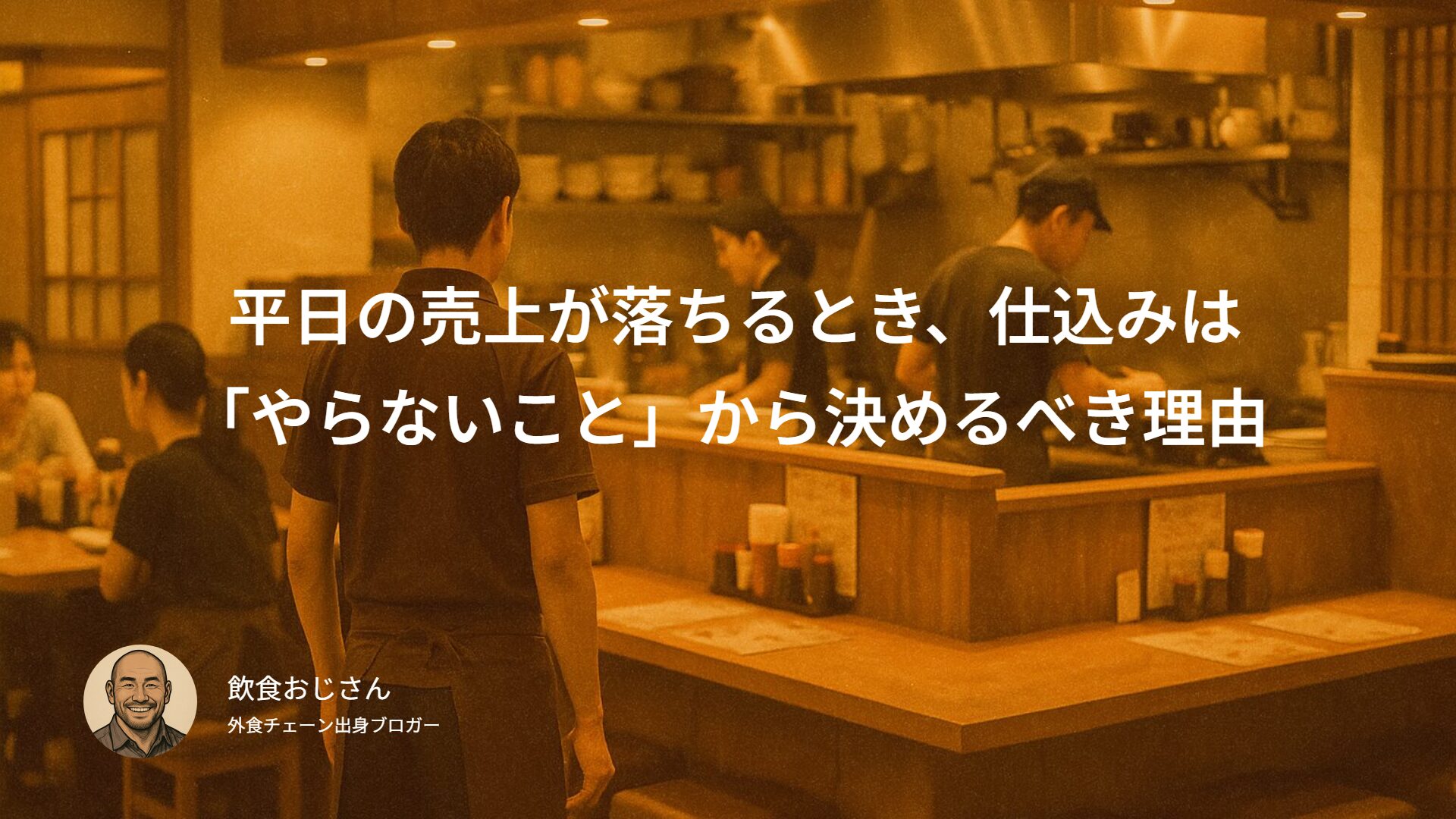
「平日は売上が読めないから、念のため多めに仕込んでおこう」
そんな判断が、かえってロスやムダを生んでしまうことも少なくありません。
私自身、店長時代は「余るぐらいでちょうどいい」と思っていた時期がありました。でもそれは、“成果に直結しない仕込み”に時間とコストを使っていたに過ぎなかったのです。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗運営に取り組んできました。

本記事では、売上が落ちる平日こそ見直すべき“仕込みの判断基準”について解説します。「何をどれだけ仕込むか」ではなく、まず「何を仕込まないか」から考えるべき理由がわかります。
✅ この記事を読むメリット
- 平日の仕込みを“最小の労力”で最大化する視点が得られる
- 売上が落ちる日でも、ムダなく回せる判断軸が手に入る
- 感覚ではなく“基準”で判断できるようになる
「仕込む」ことが目的になっていないか?そんな問いかけから始めるこの記事が、あなたの判断を研ぎ澄ませるきっかけになれば嬉しいです。
なぜ平日は“いつも通り”の仕込みをしてしまうのか?

売上が読めない平日こそ、本来は仕込みを柔軟に調整すべきです。
それでも多くの店で「とりあえずいつも通り」で動いてしまうのはなぜか?その背景には、“思考停止”と“過剰な安心”という2つの落とし穴があります。
思考停止型のルーチン|「いつものやり方」が判断を奪う
一度ルール化した仕込み量は、安心感がある一方で、思考を止める麻薬にもなります。
「売上は落ちてるけど、まあいつも通りで…」
「昨日もこの量でいけたから、今日も同じで大丈夫だろう」
――このような判断は、“過去の成功体験”を根拠にした惰性です。
仕込みは「作業」ではなく「未来への投資」です。
売上が下がる日ほど、ルーチンを見直す判断が必要なのに、お店は「いつもの手順」で行うことに慣れすぎてしまっているのです。
過剰な「安心」への投資|“足りないと困る”がムダを生む
「少なくて足りなかったらどうしよう」
仕込みすぎた分は売上につながらず、廃棄になるか、翌日に持ち越して使うしかなくなります。
でも翌日がさらに閑散日なら、そのままロスに直結する可能性も高くなります。
“足りない不安”を消すために、“ムダな安心”にコストをかけていないか?その投資は、成果に直結していない可能性があります。
安心のためにやってる仕込みが、結果的に“店を苦しくしてる”こともあります。

仕込みが「多すぎる」「少なすぎる」ことで起こる3つの問題

仕込みは「少ないと足りない」「多いとムダになる」――その両極端が現場に与える影響は想像以上です。
とくに売上が不安定な平日ほど、この判断ミスはロスやオペレーションの乱れ、スタッフの混乱に直結します。
ここでは、仕込み量の判断ミスによって起こる代表的な3つの問題を解説します。
売上に合わない仕込みは、廃棄を生む
平日は売上が読みにくいため、気持ちが先行して仕込みすぎてしまうことがあります。しかしその仕込みが売上に見合わなければ、食材は使い切れずに持ち越すか、最悪廃棄になります。
特に日持ちしない食材や、当日仕込み当日提供が前提のメニューは再利用が難しく、ロスになりやすい。
「とりあえず仕込んでおく」が、利益を削る結果になりかねません。
我が国の事業系食品ロスの発生量は、231万トンと推計されている。環境省「事業者向け情報 | 食品ロスポータルサイト
仕込みが足りないと、機会損失につながる
逆に、「今日は暇だろう」と読んで仕込みを絞りすぎた結果、思いがけない団体や急な注文に対応できないケースもあります。
準備が間に合わず、提供時間が大幅に遅れたり、一部メニューが売り切れになることで注文数そのものが減る。
これは「売れるはずだった売上」を取りこぼす、機会損失です。
仕込み判断ミスとその影響一覧
| 判断ミス | 起こりやすい問題 |
|---|---|
| 多すぎた場合 | 食材ロス・廃棄・冷蔵スペースの圧迫 |
| 少なすぎた場合 | 品切れ・提供遅れ・機会損失 |
判断のブレが、スタッフの混乱を招く
仕込み量の判断が毎回ブレていると、スタッフ側も対応に苦労します。
――そんな状態では、指示待ち・確認の手間・ストレスが生まれやすくなります。
ベテランならまだしも、新人スタッフにとっては「なぜこれだけ仕込むのか」が見えないと、オペレーションに対する理解も深まりません。
仕込みは感覚ではなく判断です。数字と経験の両方から考えることが大切です。

👉 土日の人手不足を根本的に見直したい方は、次の記事も参考にしてください。
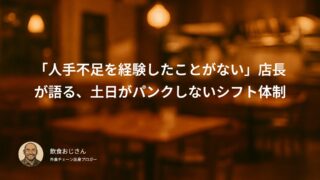
仕込みを減らす判断をどう設計するか

仕込みは「とりあえずやっておくもの」ではなく、本来は売上に対して適正な量を決める業務判断です。
売上が不安定な平日ほど、感覚に頼らず、根拠のある減らし方を設計しておく必要があります。
ここでは、仕込みを適正化するための実践的な3つの工夫を紹介します。
✅ 過去データから「最低ライン」を割り出す
まず必要なのは、「最低限どれだけ仕込めば営業に支障が出ないか」を把握しておくことです。
前月・前年の平日実績、天候、曜日別の売上傾向などから、最低ラインの仕込み量を数値で把握しておきます。
「この数字を下回ることはまずない」という基準があるだけで、不安による仕込みすぎを防げます。
逆に、このラインを知らずに仕込むと、全てが“感覚まかせ”になります。
✅ 「売上見込み別」の分岐ルールを決める
次に、当日の売上見込みに応じて仕込み量を変えるルールを事前に作っておきます。
- 売上予測8万円 → Aパターン(通常)
- 売上予測5万円 → Bパターン(抑えめ)
- 売上予測3万円 → Cパターン(最小)
このように3段階程度に分けておくと、判断に迷いがなくなり、誰でも共有できる基準になります。
売上予測の根拠は、天気/曜日/イベント/最近の傾向などをざっくりで十分です。
✅ 店長不在でも迷わない「簡易仕込み表」を用意する
判断を店長だけに任せず、誰でも迷わず対応できる仕組みがあると、平日の仕込みは安定します。
とはいえ、すべてのメニューを細かく管理する必要はありません。対象は、ロスが出やすい商品・仕込みに時間がかかる商品に絞り、
といった内容を、紙かホワイトボードにまとめておくだけで十分です。複雑なマニュアルではなく、誰でも“その場で判断できる道具”を残すことが大事です。
仕込みをどう減らすかは、店長の仕事です。再現できる形にして、毎日の迷いをなくしましょう。

まとめ|平日の仕込みに迷わない判断基準を持つ
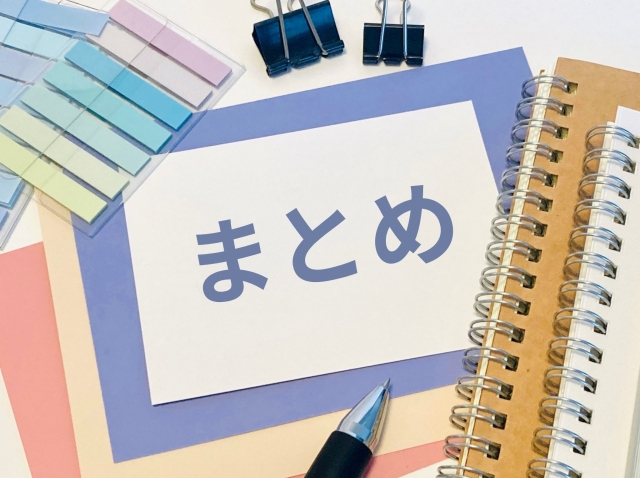
平日の売上減でもムダなく仕込みを整える3つの視点
- 仕込みは「感覚」ではなく「判断」で決める
→ 売上が落ちる日ほど、習慣に頼らず根拠をもつことが重要です。 - 最低限の仕込み量と売上予測で分岐ルールを作る
→ 3段階の仕込みパターンを用意すれば、無駄と不足の両方を防げます。 - 誰がいても判断できる仕組みを紙でも残す
→ 属人化を防ぎ、店全体の仕込み判断を安定させる鍵になります。
平日は売上が読みにくいからこそ、感覚ではなく基準で動くことが重要です。
仕込みすぎを防ぐだけでなく、スタッフ全員が同じ基準で動ける環境が整えば、ムダも迷いも減っていきます。
「仕込みの悩みは、勘をやめて仕組みに変えるだけで、ずっと楽になります。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 仕込み量の判断に自信を持ちたい方は、次の記事も参考にしてください。