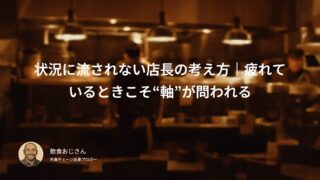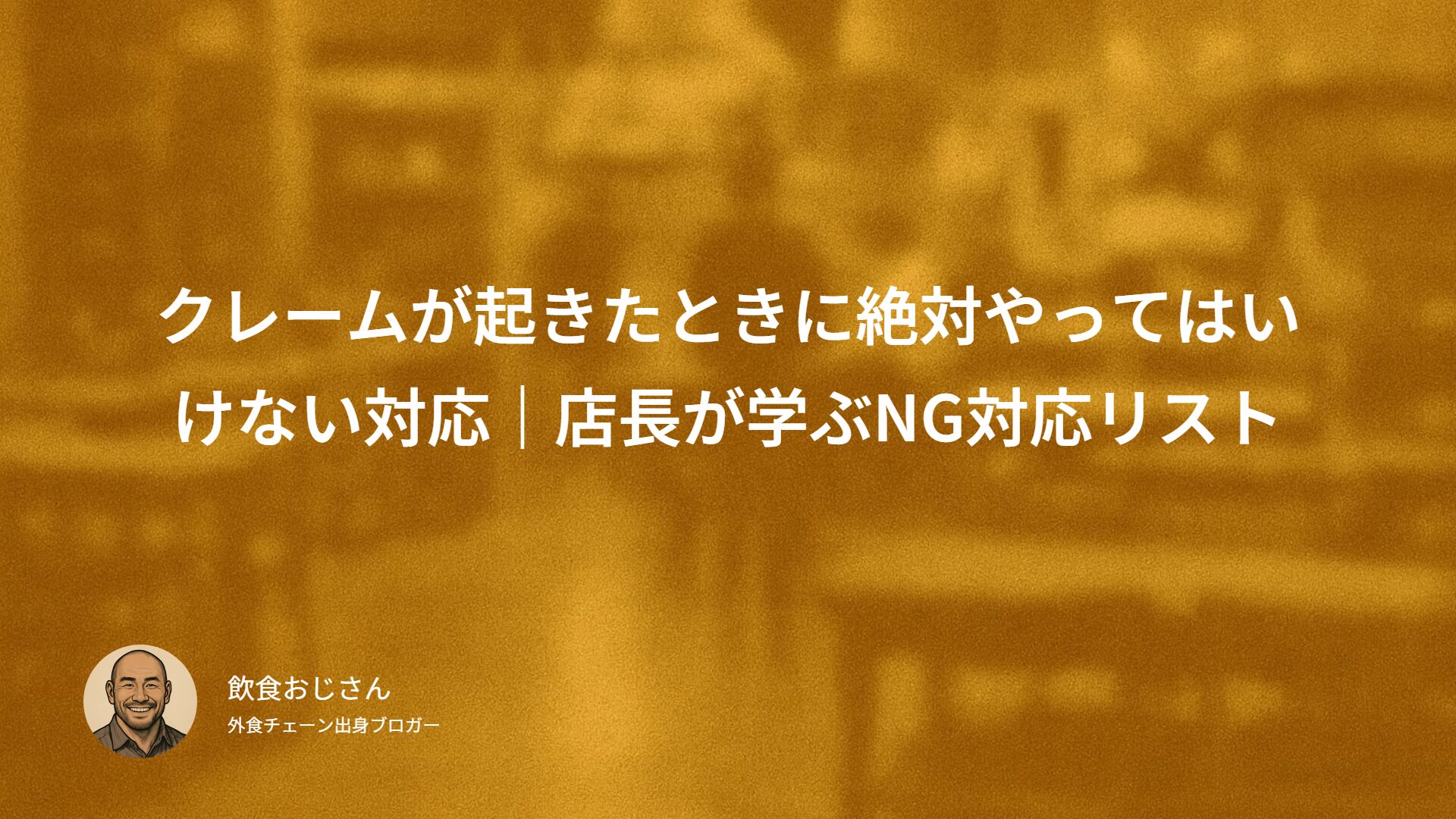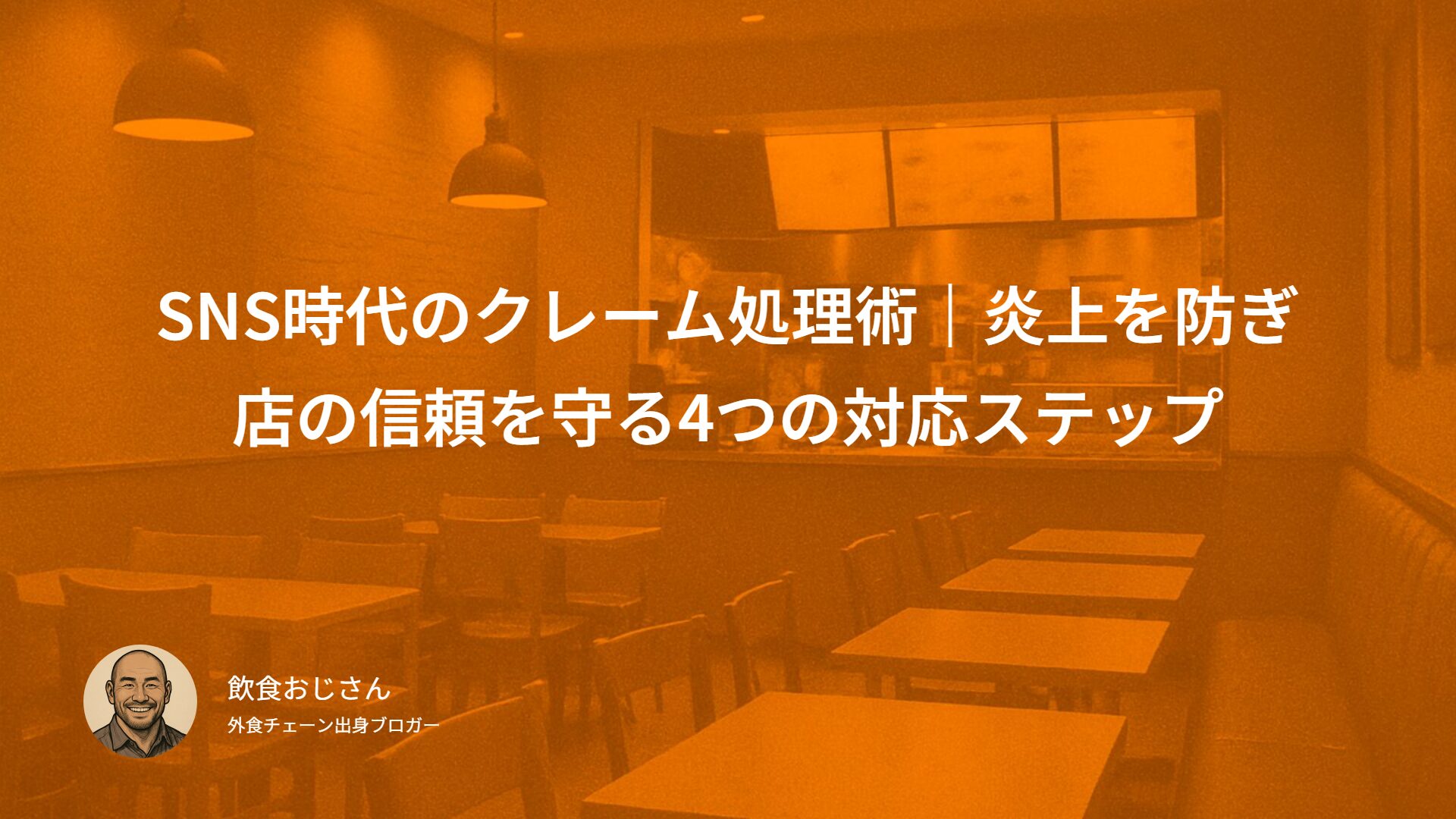火事・停電など緊急時の初動マニュアル|店長が冷静に動くための4つの原則
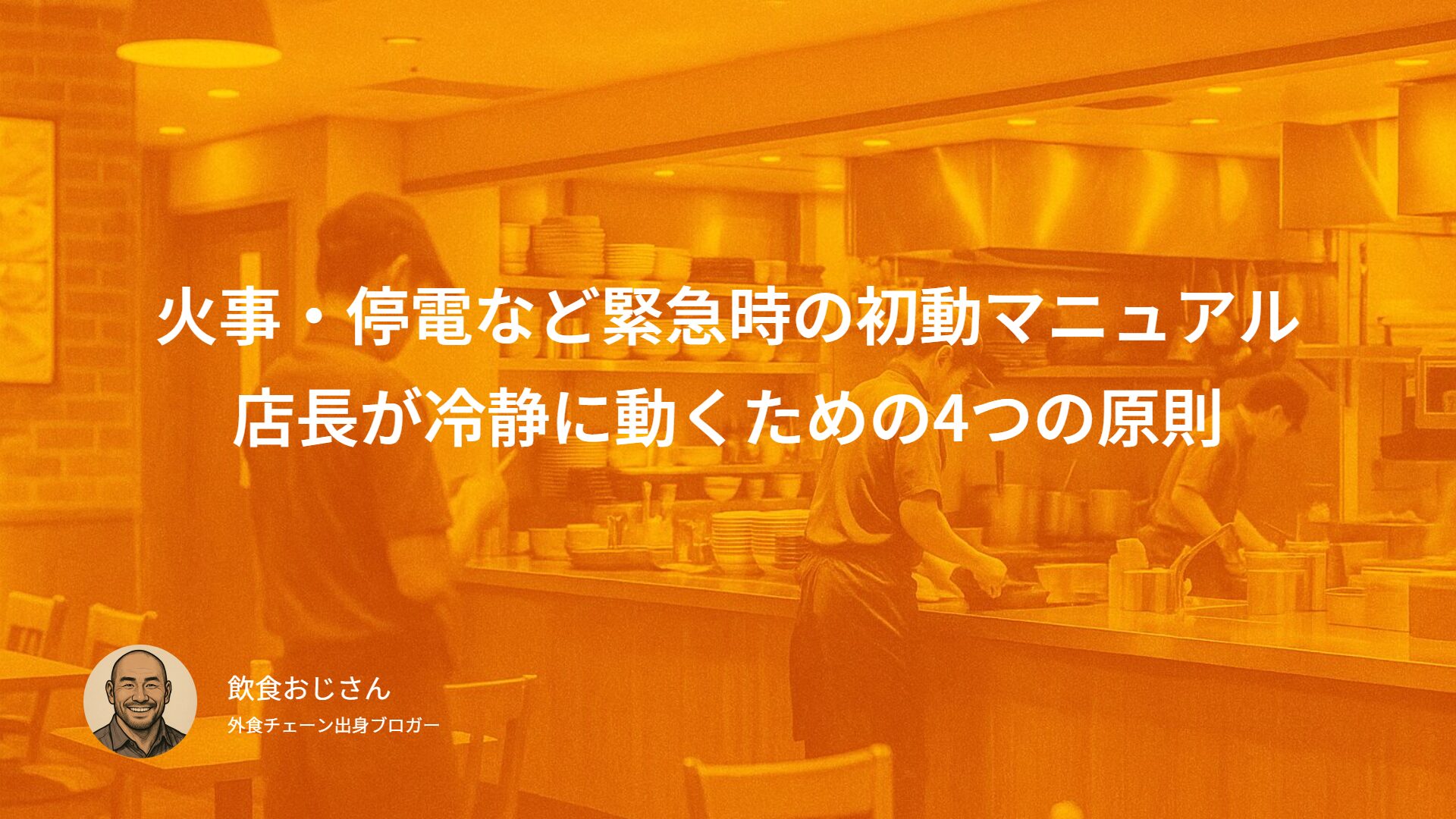
火事・停電・ガス漏れなど、いつ起きるかわからない“非常事態”。
「もし今、店で火が出たら」
「お客様が倒れたら」
──そんな想定外に、あなたはすぐ動けますか?
多くの店長さんが「慌ててしまった」「何を優先すべきか迷った」と感じています。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗運営に携わってきました。

本記事では、緊急時に店長が最初に取るべき行動を、わかりやすく4つの原則にまとめました。
✅ この記事を読むメリット
- 非常時の行動の“正しい順番”がわかる
- 火事・停電・ガス漏れなどの対応を体系的に整理できる
- スタッフと共有できる実践的なマニュアルが手に入る
いざという時に慌てないために。「想定外を想定内に変える」判断基準を、一緒に確認していきましょう。
緊急時に迷わないための「初動の優先順位」

トラブルのとき、最初の1分で行動を誤ると、被害は一気に広がります。火事でも停電でも、慌てて判断を誤ると取り返しがつかなくなることがあります。
多くの店で“初動の迷い”が二次被害を招いてきました。
最初に守るのは「人命」
緊急時に絶対に迷ってはいけないのが、人命の判断です。
「自分の安全」「スタッフ」「お客様」の順に冷静に行動します。
人を守るためには、“助けるより逃す”という意識を持つことが大切です。命の安全が確保されなければ、店も営業も成り立ちません。
「安全確保」と「被害の拡大防止」
人命を守ったら、次は二次被害を防ぎます。
ブレーカーを落とす
ガスの元栓を閉める
周囲の危険物を遠ざける
この段階で無理な消火や点検を行うと、再び火が上がるなど逆効果になることもあります。安全が確保されていないうちは、絶対に戻らない判断も重要です。
正確に「報告・連絡」する
安全を確保したら、次は報告です。
消防や警察、オーナー、上司に「何が起きて」「今どうなっているか」を簡潔に伝えます。
- 誰に(上司・オーナー・関係機関)
- 何を(発生状況・被害・現在の対応)
- どう伝えるか(電話・写真・動画)
ここで焦って報告を省略すると、支援が遅れ、被害が拡大します。報告の目的は「助けを呼ぶこと」だけでなく、「次の判断を委ねる」ことでもあります。
緊急時の初動対応フロー(行動の優先順位)
| 優先順位 | 行動内容 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| ① | 人命の確保 | お客様・スタッフを守る | 避難誘導・救急要請 |
| ② | 安全の確保 | 二次被害を防ぐ | ブレーカー遮断・ガス元栓停止 |
| ③ | 迅速な報告 | 被害拡大を防止 | 上司・オーナー・消防へ連絡 |
【管理視点】
「優先順位を決めておくこと」は、緊急時のリーダーシップそのものです。
決断を迷う時間こそ、最も危険です。
行動の順番を整理しておくことが、冷静さを保つ最大の防御になります。
焦らないことです。まず“人”を守りましょう。それさえできれば、あとのことはどうにでもなります。

火事・停電・ガス漏れに共通する「正しい初動」
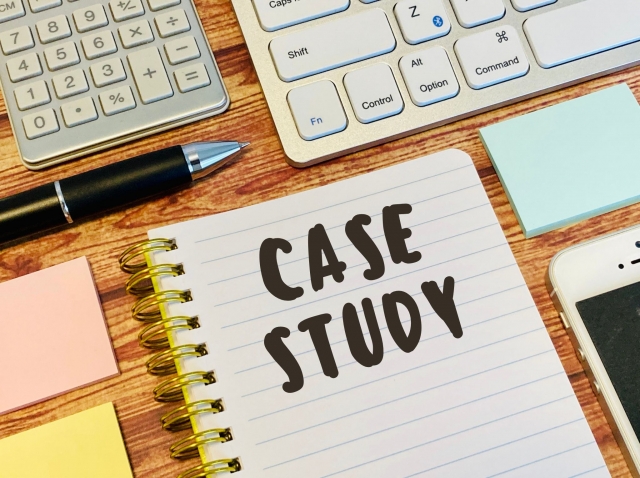
トラブルの種類は違っても、店長の行動原則は共通しています。
ポイントは「慌てず、順番通りに動くこと」です。火事でも停電でもガス漏れでも、人を守る → 被害を止める → 伝える、この流れを崩さなければ致命的な被害は防げます。
火事が起きたときの行動手順
火事の初動対応で最も大切なのは、消火より避難です。
火を止めるより、まず人を逃がすことを優先しましょう。
- 「火事です!」と大声で知らせる
- お客様を店外へ避難誘導する
- 炎が小さい場合のみ初期消火(無理はしない)
- ブレーカーとガス元栓を止める
- 消防とオーナー・上司に連絡する
この順番を守れば、混乱を最小限に抑えられます。火の勢いに気を取られて行動すると、二次被害を招くおそれがあります。
自分が動くより「周囲に指示を出す」ことを意識しましょう。
原則として小火(ぼや)で済みそうな場合でも、火災を発見した場合には直ちに消防に通報しましょう(中小企業庁)
停電・ガス漏れ時の安全確保
停電やガス漏れは、一見落ち着いて見えても危険をはらんでいます。慌ててスイッチや機器を操作するのは厳禁です。
- 暗所での転倒や事故を防ぐため、安全確保を最優先
- 分電盤・ブレーカーを確認し、異常があれば電力会社に連絡
- 周囲の店舗にも状況を確認する(広域停電の可能性あり)
- 火気厳禁(換気扇・電気スイッチも使用しない)
- 元栓を閉め、窓や扉を開放して換気
- ガス会社へ連絡し、点検が終わるまで営業停止
停電は「感電」、ガス漏れは「爆発・中毒」の危険があります。
「確認より先に安全確保」、これを徹底してください。
【管理視点】
緊急時の判断ミスは「行動の焦り」から生まれます。
順番を決めておくことで、余計な思考を減らし、判断を自動化できます。
マニュアルとは、考えずに正しく動けるための準備です。
慌てないことです。順番を守れば、どんなトラブルも防げます。
まず安全を確保して、次に冷静に伝えましょう。

👉 クレーム対応で慌てずに行動したい方は、次の記事も参考にしてください。
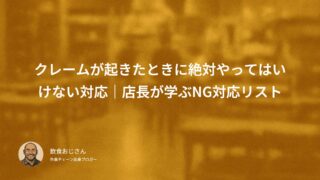
報告・記録・共有で「再発を防ぐ」

トラブルを“その場で終わらせる”だけでは、同じことがまた起きます。大切なのは、起きた事実を残し、共有し、次に活かすことです。
報告・記録・共有の3つがそろって、初めて「再発防止」が成り立ちます。
✅ 正確な「報告」で混乱を防ぐ
緊急時の対応が落ち着いたら、まず上司・オーナー・本部に報告します。報告の目的は「叱られないため」ではなく、「店を守るため」です。
いつ・どこで・何が起きたか(日時・場所・概要)
どのように対応したか(手順・所要時間・結果)
被害や影響(人的・物的・営業面)
今後の対応(再開時期・安全確認)
報告はできるだけその日のうちに行うのが理想です。時間が経つほど、状況の記憶は曖昧になります。
✅「記録」を残して判断力を高める
報告が済んだら、記録を残しましょう。これは自分のための“復習”です。
- その日の状況メモ(どんな流れだったか)
- 写真・動画(現場・対応の様子)
- スタッフの反応・意見
- 改善すべき点・気づき
記録を残すことで、「次に同じ状況が起きたとき、迷わず動ける」ようになります。
つまり、判断の再現性が高まるということです。
✅「共有」でチームの意識を高める
報告と記録を終えたら、最後はチーム全体で共有します。
ミーティングや朝礼などで「実際に何があったか」「どう対応したか」を伝えましょう。
誰かを責めるのではなく、「次に同じことが起きたら全員で防ぐ」ための意識づくりが目的です。
スタッフが「自分ごと」として考えられるようになると、初動も速くなります。これが、強い店づくりの第一歩です。
【管理視点】
報告・記録・共有の3つは、すべて「再発を防ぐための仕組み」です。
失敗を隠すより、共有する文化をつくるほうが、はるかに安全で成長のある店になります。
書き残すことです。そして、みんなで話し合いましょう。それが、次のトラブルを防ぐ一番の方法です。

まとめ|緊急時対応は「順番と準備」で決まる
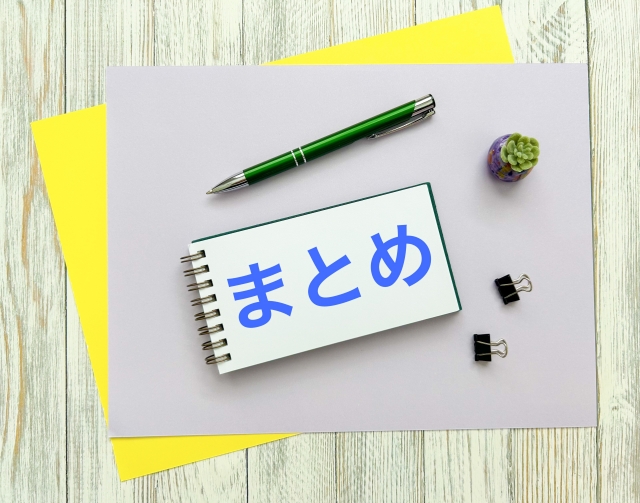
店長が非常時に守るべき3つの原則
- 人命を最優先に行動する(お客様とスタッフの安全を最優先)
- 被害を最小限に抑える(ブレーカー・ガス元栓の遮断を徹底)
- 冷静に報告・共有する(上司・関係機関・スタッフ間で迅速に伝達)
どんなトラブルでも、この3つの流れを守ることで致命的な被害を防げます。そして、普段から「訓練・確認・共有」を習慣化しておくことが、慌てない店づくりの基本です。
「焦らないことです。順番を決めておけば、誰でも冷静に動けます。
その準備こそが、店を守る一番の力になります。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 判断に迷わず、落ち着いて店を導きたい方は、次の記事も参考にしてください。