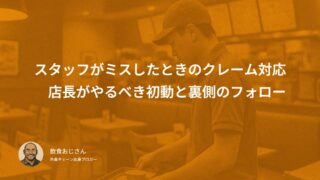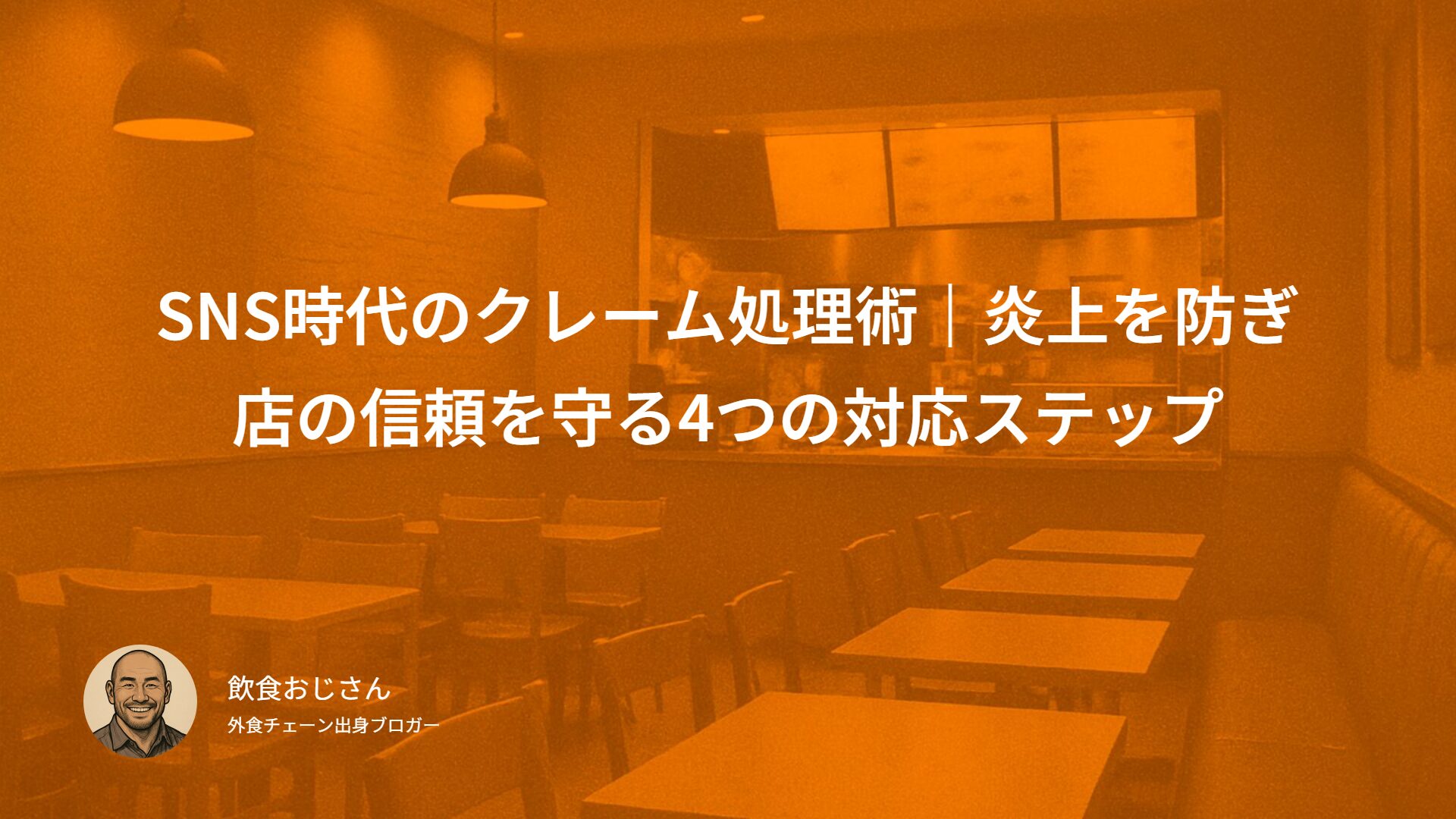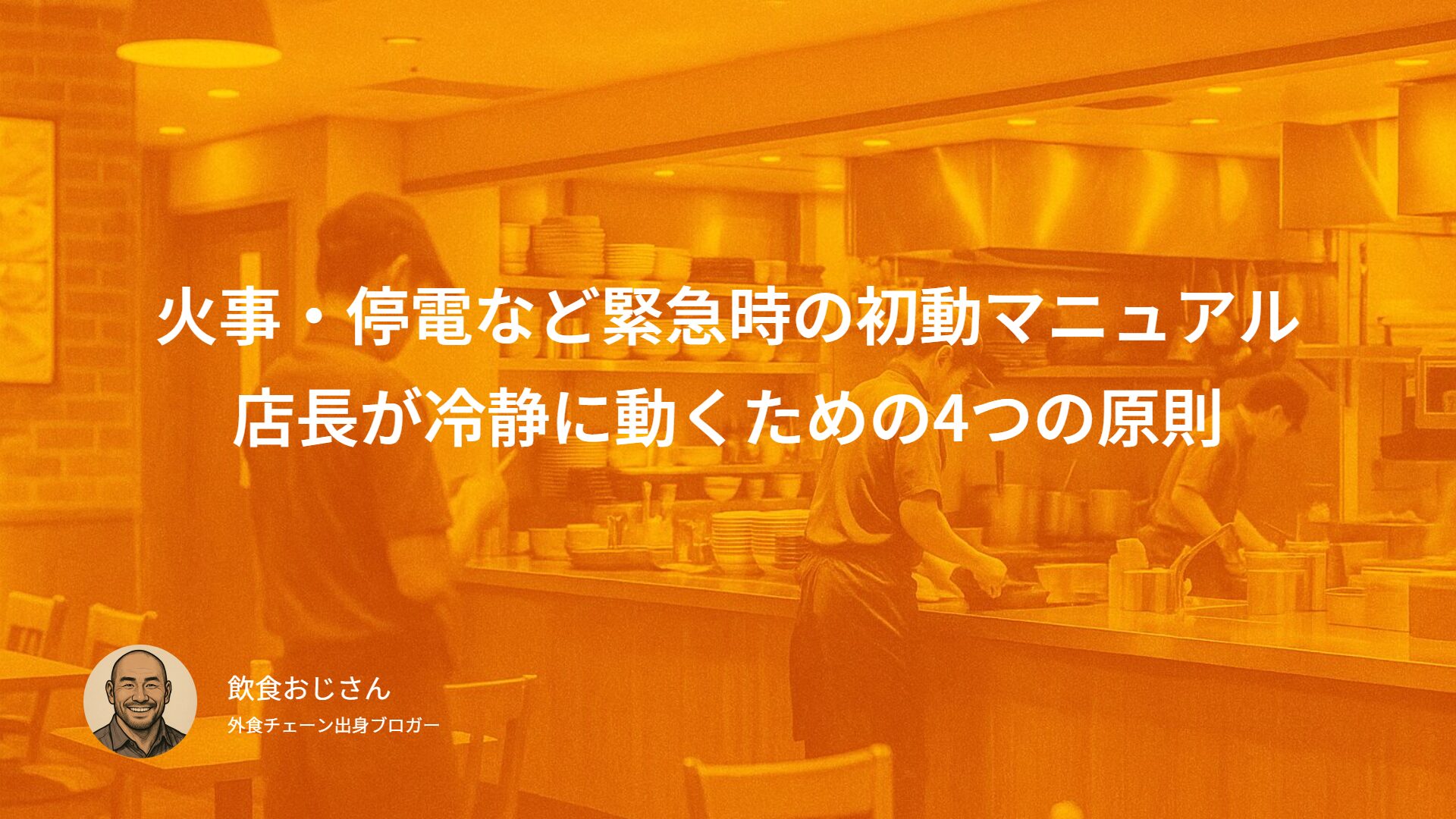クレームが起きたときに絶対やってはいけない対応|飲食店店長が学ぶNG対応リスト
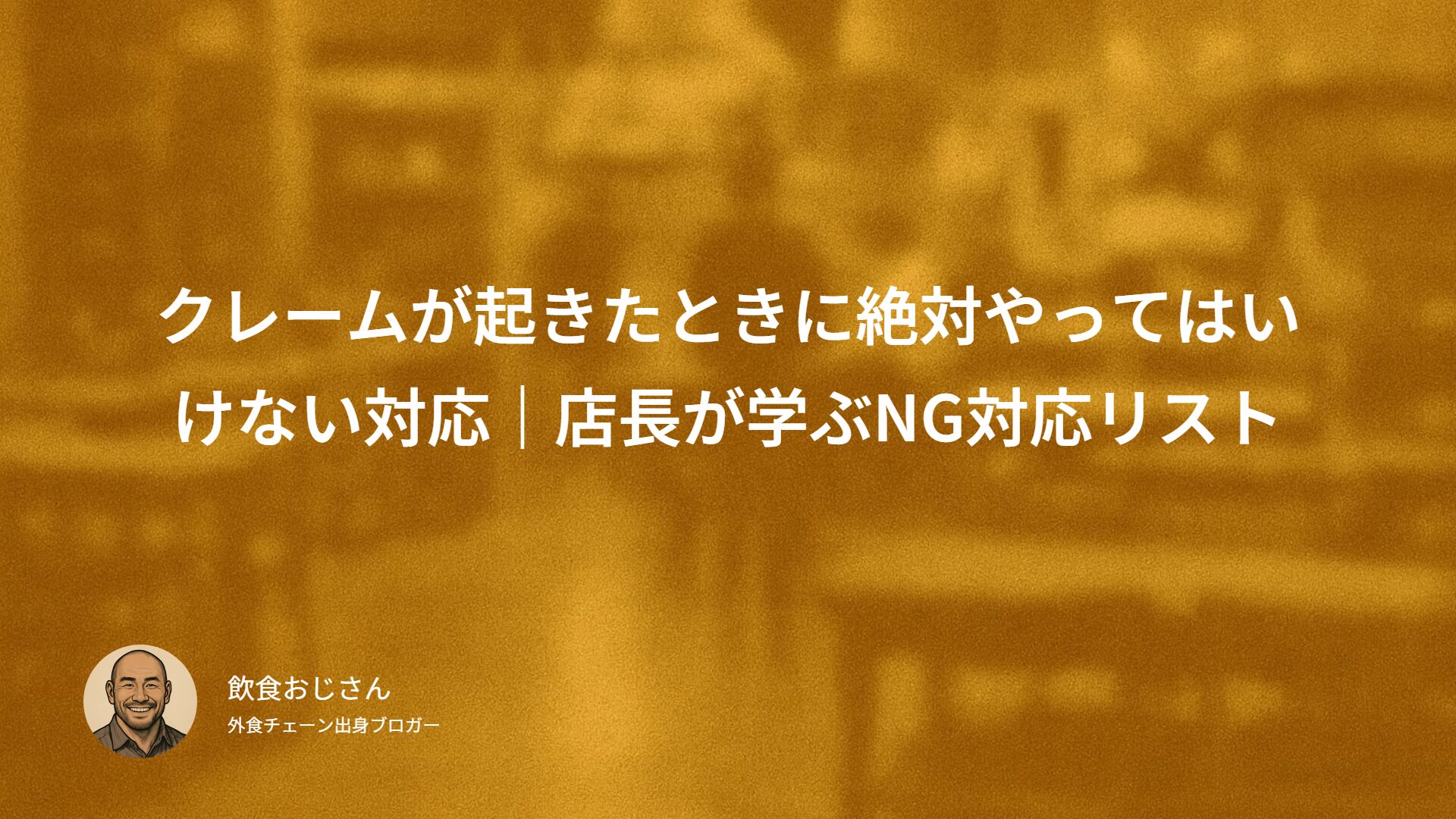
クレーム対応で
「余計にお客様を怒らせてしまった…」
そんな経験はありませんか?
店内では一刻を争う場面が多く、ついその場しのぎで動いてしまいがちです。
しかし実は、クレームが発生したときに“絶対にやってはいけない対応”が存在します。これを知らずに対応してしまうと、信頼は一瞬で失われ、店全体の評判にまで影響します。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗の運営に取り組んできました。

本記事では、飲食店でよくあるクレーム時のNG対応と、その背景、そして信頼を守るための正しい対応の流れを解説します。
✅この記事を読むメリット
- クレーム時に絶対避けるべきNG対応がわかる
- お客様の信頼を守るための正しい初動が学べる
- 再発を防ぐ仕組み化のヒントが得られる
「どう対応すべきか迷う瞬間」をなくすために、最後まで一緒に整理していきましょう。
現場でやってしまいがちなクレーム対応ミス

クレーム対応は一瞬の判断が店の評価を左右します。
ところが現場では「とっさに出てしまう言葉」や「場を収めたい気持ち」から、かえって状況を悪化させてしまう対応が少なくありません。
ここでは、飲食店でよくあるNG行動を整理します。
商品やサービスに対して不満のある消費者が、店舗対応を求める…日常的に店舗で謝罪要求を受けるようになっている(厚生労働省資料)
その場しのぎの言い訳
お客様が怒っているときに、つい口にしてしまうのが
といった言い訳です。
一見すると状況説明ですが、相手からすれば「責任逃れ」にしか聞こえません。結果的に「店全体の責任感がない」と映り、クレームはさらに拡大してしまいます。
責任をスタッフに押し付ける対応
と担当者を指摘する対応もNGです。
お客様は「誰が悪いか」より「どう解決してくれるか」を求めています。
責任を個人に押し付けると、店長自身の信頼も同時に失われますし、スタッフの士気も下がり、チーム全体の雰囲気まで悪くなります。
感情的に反応してしまう瞬間
と、つい言い返してしまうケースもあります。
正論をぶつけても、お客様の怒りはおさまりません。むしろ「客を否定した店」として悪評が広がる危険すらあります。
SNS時代では、この一言が数百人に拡散される可能性もあるのです。
クレーム対応でやってはいけないNG行動3選
| NG行動 | なぜNGなのか | 起きやすいシチュエーション |
|---|---|---|
| 言い訳をする | 責任逃れに聞こえ、さらに怒りを買う | 忙しいときに「混んでいたので…」と答える |
| 責任をスタッフに押し付ける | お客様は解決を望んでおり、責任転嫁は不信感を招く | 店長が「新人がやりまして…」と言う |
| 感情的に反応する | 否定や言い返しは悪評につながりやすい | 「そんなことはしていません!」と反射的に答える |
クレーム時に大事なのは“感情”ではなく“対応の型”。冷静さを失った瞬間に勝負はついてしまいますよ。

なぜNG対応が生まれるのか?

クレーム対応でNG行動が出てしまうのは、単なる「店長やスタッフの性格の問題」ではありません。
多くの場合、背景には店舗運営上の仕組みや環境の不備があります。ここでは、その主な原因を整理します。
仕組み不在による場当たり対応
クレームが起きたときにマニュアルやルールが整っていないと、現場は「その場しのぎ」で動かざるを得ません。
たとえば「謝るのか?」「説明するのか?」という判断基準がなく、結果的にスタッフごとに対応がバラバラになります。
統一されない対応は、さらにお客様の不信感を招きます。
人員不足・教育不足の影響
忙しい店ほど、クレーム対応の教育は後回しになりがちです。
「まずは現場を回すこと」が優先され、クレーム時の会話例や初動フローを共有できていないため、若手スタッフはパニックに陥ります。
人手不足が続く中で「経験不足の人が最前線に立つ」こと自体が、NG対応の温床になっているのです。
数字を意識しすぎた判断の誤り
売上や回転率に意識が向きすぎると、クレーム処理を「早く終わらせること」に走ってしまいます。
結果として「とりあえず謝って終わり」「お金を返して追い返す」など、短期的な処理に偏りがちです。
しかし、お客様が本当に求めているのは「誠実に聞いてくれた」という安心感であり、
スピード処理だけでは逆効果になることもあります。
NG対応が生まれる3つの原因
| 原因カテゴリ | 現場の典型的な状況 | 結果起きるNG対応例 |
|---|---|---|
| 仕組み不在 | マニュアルやルールが整っていない | スタッフごとに対応がバラバラ |
| 人員・教育不足 | クレーム対応の研修がされていない | パニックで謝罪すらできない |
| 数字優先の誤り | 売上や回転率だけを重視 | 「とりあえず返金で終わらせる」 |
通常の接客から逸脱した利用者からのクレームや苦情、行き過ぎた要求の線引きはどのような基準で判断するのかが課題である(厚生労働省)
NG対応の多くは“人のせい”ではなく“仕組みの欠如”から生まれます。人を責めるより、仕組みを整えることが再発防止の第一歩ですよ。

👉 SNSで拡散されるのが怖く、クレーム対応に慎重になりたい方は、次の記事も参考にしてください。
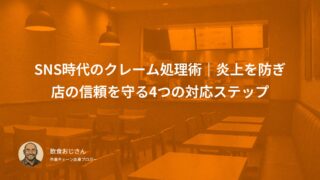
信頼を失わないための正しいクレーム対応

クレーム対応で一番大切なのは「お客様の信頼を守ること」です。
そのためには場当たり的な謝罪や返金ではなく、再現性のある“型”を持つことが欠かせません。
ここでは現場で実践できる正しい対応の流れを紹介します。
✅ すぐに謝る前に“聞く”姿勢を示す
多くの店長やスタッフが「まず謝らなければ」と考えますが、拙速な謝罪は逆効果になる場合があります。
お客様は「自分の話を聞いてほしい」という思いを抱えているため、まずは遮らずに耳を傾けることが大切です。
相槌やメモを取りながら聞くだけでも、「この店は真剣に向き合っている」と伝わります。
✅ 事実確認と共感のバランスを取る
聞き終えた後は、事実確認をしながら「ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と共感を示します。
ポイントは「お客様の感情に寄り添う言葉」と「事実に基づく説明」をバランスよく伝えること。
片方だけに偏ると「形式的」「言い訳している」と受け取られる危険があります。
✅ 再発防止策をその場で伝える
クレームが収束しないのは「また同じことが起きるのでは」という不安を残してしまうからです。
そのため「本日中に再確認いたします」「次回からこのように改善いたします」と、具体的な防止策を提示することが重要です。
小さな改善案でも、その場で言葉にすることで信頼回復につながります。
✅ 仕組み化でスタッフ全員が同じ対応を取れるようにする
まずは事実関係、因果関係を確認し、自社に過失がないか判断基準を明確にし、現場と共有しておくことが望ましい(厚生労働省)
クレーム対応を一部のベテラン任せにしていると、再現性がなくなります。
新人でも同じように対応できるよう、事例を共有したり「初動対応マニュアル」を整備することが効果的です。
仕組みに落とし込むことで、誰が対応しても一定水準を守れる“安心できる店”になります。
クレーム対応の基本フロー
遮らず、相槌やメモで「聞いている」ことを伝える
「ご不快な思いをさせて申し訳ありません」と感情に寄り添う
何が起きたかを冷静に整理し、お客様に確認する
「次回から〇〇を徹底します」と改善策を提示
クレーム対応は“その場を収める技術”ではなく“信頼を守る仕組み”。個人の神対応より、全員で再現できる仕組みを優先しましょう。

まとめ|クレーム対応で信頼を守るために避けるべき行動

クレーム対応でやってはいけない対応と正しい解決策
クレームは飲食店にとって避けられない課題ですが、「やってはいけない対応」を避けるだけでも信頼を守ることができます。
今回紹介したポイントを整理すると以下の通りです。
- 言い訳・責任転嫁・感情的な反応は信頼を失うNG行動
- NG対応は“人の失敗”ではなく“仕組み不在”から生まれる
- 信頼を守るには「聞く→共感→事実確認→再発防止」の流れを仕組みに落とし込むことが重要
「完璧を目指す必要はありません。“やってはいけない対応”を避けるだけで、店の信頼は十分に守れますよ。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 スタッフのミスでお客様が怒っている場面を、落ち着いて収めたい方は、次の記事も参考にしてください。