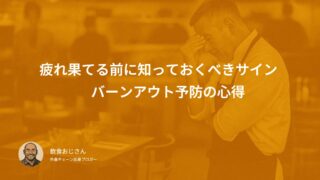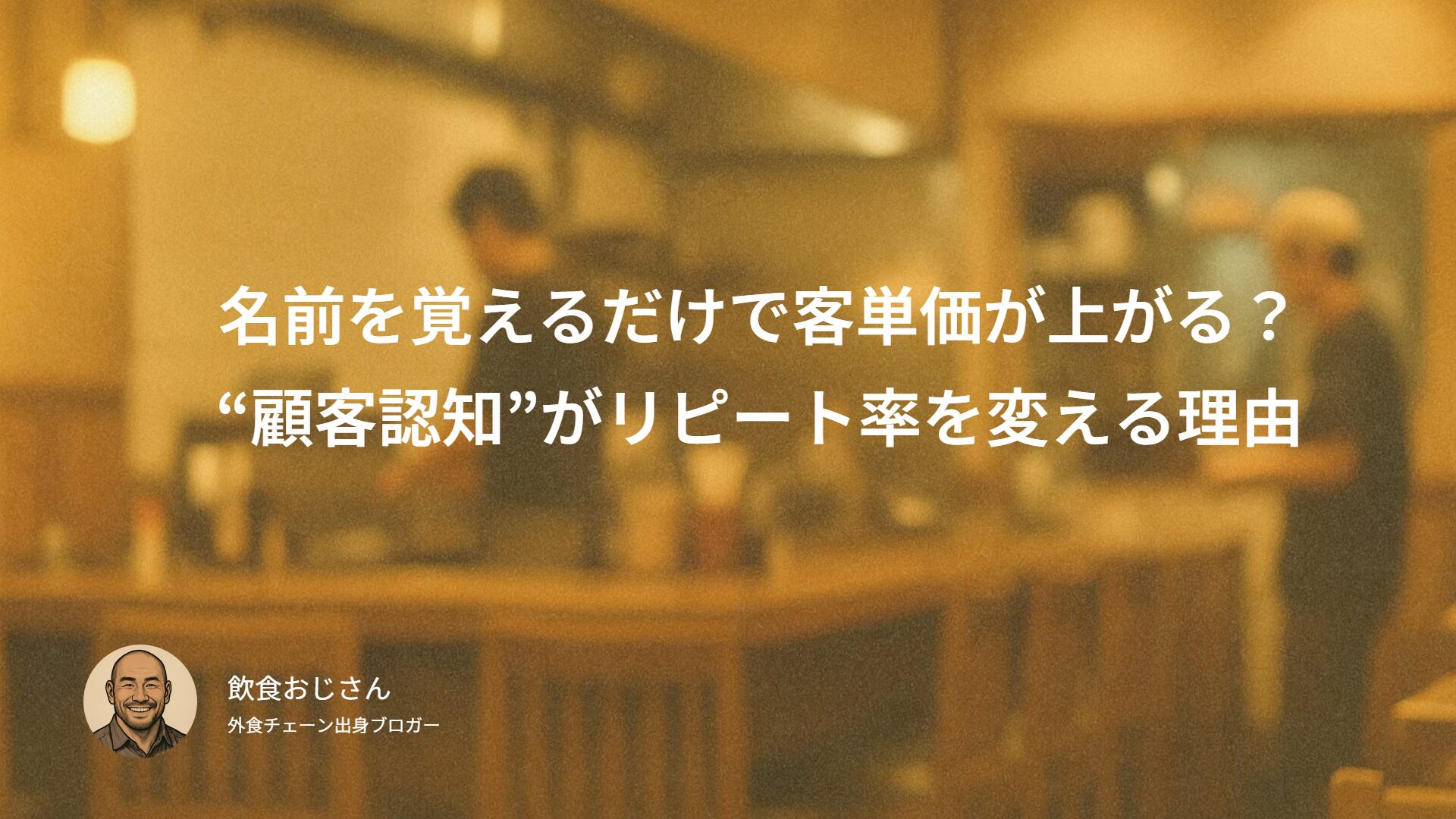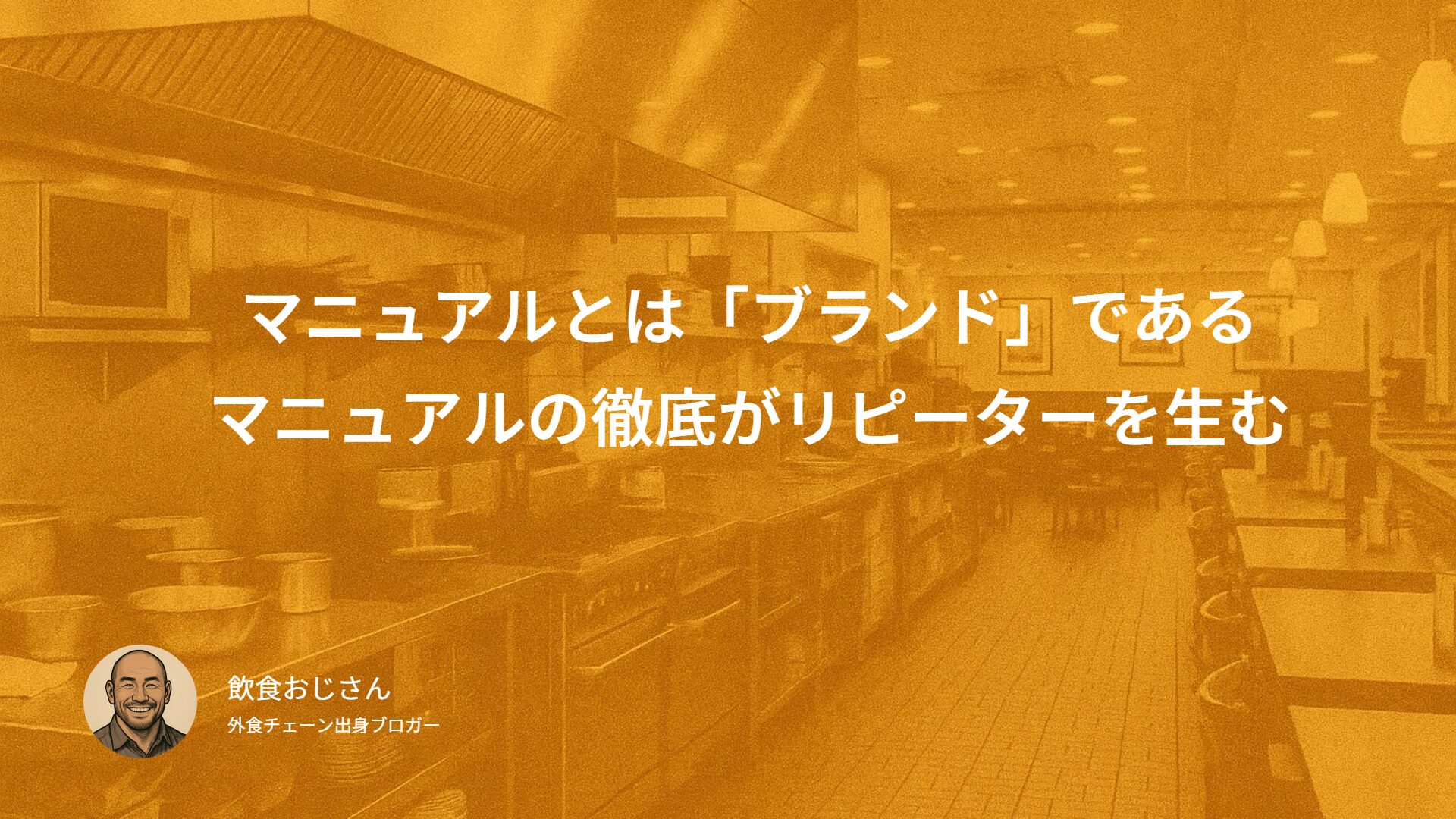常連が通う店に共通する5つの仕掛け|飲食店のリピーター戦略
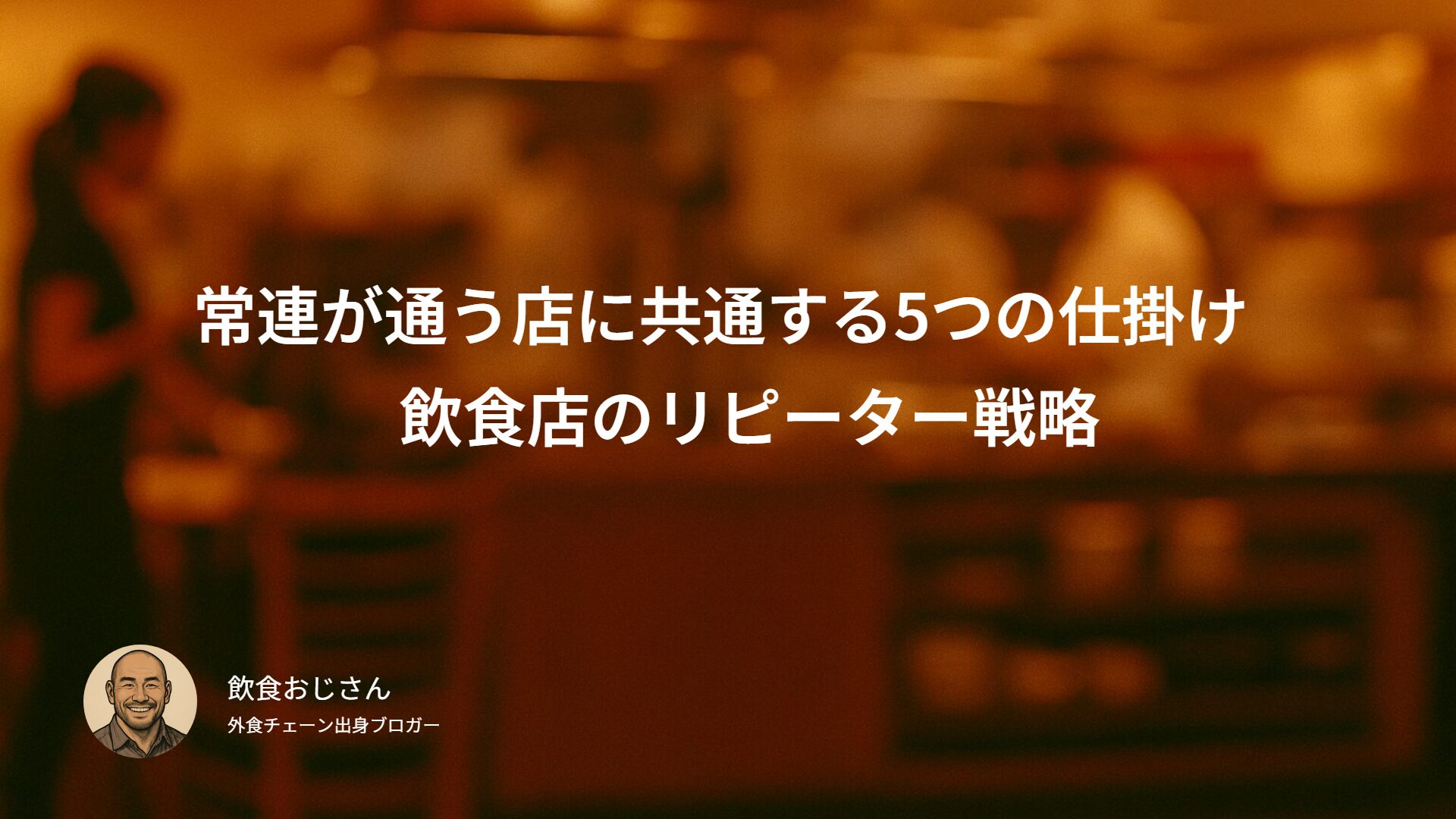
「一度は来てくれるけど、その後なかなか続かない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
新規のお客さんを呼び込むのは大切ですが、実際に店を支えてくれるのは“常連客”です。ところが、リピーターが育たない店は、売上が安定せず毎月の数字に振り回されがちです。
「おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗運営に取り組んできました。」

この記事では 「常連が通う店に共通する5つの仕掛け」 を現場目線で解説します。
✅ この記事を読むメリット
- 常連客が「また来たい」と思う理由がわかる
- リピーターを増やすための具体策を学べる
- 売上を安定させる仕組みづくりのヒントが得られる
「リピーターをどう増やすか」を考えているなら、最後まで読むことで明日から取り入れられるヒントが見つかります。
なぜ常連が店を支えるのか
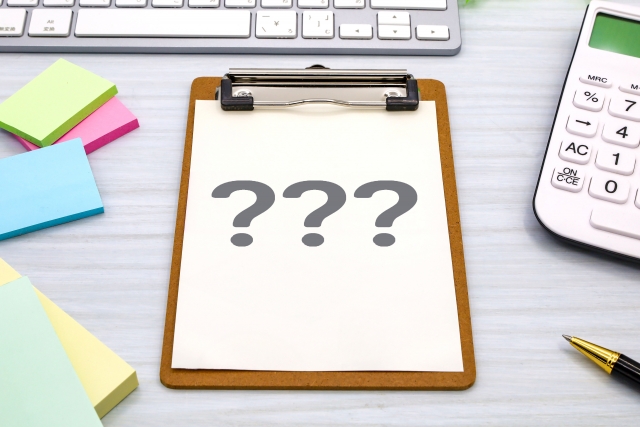
リピーターの売上インパクト
例えば、ある調査では「売上の6〜7割は常連客から生まれる」と言われています。
新規客は広告やキャンペーンで一時的に集まりますが、継続して来店してくれる保証はありません。
ところが常連客は、安定的に来てくれるだけでなく、家族や友人を連れてきてくれることも多い。つまり「1人の常連客=複数の新規客を連れてくる可能性がある」わけです。
新規客と常連客の比較表
| 項目 | 新規客 | 常連客 |
|---|---|---|
| 来店頻度 | 低い | 高い |
| 広告コスト | 高い | ほぼゼロ |
| 客単価 | 変動が大きい | 安定しやすい |
| 店への貢献 | 単発的 | 継続的+紹介を生む |
現場あるある「常連が減る理由」
一方で「常連が定着しない」店には共通する落とし穴があります。
クーポンや割引に頼りすぎて、常連の特別感がなくなる
スタッフの入れ替わりで、顔なじみの安心感が消える
忙しさに追われ、会話や気配りが減ってしまう
私自身、店長時代に一度経験しました。
新規集客に注力しすぎて常連への対応が疎かになった結果、「あのお客さん最近見ないな…」という状況が続いたのです。
短期的には売上が上がっても、常連が減ると数字はすぐに落ち込みました。
『飲食店営業(一般食堂)の実態と 経営改善の方策』厚生労働省(引用元)
常連さんは“広告費ゼロ”で店を支えてくれる存在。ここを強くすると経営が安定します。

常連が通う店に共通する5つの仕掛け

① 顔と名前を覚える
人は「自分を覚えてもらっている」と感じるだけで特別な存在になれます。
と声をかけるだけで、再来店率はぐっと上がります。
高額な施策よりも、日常の積み重ねが効く部分です。
② 居心地の良さを演出する
常連は料理だけでなく「空間」に価値を感じています。
- 自分の好きな席が確保できる
- 照明や音楽が落ち着く
- 店員の接し方が心地よい
こうした要素の総合点が「また来よう」と思わせるきっかけになります。
③ 特別扱いの小さな工夫
誕生日にひとこと声をかける、好みのドリンクを先に提案するなど、小さな積み重ねが常連を「ファン」に変えます。
派手なサービスではなく「自分のことを知ってくれている」という実感が肝心です。
④ 安心できる“ブレない体験”
味や接客にバラつきがあると、常連は離れていきます。
どのスタッフでも同じ体験ができる「ブレのなさ」は、マニュアルだけでなく教育の仕組みから生まれます。
⑤ 会話から始まる関係性
「今日はお仕事帰りですか?」の一言が関係を深めます。
売上を意識したセールストークではなく、ちょっとした会話のキャッチボールが信頼を育てるのです。
常連が増える仕掛け5つのまとめ表
| 仕掛け | ポイント | 具体例 |
|---|---|---|
| 顔と名前を覚える | 認知と安心感 | 「田中さん、いつもありがとうございます」 |
| 居心地の良さ | 空間・接し方 | 好きな席を覚える、照明やBGM調整 |
| 特別扱い | 小さな工夫 | 誕生日の声かけ、好みのドリンク |
| ブレない体験 | 安心感 | どのスタッフでも同じ接客 |
| 会話 | 関係性づくり | 「お仕事帰りですか?」の一言 |
仕掛けは“派手なサービス”じゃなく、日常の積み重ねです。

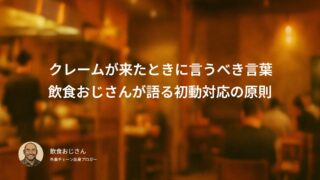
常連を増やす仕組みづくり

『飲食店でリピート率を高める方法は?平均や調べ方も解説』出典:オーダーアールメディア
✅ 短期でできる工夫
まずは今日からできる小さなアクションです。
こうした行動はほとんどコストがかからず、すぐに効果が出やすいのが特徴です。
✅ 長期で効く仕組み
一方で、常連を安定的に増やすには「仕組み」が欠かせません。
好みや来店頻度を簡単に記録
「常連対応は誰でも同じようにできる」を徹底
誕生日や来店回数に応じた小さな特典
これらは単発の工夫ではなく「仕組み化」することで、担当スタッフが変わっても継続できます。
短期の工夫と長期の仕組みの比較表
| 期間 | 具体策 | 特徴 |
|---|---|---|
| 短期 | 名前を呼ぶ、次回来店の声かけ | コストゼロ・即効果 |
| 長期 | 顧客台帳、教育マニュアル、特典ルール | 継続的に効果、誰でも再現可能 |
✅ 成功事例(体験談)
私が店長時代に力を入れたのは「スタッフへの見本づくり」でした。
スタッフルームでわざと大きな声で、
とオーバーアクションで手本を見せるんです。
その後スタッフにも真似をさせて、できたらすぐに褒める。
実際の接客でも私が率先してやることで、シャイなスタッフも自然と同じように行動してくれるようになりました。
お客さんは明らかに嬉しそうで、笑顔や会話が増えたのを実感しました。
やり方を共有するだけでなく、現場で“見せる”ことが仕組みになると気づいた瞬間でした。
一度来たお客さんを“また来たい”に変えることが、最も効率のいい戦略です。

まとめ|常連づくり成功のポイント
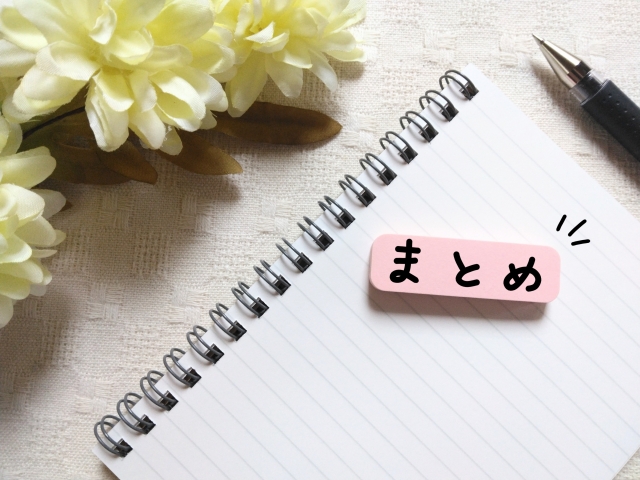
リピーター戦略を実現する3つの視点
常連を増やすことは、飲食店にとって“売上の安定”そのものです。派手なキャンペーンよりも、日常の小さな積み重ねが効いてきます。
今回ご紹介した内容を振り返ってみましょう。
- 常連は売上の大黒柱であり、新規客以上に店を支えてくれる
- 通う店には「覚える・居心地・特別感・ブレなさ・関係性」の共通点がある
- 短期の工夫と長期の仕組み化を組み合わせることでリピーターは増えていく
結局のところ、常連づくりは「特別な魔法」ではなく、日常の積み重ねを仕組みに変えることです。
「派手な集客より、常連さんを大切にすること。これが最強のリピーター戦略です。」毎日“本当に”おつかれさまです。

常連づくりを続けるには、店長自身のコンディション管理も欠かせません。
👉 続けて 「店長が疲れ果てる前に知っておくべきサイン」 もご覧ください。