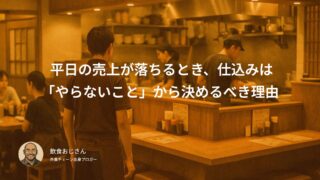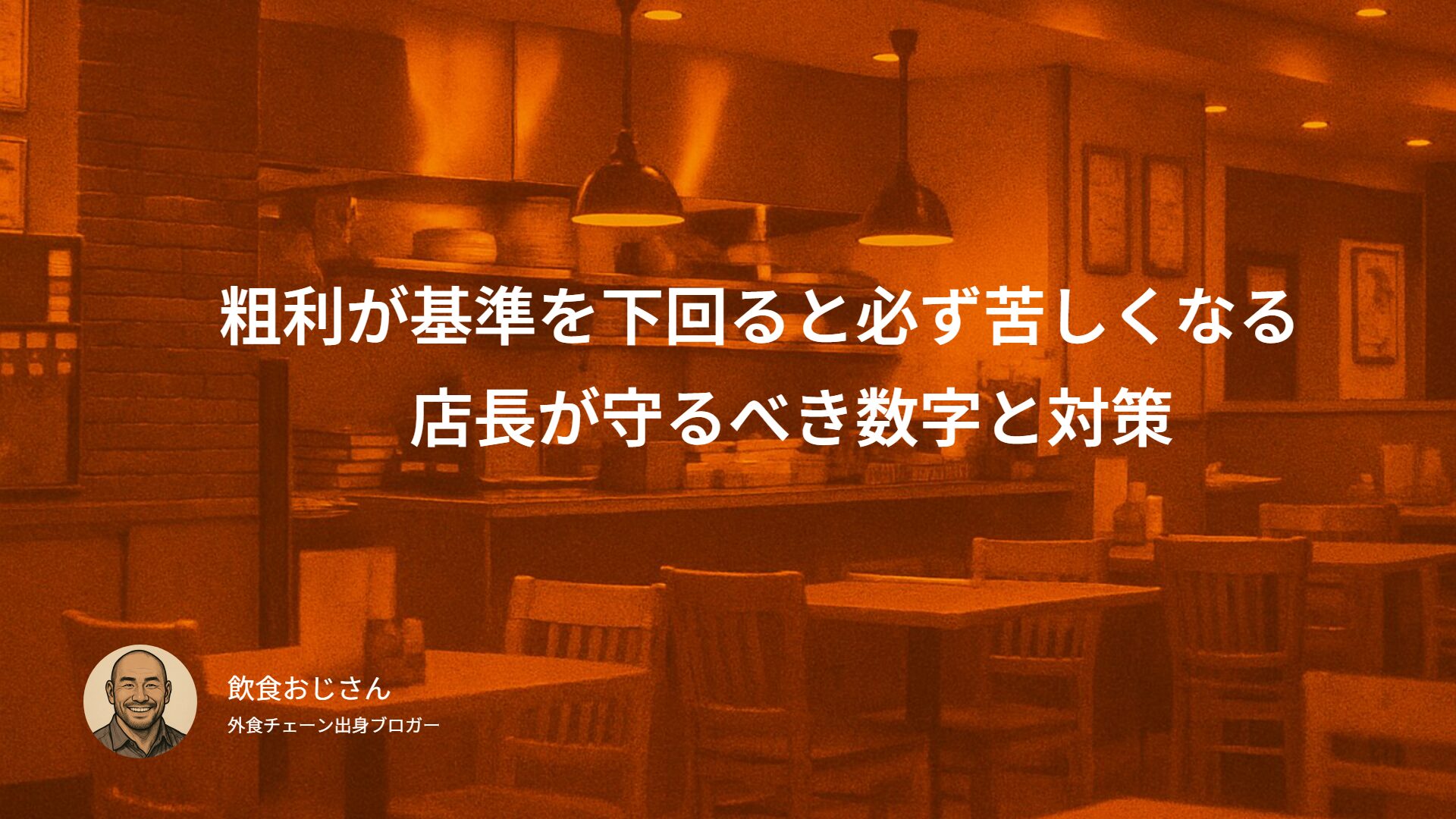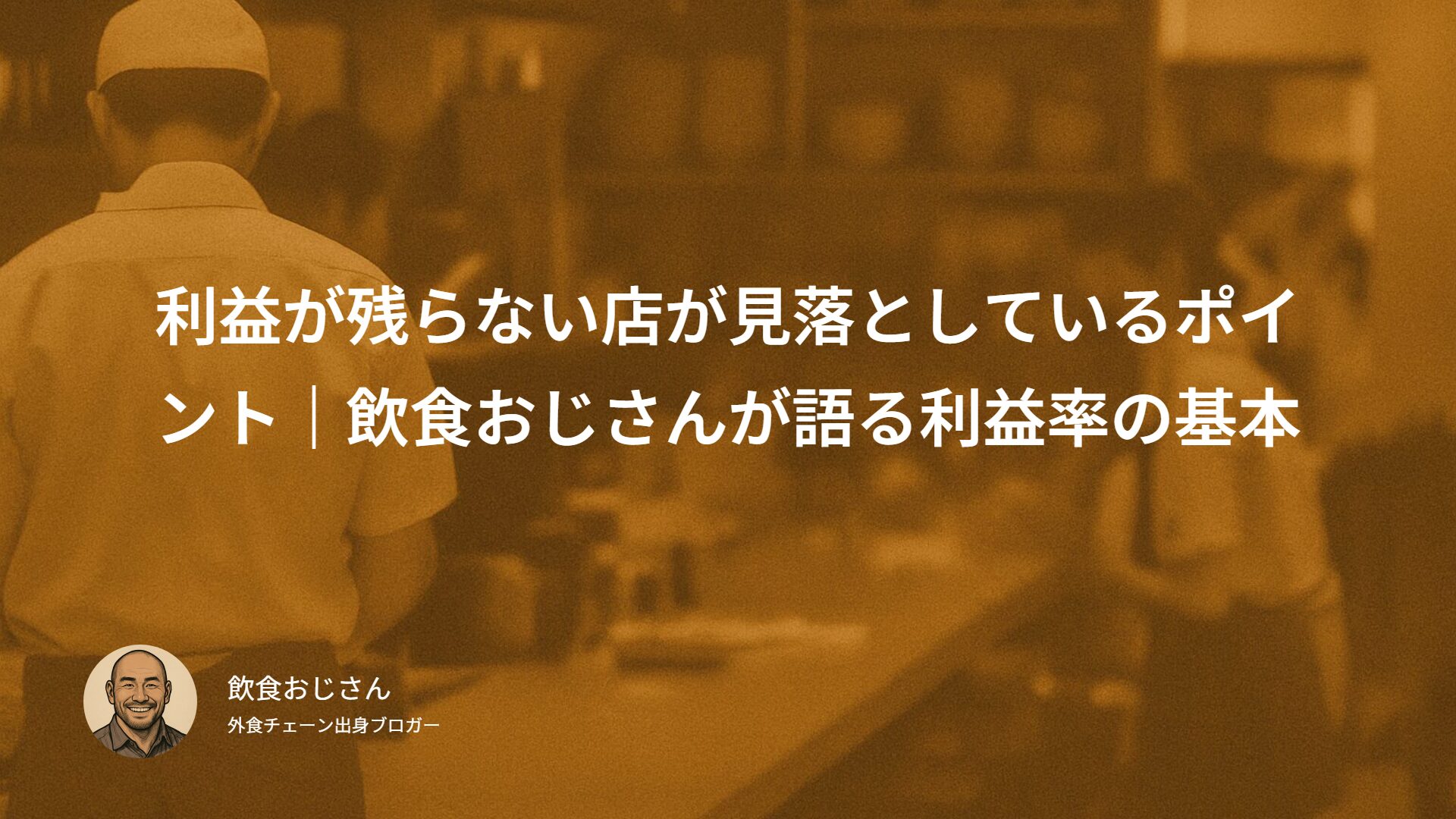粗利が合わないのは自分のせい?|本部の基準とどう向き合うか
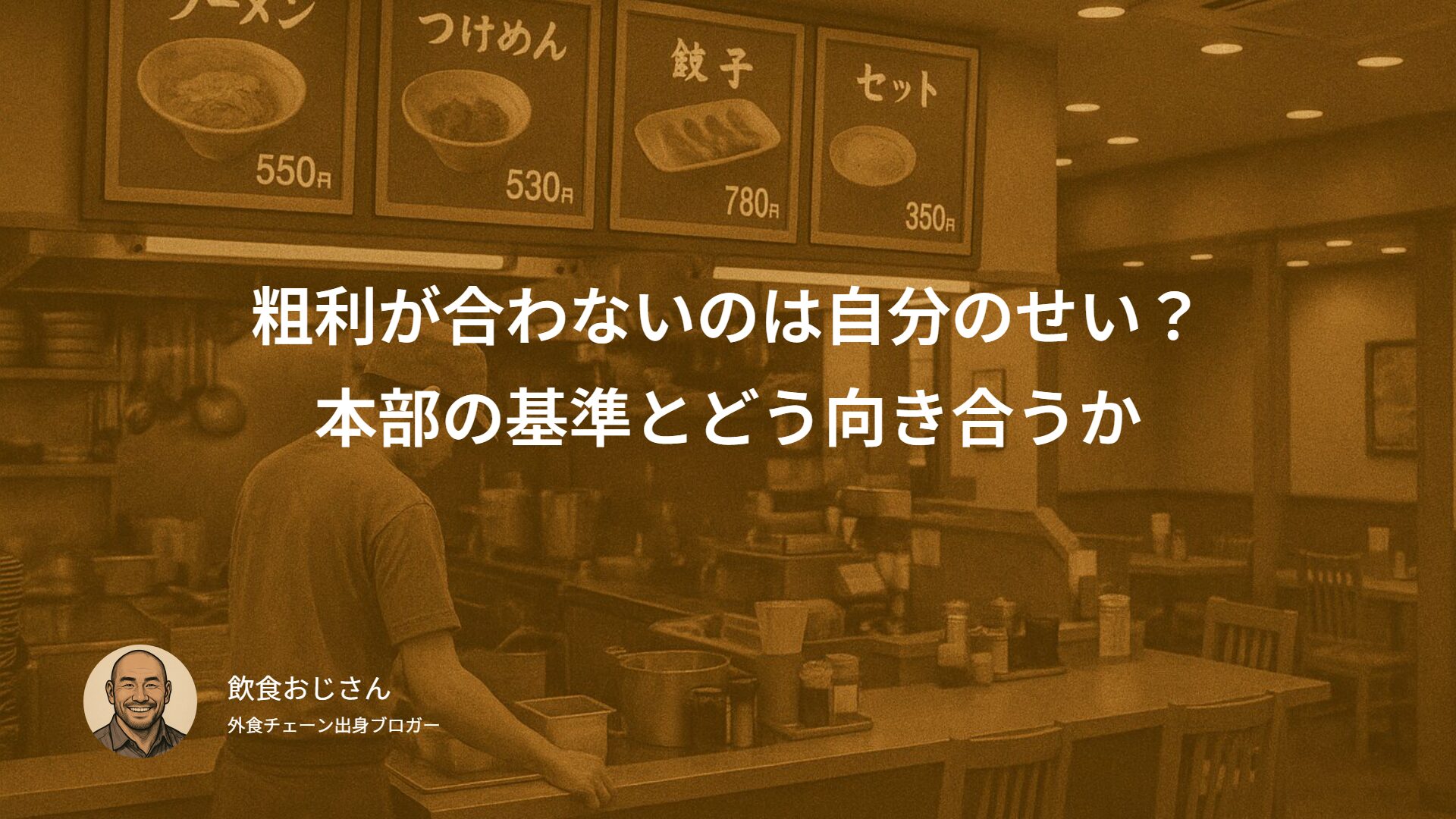
「粗利が合わない」――数字を見て、そんな不安を感じたことはありませんか?
本部の基準を守っているのに、粗利率が悪く見える。
手を抜いているわけでも、ロスを放置しているわけでもない。
でも数字は、まるで「やってない人」のように映ってしまう……。
正直にやってる人ほど、なんだか報われない気がする。あれ、なんなんでしょうね。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗運営に取り組んできました。

本記事では、「本部が計算している粗利」と「現場の感覚」のズレを整理しながら、
正直にやってる人が“報われる考え方”をお届けします。
✅ この記事を読むメリット
- 粗利の数字に対する捉え方が変わる
- 自分の働き方が数字に合わなくても、正しかったと納得できる
- 本部とのズレをどう受け止めればいいかがわかる
自分を責める前に、いったんこの記事を読んでみてください。「やるべきことは、もうやっていた」と気づくかもしれません。
粗利率が合わないときに感じる疑問と不安

自分の損益を見ながら、「なんでこんなに粗利が悪いんだ?」と感じたことはありませんか?それなのに、会議では「○○店は粗利がいい」と言われる。
「あれ、自分だけ何か間違ってるのか……?」そんな不安が、じわじわ湧いてくる瞬間を経験したことがある方もいるでしょう。
真面目にやってるほど「なぜ?」が残る
これは、手を抜いてる人には起きません。むしろ、基準通りに丁寧にやっている人ほど「なんでこんな数字になるんだ?」と疑問を感じる。
たとえばこんなときです:
……それでも数字が合わない。
「ズルしてない人だけが損してる気がする」
自分では誤魔化しもしていないし、決められたやり方も守っている。でも、ふと耳に入ることがあります。
「あの店ではこうしてるらしいですよ」
アルバイトの雑談や、異動してきたスタッフのひとこと。
もちろん直接は言わないし、誰も明言しない。でも、その情報が頭に残ると、ふと考えてしまうんです。
「自分だけ真面目にやって、バカを見てるんじゃないか……」
「評価の数字と、やってきた仕事が噛み合わない」
本来、数字は「がんばりの結果」を見せてくれるもののはず。
でも粗利に関しては、「ちゃんとやってるほど悪く出る」ことがある。この瞬間に、数字そのものへの信頼が少し揺らぐのです。
粗利が合わないのは、やってないからじゃありません。やってるからこそ“ごまかせない数字”が出てくるのです。

粗利基準がズレてしまう3つの理由

「この粗利率、正直にやってたら届かない」そう感じたことがある方へ、まず伝えたいのはこれです。
粗利は「実行するには厳しい基準」で作られています。
だから、ていねいにやってもわずかにズレることはあります。
でもそのズレは、月商500万円の店で1%=5万円。小さく見えて、決して軽く扱えない数字です。
だからこそ、「自分はちゃんとやった」と言えるかどうかが、判断の軸になります。
使用量と歩留まりは“実務”とずれている
本部が作る粗利計算では、食材の使用量が“実行するには厳しい基準”で設定されています。
- 魚の脂のノリやサイズによって、歩留まりが微妙に変わる。
- ネタが薄すぎればクレームになるため、状況によって厚めに切ることもある。
- 出た端材は基本的に冷凍保存して使い切る運用にしているが、切り落としの量やタイミングによって、粗利に少し影響が出ることもある。
こうした日々の判断と修正は、本部の数字には正確に入っていません。
仕入れ価格と納品ロットに微妙なブレがある
「一括仕入れだから単価は一定」と思われがちですが、実際には
こうした小さなブレが積み重なると、粗利に“ジワッと”影響が出るのです。
でも、資料上では一律になっているため、“理論では合ってるのに、体感ではズレてる”ということが起きます。
粗利で評価されるのは当然。でも前提がズレていると不公平になる
粗利で評価されることに異論はありません。数字で判断されるのは当然のことで、それ自体が悪いわけではないと思います。
実際、粗利は「どれだけ適正に利益を残しているか」を示す重要な指標です。
ただし、その数字が「どんな条件で計算されているか」に目を向けなければ、正直にやっている人ほど損をする構造が生まれてしまいます。
食材の状態にバラつきがある
歩留まりが想定より悪くなることもある
マニュアル通りにやっても、理論値に届かないケースがある
それでも、「粗利が悪い」という一点だけで評価されてしまうと、まじめにやっている人間が「ちゃんとやっているのに……」と感じてしまいます。
粗利率がズレる具体的な要因一覧
| 要因カテゴリ | 具体的な内容 |
|---|---|
| 使用量・歩留まり | 魚の脂のノリ、ネタの厚さ調整、端材の扱い |
| 納品状況 | スペック外の納品、日による品質差 |
| コスト構成 | 代替品対応、ロットによる変動 |
| 運用のギャップ | 計算通りにいかない現場の動き、理論値との誤差 |
ズレがあることは不思議ではありません。「実行するには厳しい基準」と実際の運用結果が100%一致するなんてことは少ないのが現実です。

👉 売上はあるのに利益がなかなか残らないと感じている方は、次の記事も参考にしてください。
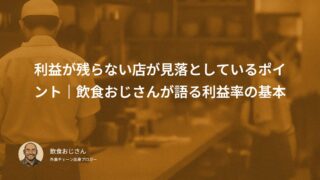
正直にやっても粗利が届かないとき、どう考えるべきか

粗利が悪い。
本部からそう言われると、納得いかないこともあると思います。
基準通りにやっていても届かないことはあるし、他店との違いを知ってモヤモヤすることもあるかもしれません。
でも、そこで悩み続けるのは正直もったいないです。もっとエネルギーを使うべき場所は他にあります。
✅ どこまでいっても“比べるだけ無駄”
店長会で数字が共有されると、「うちだけおかしい?」と感じることがあります。ただ、他店のやり方をいちいち気にしてもキリがない。
もちろん、仲がいい人から正直な話を聞くことはあります。
「あんなもん、無理に決まってるって」
そんな本音を聞いて安心した経験がある人もいるでしょう。
でも、だからといって粗利のズレが消えるわけでもないし、他店のやり方をまねしたところで根本的な解決にはなりません。
比べるだけ時間の無駄です。
✅文句を言っても、状況は変わらない
粗利の数字は、理想的な条件で作られています。だから、正直にやればズレが出るのは当然といえば当然。
でも、「ズレて当然だ」と主張しても、数字が変わるわけではないし、上からの見え方が変わることもない。
むしろ「言い訳」として扱われるリスクの方が大きい。
冷静に受け止めて、処理するだけの話です。
✅指摘されたら1回だけ頭を下げる
やることをやっていても、指摘されることはあります。そんなときは、1回だけ頭を下げればそれで終わりです。
本部にも仕事がある
店にもやるべきことがある
社会人同士として、表面だけ合わせれば十分
そのあと引きずらない。反論もしない。さっさと済ませて、次にやるべきことに集中する。
それがいちばん現実的な動き方です。
✅ どうしても納得いかないなら、すべて記録する
本当に納得できない。
自分のやり方が正しいことを証明したい――そう思うなら、手はあります。
全工程を動画で記録する
盛り付け・計量・廃棄・仕込み、すべて手順通りにやっている証拠を残す
粗利計算と突き合わせて、客観的に差を示す
ここまでやれば、設定した側もぐうの音も出ないでしょう。やろうと思えば、できます。
でも、現実にはこうです。
記録には時間も労力もかかる
その間、他の仕事が滞る
店の数字全体から見れば、1%のズレの話
そして、たいていの場合――
上にいる人間はある程度「わかっててやっている」のです。
あなたの上司にも上司がいます。……しょうがないだろ?

まとめ|粗利が合わない時に店長がとるべき冷静な判断とは
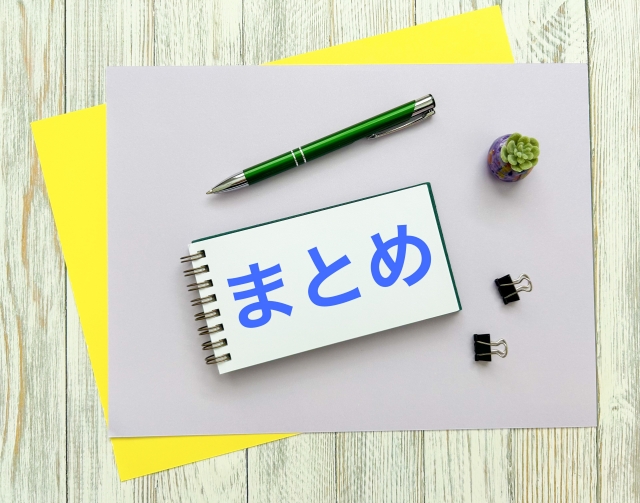
粗利のズレは“おかしい”のではなく“よくある話”
- 他店との違いにモヤモヤしても、比べるだけ無駄
- 正直にやっていても、届かないときはある
- 設定が厳しすぎることを、店の努力でカバーしきれないだけ
ズレに気づいたら微調整、でもそれ以上は引きずらない。粗利とどう付き合うかも、店長としての技術です。
粗利は大事な数字です。評価にも影響するし、見逃してはいけません。
でも、大事なのは、次の一手に集中することです。

👉 平日の売上が読めず、仕込みの判断に迷っている方は、次の記事も参考にしてください。