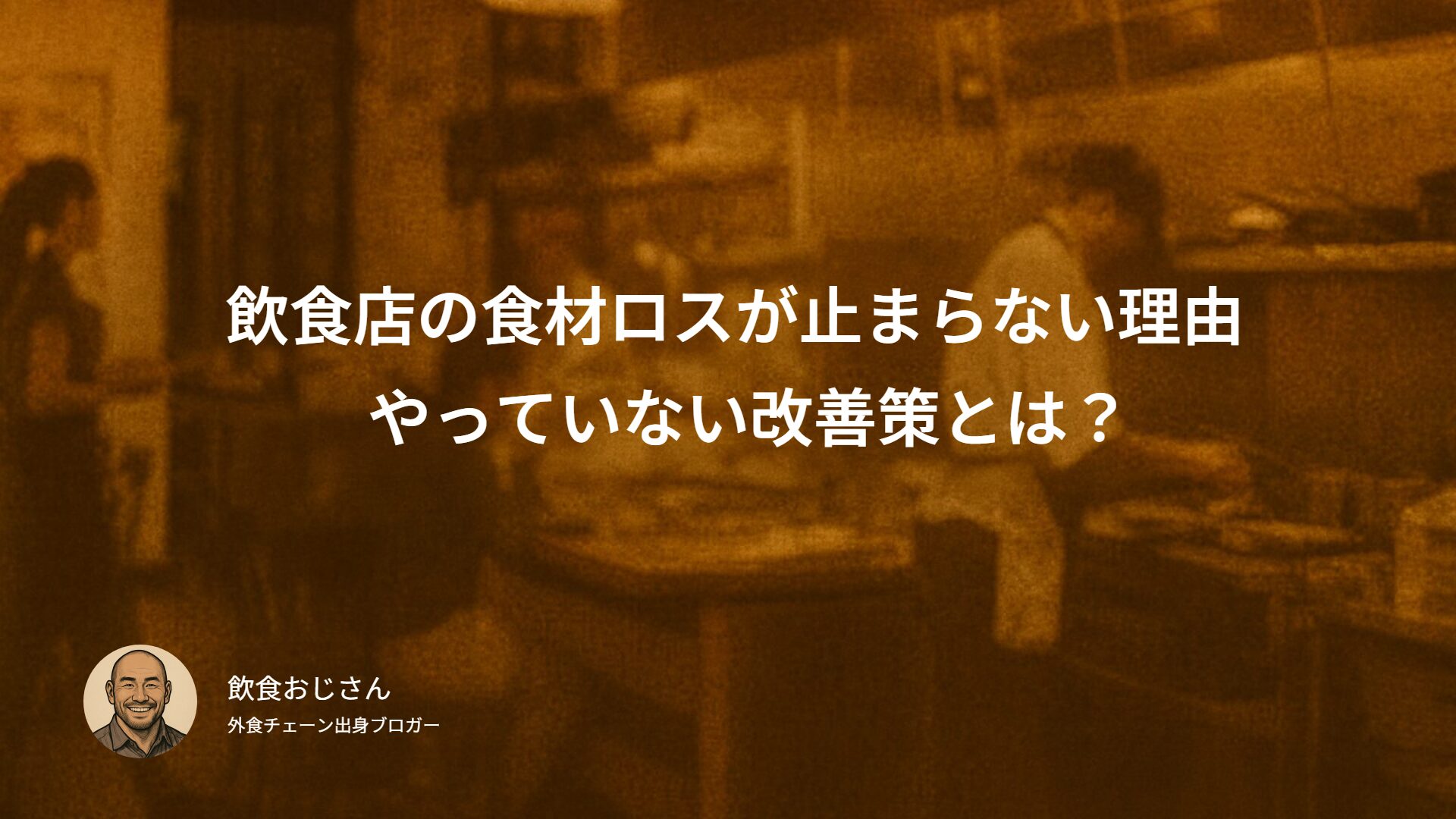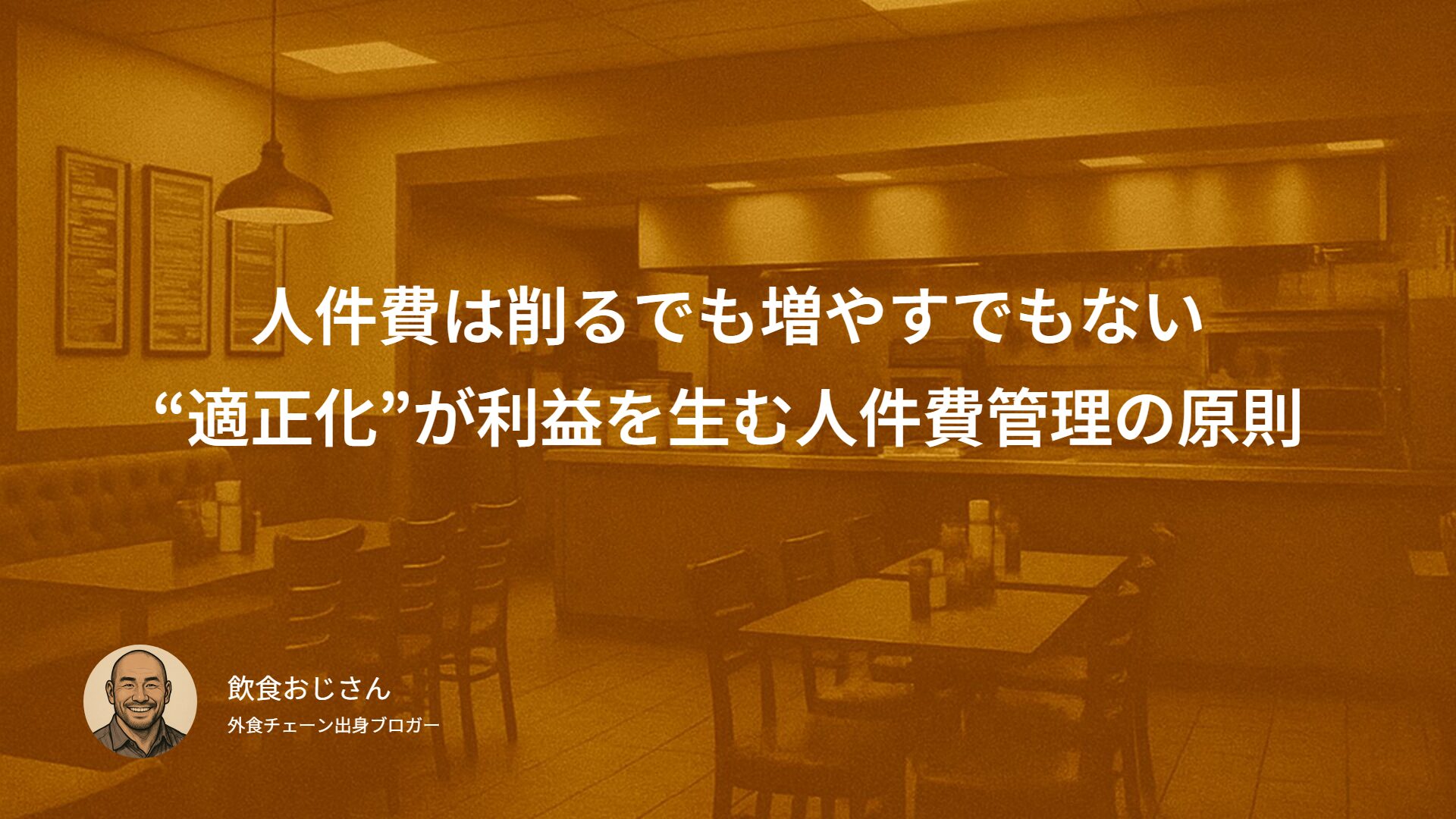廃棄を減らすための仕込み量の決め方|数字と感覚のバランスが店を強くする
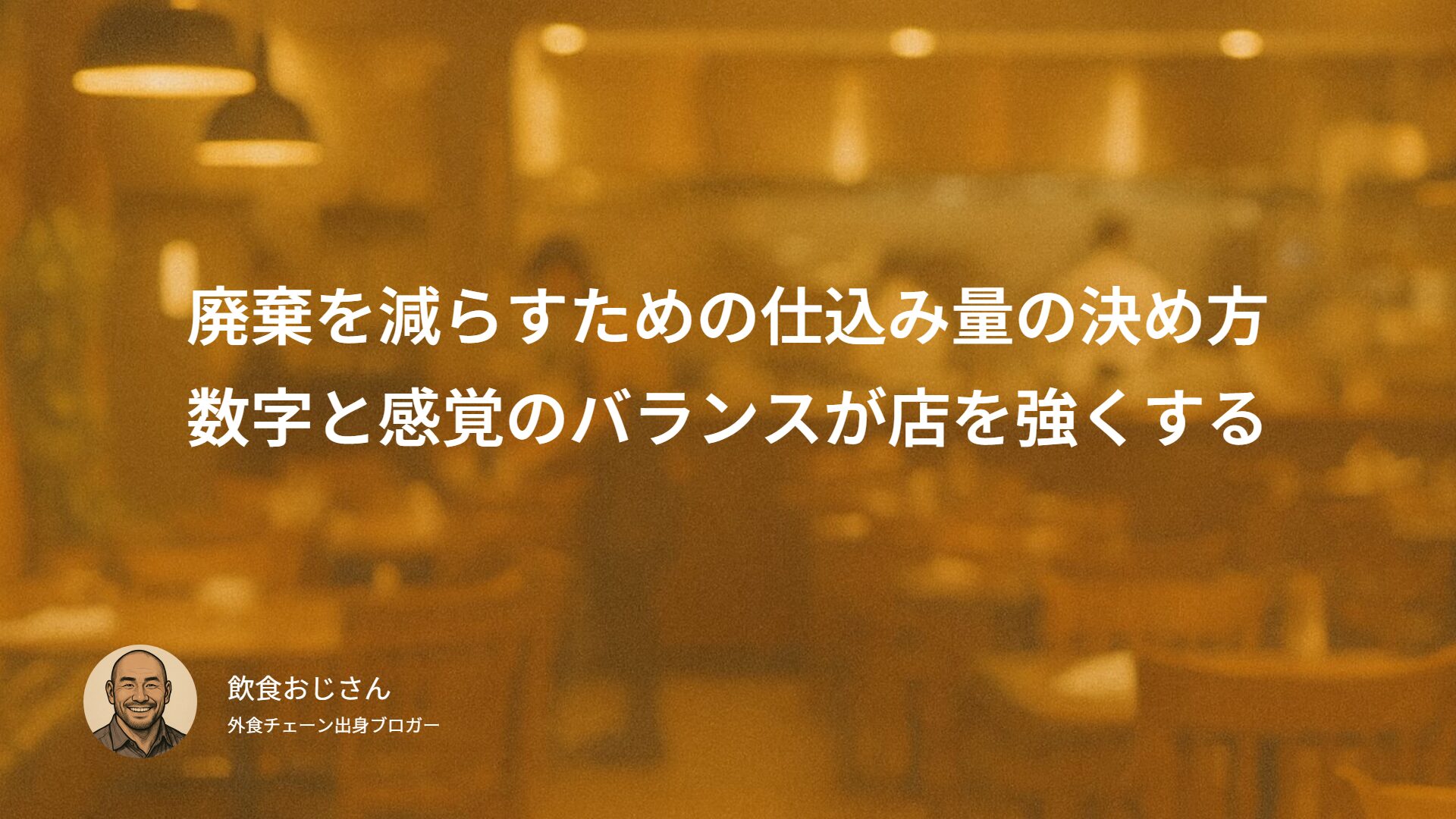
「仕込みを少なくしてロスを減らせ」
──頭では分かっていても、現場ではそう単純にいきませんよね。
売り切れればお客様に迷惑をかけ、余れば廃棄が出る。昔の私も、毎朝“データとにらめっこ”しながら、その狭間で悩んでいました。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗の運営に取り組んできました。

廃棄を減らすコツは、数字を信じることでも、感覚に頼ることでもなく、“数字と空気をつなぐ考え方”にあるということです。
✅ この記事を読むメリット
- 仕込み量を“感覚”ではなく“再現できる基準”で決められる
- 廃棄を「悪」ではなく「点検サイン」として扱える
- “数字と現場”をつなぐ店長思考が身につく
「仕込み量に迷う時間」を減らしたい店長へ。
本記事を読み終えたころには、明日の仕込みが“少し楽になる考え方”が見つかるはずです。
ズレは数字の問題ではなく、判断の問題です

数字は正しくても、使い方で結果が変わります
令和3年度の食品ロス量は約523万トンと推計されています。出典:環境省|食品ロスの発生量(令和3年度推計値)
仕込み量を決める際、多くの店舗が「昨日の販売数」や「平均実績」を基準にしています。
それ自体は正しい考え方です。しかし、問題は数字をどの視点で使うかという点にあります。
たとえば、昨日30食売れたから今日も30食仕込むという判断。一見合理的ですが、その30食が「なぜ売れたのか」を検証しなければ再現はできません。
偶然のヒット商品、天候、客層、スタッフの動き――条件が異なれば、同じ数字でも意味はまったく違ってきます。
数字を「答え」として扱うと、仕込みは一度きりの判断になります。
一方で、数字を「仮説の材料」として捉えれば、仕込みは再現性のある思考に変わります。数字は決断の“終わり”ではなく、“始まり”に使うものです。
判断を止めた瞬間に、仕込みはズレ始めます
ズレの原因は“分析ミス”ではなく、“思考の停止”にあります。
忙しいときほど「昨日と同じでいいか」と考えてしまいがちです。この瞬間に、現場の仕込み精度は確実に下がります。
判断とは、常に“今”の状況を整理する行為です。
一見単純な確認でも、これを毎日行うかどうかで、廃棄率は大きく変わります。
数字を扱い慣れた店ほど、この“現場の再確認”を軽視しがちです。しかし、数字は過去の積み重ねにすぎません。
今日の判断に使うのであれば、「今、何が違うのか」を常に意識する必要があります。正確さだけを追えば追うほど、現場の感覚は鈍っていきます。
数字は便利ですが、正解ではありません。数字を信じるというのは、考えることをやめないということです。

仕込み判断のタイミングを見誤ると、廃棄は止まりません

仕込みは「朝の1時間」で決まります
廃棄を減らす店ほど、朝の時間の使い方がうまいです。一日のリズムをつくるのは“朝の判断”です。「昨日の数字」を見るよりも、「今日の空気」を読むことが重要です。
朝に確認しておくべき3項目を明確にすると、仕込み判断の精度が上がります。
予約数と客層:予約状況、客層、団体有無をチェックする。
人員とスキル:誰が入っているか、仕込み能力と調理スピードを把握する。
天候と動線:天気・気温・イベント・交通量など、客足に関わる要因を確認する。
この3つを5分で整理できるだけで、当日の仕込み過多を防ぐことができます。
「安全マージン仕込み」がロスを生みます
多めに仕込むと、心理的には安心します。しかし、ロスの多くはその“安心の積み重ね”から生まれます。「万が一のため」のつもりが、実際には“慢性的な余剰”をつくっているのです。
もし不安を感じるなら、次の3点を意識してみてください。
- 売り切れの損失より、廃棄の損失を可視化する
→ 売り切れは一時的、廃棄は累積的です。 - 仕込みの「目的」を明確にする
→ 「足りなかったら困る」ではなく「必要な分を出し切る」へ意識を変える。 - 一日の仕込み目標を“量”ではなく“精度”で評価する
→ 廃棄量ではなく、仕込み精度(誤差率)をチームで共有します。
数字の多い店ほど、“仕込みの安心”がコスト化していることに気づいていません。
週単位で見てこそ“タイミング”が見えます
日ごとに仕込み量を調整しても、効果は限定的です。仕込み判断の誤差は「日単位」ではなく、「週単位」で補正する方が正確です。
1週間ごとの流れをまとめて振り返ることで、「どの曜日にズレが起きやすいか」が見えるようになります。
この“曜日別の誤差パターン”を可視化できると、感覚的な判断を数字で裏づけることができ、精度が格段に上がります。
焦って仕込むと、数字は乱れます。落ち着いて“流れ”を読む店ほど、ロスは減っていきます。

👉 仕込み判断の精度を上げたい方は、次の記事「飲食店の食材ロスが止まらない理由」も参考にしてください。
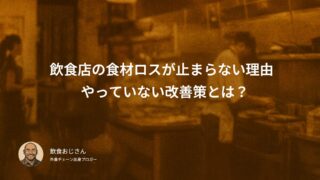
仕込み量を決める3つの基準

✅ ① 数字を“道具”として使う
数字は判断を助ける道具であって、答えではありません。過去データをそのまま当てはめるのではなく、基準線として扱うことが重要です。
たとえば、前年同日の売上が30万円だった場合でも、
- 天候
- 客層の変化
- メニュー構成
などの条件が違えば、数字の意味も変わります。
数字を使う際は、次の3点を意識します。
比較対象をそろえる(曜日・天気・イベントを揃える)
例外を除外する(特異日やキャンペーン日は分けて扱う)
「平均」より「傾向」で読む」(流れを重視する)
この3つを守るだけで、数字が“予想”ではなく“判断の基盤”として使えるようになります。
✅ ② 兆しを拾う観察力を鍛える
仕込み判断において、兆しを見抜く力は経験よりも重要です。数字に現れる前の“空気の変化”を感じ取れるかどうかで、ロス率は大きく変わります。
観察するポイントは次の通りです。
- 予約や問い合わせの増減
- SNSでの話題・口コミの反応
- 仕入れ先の動き(価格変動や入荷量)
- 店内の雰囲気(スタッフやお客様のテンション)
これらを毎日メモしておくと、数字では見えない“前兆”を掴めるようになります。
それが、経験を超えた「予測力」を育てます。
✅ ③ 当日の“余力”を読む
仕込みの判断は、材料だけでなくその日の人員状況によっても変わります。
人手が足りない日に多く仕込んでも、作業が追いつかず廃棄が出てしまいます。逆に、十分な人員が確保できている日は、多少多めに仕込んでも対応できます。
今日の人員で仕込みが回るかを確認する
ピーク前に仕込みが終わる時間配分を意識する
仕込み量を増やす日は、担当と責任者を明確にする
人の動きを“リソース”として捉えると、無理のない範囲で仕込み量を調整できます。判断の根拠が明確になり、仕込みの再現性も高まります。
仕込み判断に使う3つの基準
| 判断基準 | 主なチェック内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 数字 | 過去データ・売上・天候・曜日 | 数字は“基準線”として使う |
| 兆し | 予約・SNS・客層の変化 | 変化の前触れを捉える |
| 人 | 当日の人員・作業量・時間配分 | 無理のない仕込み量を設定 |
数字で見て、兆しで感じて、人で動かす。仕込みの精度は“理屈と空気の両立”で決まります。

まとめ|廃棄を減らすための仕込み量と適正在庫の考え方
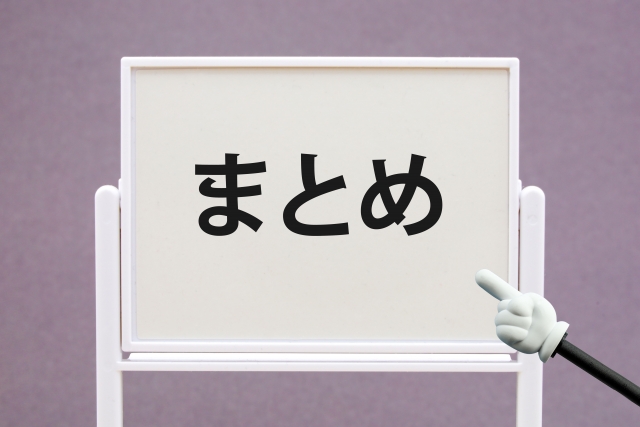
廃棄を減らす3つの判断基準と仕込み精度を上げる方法
- 仕込み判断は「数字・兆し・人」の3つの視点で行う
- 廃棄は“悪”ではなく、判断を見直すサインと捉える
- 精度の高い仕込みは、日々の仮説と検証の積み重ねで実現する
過去データを読み、兆しを感じ取り、当日の余力を見極める。その積み重ねが、ロスを最小限に抑えた「再現性のある仕込み」を生み出します。
仕込みを減らすより、判断の精度を上げることです。数字を使いこなせば、廃棄は自然と減っていきます。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 次の記事「“マニュアルを守る”という仕事の基本」もご覧ください。当たり前を徹底する力が、チームを強くします。