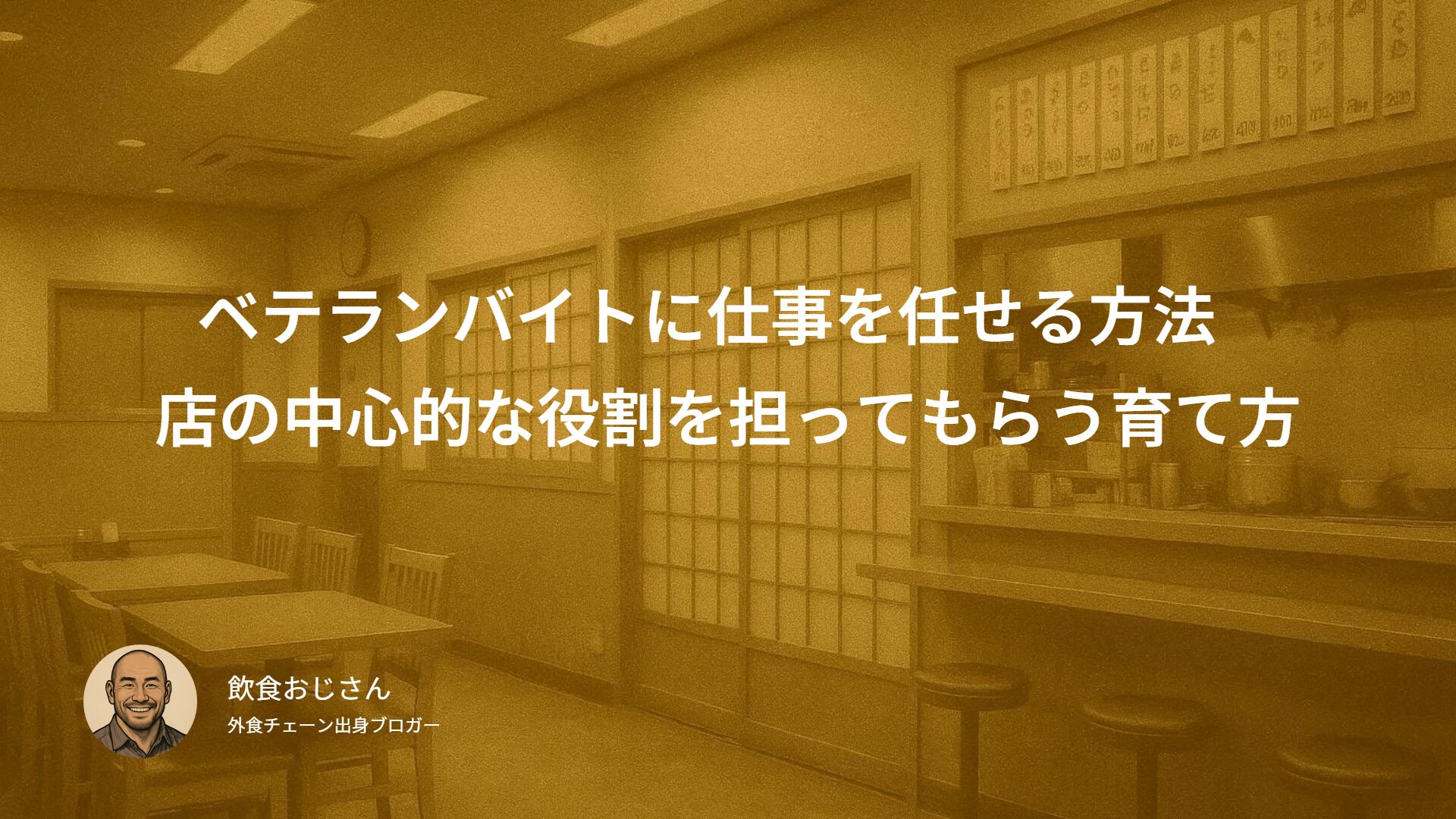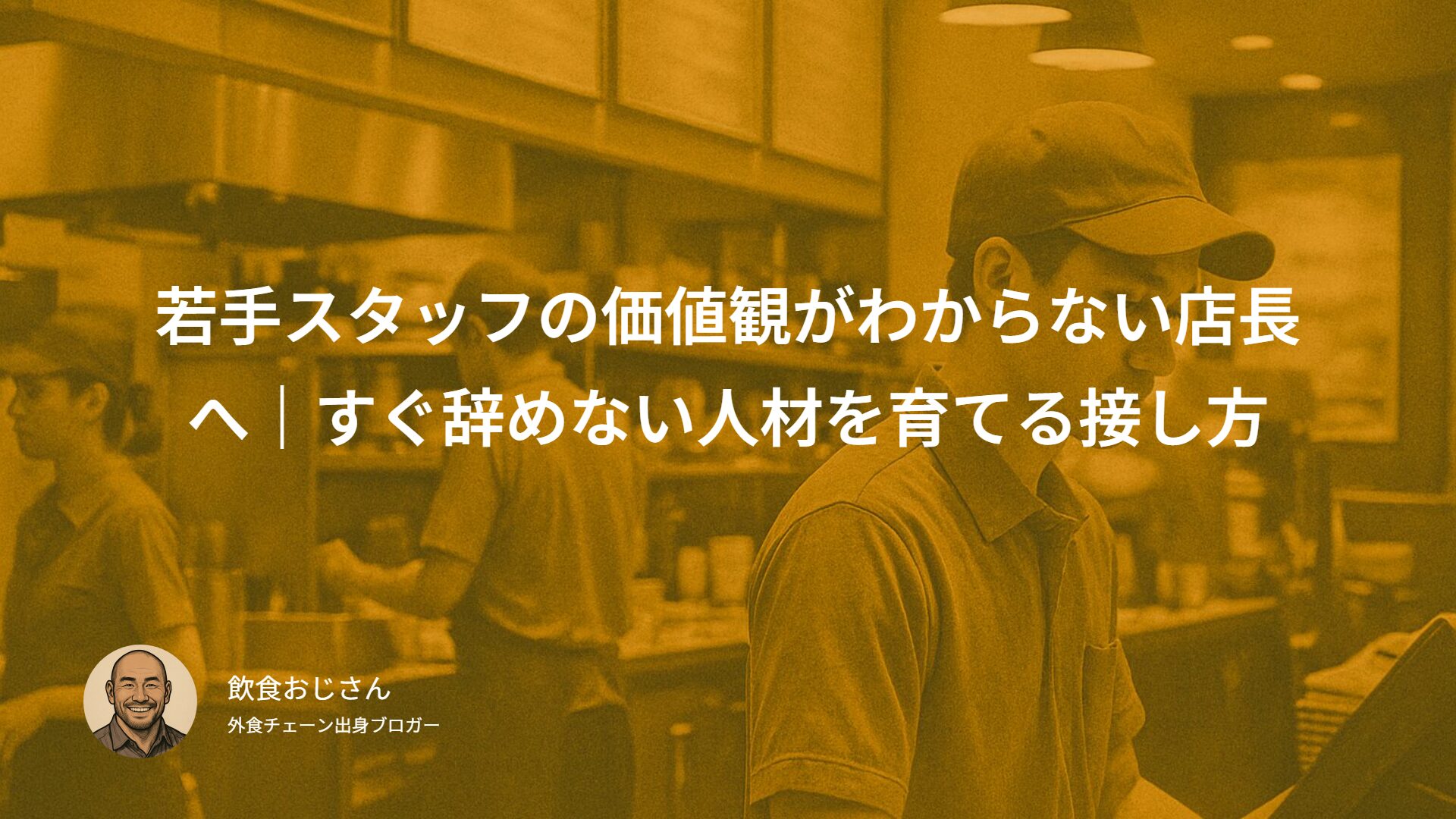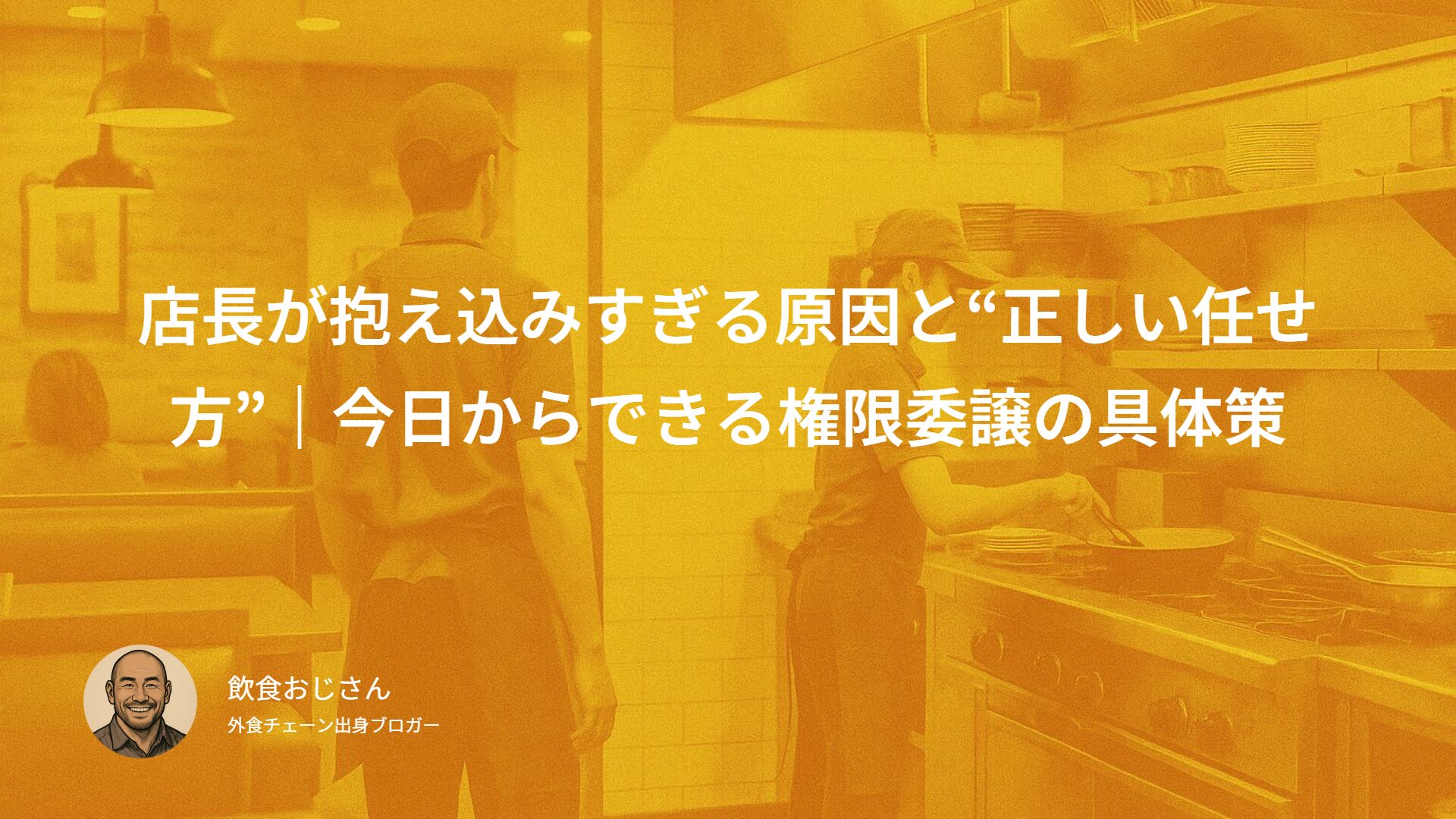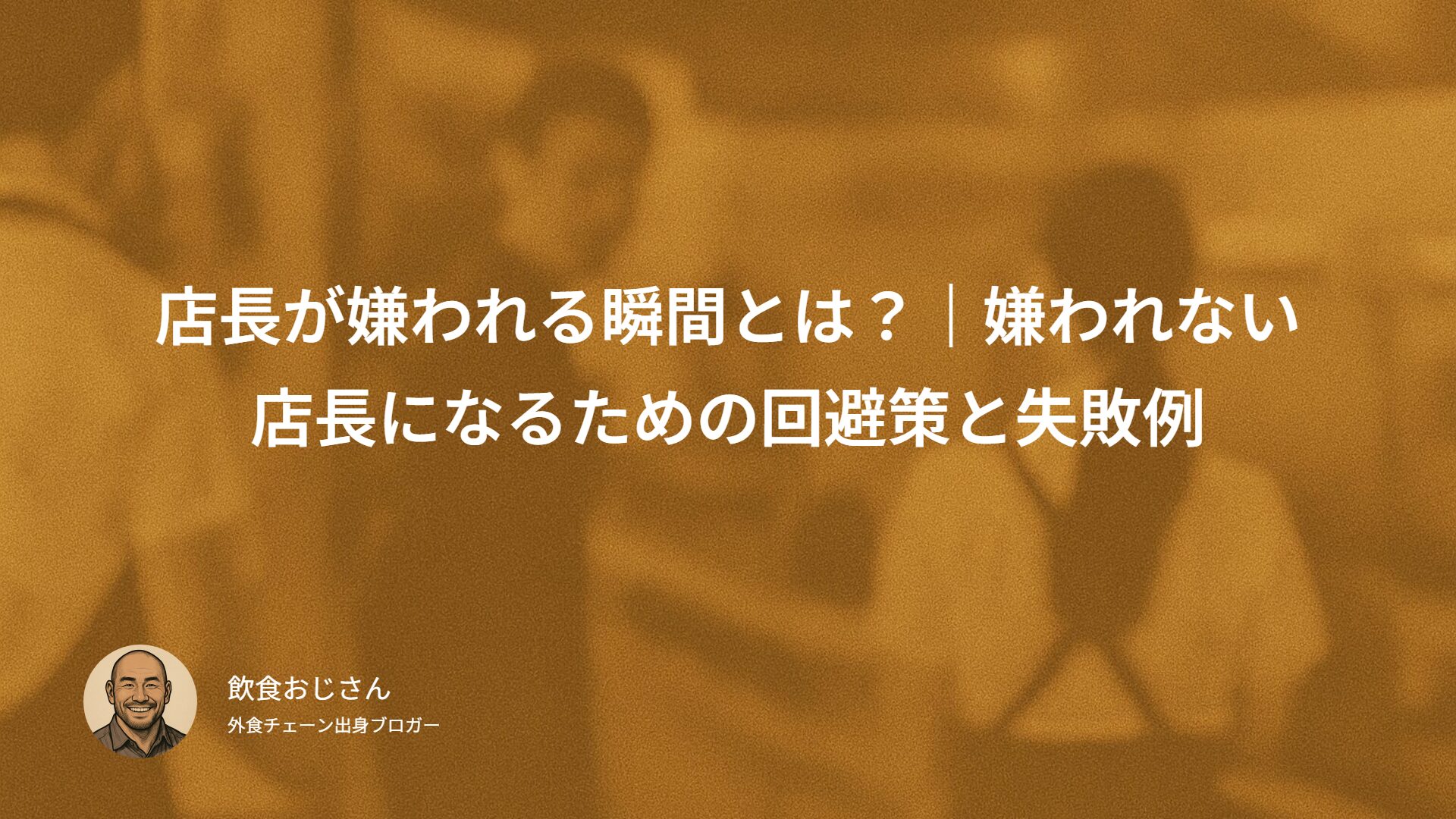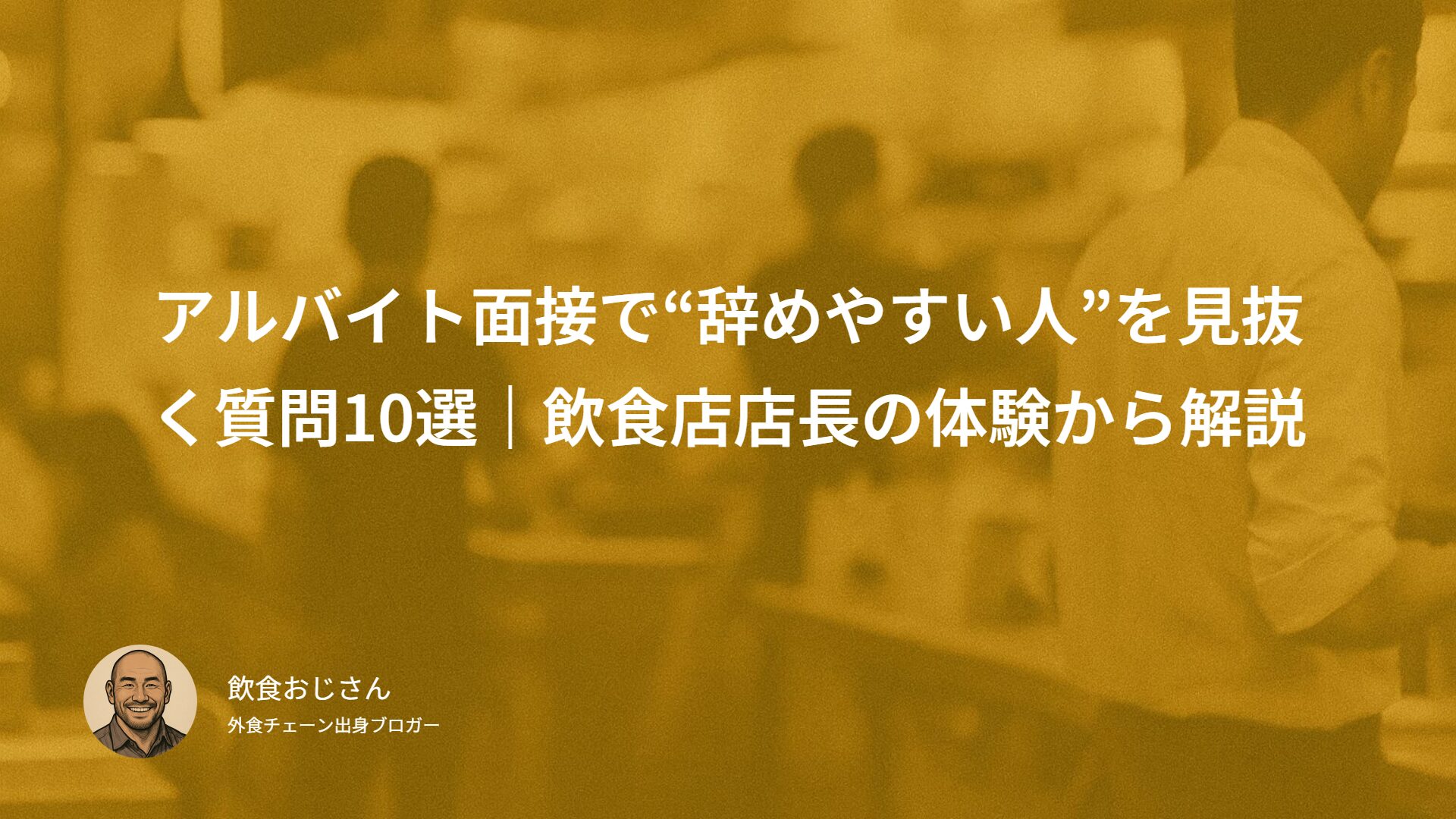教え方がバラバラをなくすチェックリスト|マニュアルを“使いこなす”店長の育成術
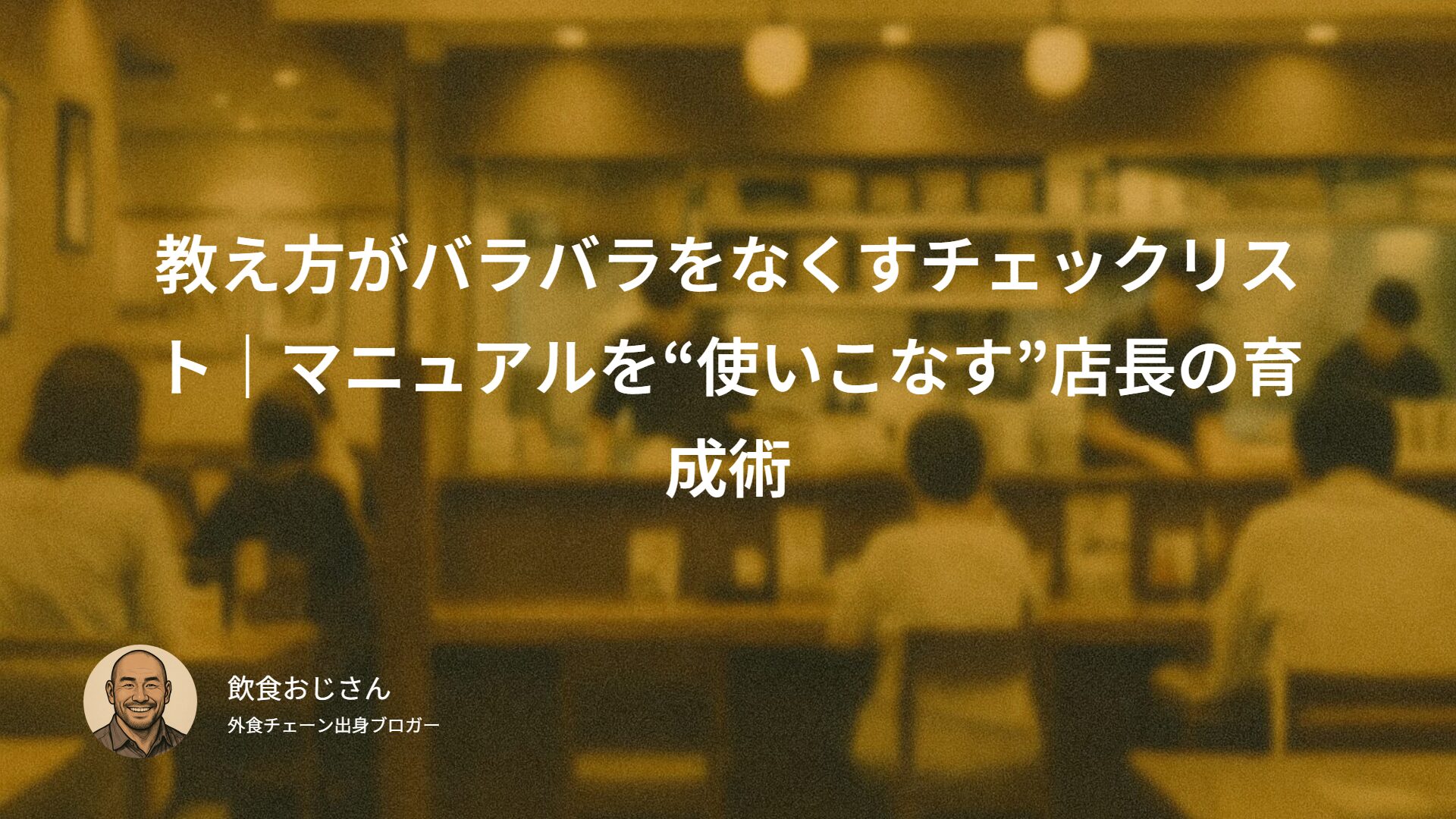
「マニュアルはあるけど、結局人によって教え方が違う」
そんな経験はありませんか?
新人に教えるたびに伝え方が変わり、結果として覚えるまでに時間がかかってしまうことがあります。
「うちのやり方はこうです」と言いながらも、気づけば人によって基準がずれています。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗の運営に取り組んできました。

忙しいお店ほど、同じように教えられる仕組みが必要です。マニュアルは、縛るためではなく、お客様に安定したサービスを届けるために積み上げられた知恵です。
本記事では、教え方のバラつきをなくし、マニュアルを活かすためのチェックリストを紹介します。
✅この記事を読むメリット
- 教える人と教わる人のズレを減らせます
- 忙しい中でも教育を続けやすくなります
- “お客様のための仕事”を安定させられます
マニュアルを味方につければ、教える負担も減り、スタッフが安心して成長できる環境を整えられます。
最後まで読んでいただければ、今日から使える“教え方をそろえる工夫”が見つかるはずです。
マニュアルがあるのに教え方がそろわない理由
多くの店には、しっかりしたマニュアルがあります。それでも、教育の結果に差が出てしまうのはなぜでしょうか。
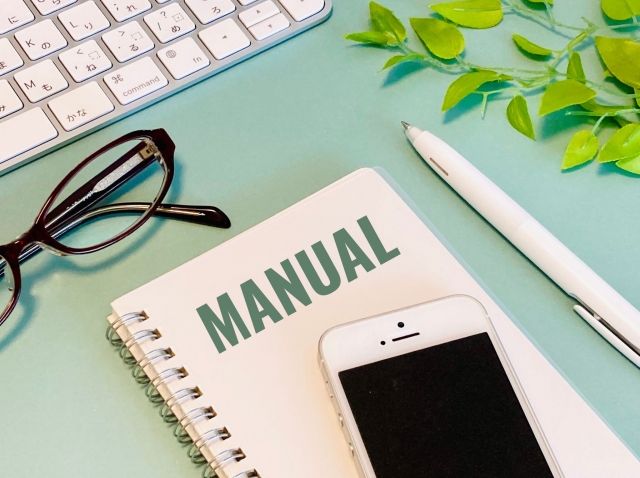
新人がなかなか育たない、スタッフごとに教え方が違う──その背景には、いくつかの共通した原因があります。
マニュアルは参考資料として活用し、従業員が状況に応じて判断できる教育が必要であるーお名前.com Biz ビジネスコンシェルジュ【業務マニュアル作成のポイント】
教える目的が人によって違う
「早く覚えてほしい」
「丁寧にやってほしい」
どちらも正しい考え方ですが、目的がそろっていないと指導がぶれます。
教育の目的は“教えること”ではなく、“任せられる状態をつくること”です。その視点が欠けると、マニュアルを使っても成果が安定しません。
マニュアルが“形だけ”になっている
マニュアルは運営の基準を示す「仕組みの中心」です。使われない状態が続くと、基準そのものが曖昧になります。
確認とフィードバックの仕組みがない
「教えた」「聞いた」で終わってしまう教育も少なくありません。
大切なのは、“できたかどうか”を確認し、その結果を次の指導や改善に生かす仕組みを持つことです。
人は確認されることで安心し、継続することで精度が上がります。
教え方のズレを生む3つの原因
| 原因 | 起こりやすい状況 | 主な影響 |
|---|---|---|
| 教える目的のズレ | 教える人によって優先順位が違う | 教育の基準が安定しない |
| マニュアルの形骸化 | 掲示しても使われていない | 内容が古く、信頼が落ちる |
| 確認の仕組み不足 | 教えたまま終わる | 定着せず再教育が増える |
マニュアルが機能しないのは、形式の問題ではありません。どう使い、どう確かめるか──それを決めるのがリーダーの仕事です。

マニュアルを正しく使うための3つの視点

マニュアルは、誰かが積み上げてきた仕事の基準です。それを軽く扱うと、同じ間違いを何度もくり返すことになります。
ここでは、マニュアルを正しく使うための3つの視点を整理します。
① 目的をそろえる
マニュアルは、“同じように動くため”ではなく、“同じ考えで判断するため”にあります。教える人が何を大切にしているかが違えば、同じ内容でも伝わり方が変わります。
目的が一致していれば、指導の言葉も揃ってきます。
② 決められた基準を守る
マニュアルは、上の人や先に働いた人たちが、失敗と改善を積み重ねて作ったものです。内容を勝手に変えたり、自分のやり方を優先したりすると、基準が崩れます。
迷ったときこそ、まずマニュアルに立ち返りましょう。
③ 気づいたことは正式に提案する
マニュアルを動かす権限は、決められた立場にあります。
判断と承認を経て修正されることで、全員が同じ基準を保てます。守るべきものを守る姿勢こそ、信頼を生む教育の土台です。
マニュアルは、自分を縛るものではありません。同じ方向に進むための“共通の地図”です。正しく使えば、人も仕事も迷いません。

👉 新人教育の「最初の3つ」を押さえるだけで、辞めないチームがつくれます。
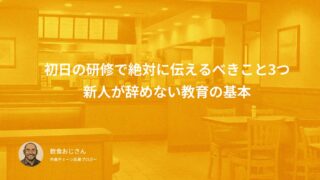
教え方をそろえるチェックリスト

マニュアルを正しく使ううえで、最も大切なのは「教え方をそろえる」ことです。同じ内容でも、教える順番や言葉が違えば、受け取る側の理解はまったく変わります。
ここでは、今日から確認できるチェックリストを紹介します。
✅ ① 教える内容を分けて伝える
一度に全部を教えようとすると、相手は混乱します。作業・言葉・考え方の三つに分けて説明しましょう。
「作業」は動き方を見せる
「言葉」は接客や報告の言い回しを伝える
「考え方」はその仕事の目的を説明する
この三つを分けるだけで、伝わり方の精度が大きく変わります。
✅ ② 教える順番を決める
人によって教える順番が違うと、覚え方もバラバラになります。
「見せる → 一緒にやる → 任せる」という流れを意識して、順番を固定しましょう。
先に見せることで安心し、一緒にやることで自信がつき、任せることで責任が生まれます。順番を決めておけば、教える人が変わっても育ち方は安定します。
✅ ③ 教えたあとを確認する
「教えたつもり」で終わると、どれだけ理解しているのか分かりません。
ポイントを質問してみる
実際にやってもらう
チェックシートにサインを入れる
など、確認の形を決めましょう。
確認は評価ではなく、信頼を積み上げる時間です。できた部分を認め、次に何を目指すかを一緒に整理します。
✅ ④ 迷いを減らす仕組みをつくる
教える側も完璧ではありません。伝え方に迷ったときにすぐ確認できるノートや掲示を作っておくと、教育のムラが減ります。
「自分の教え方が正しいか不安になったとき、どこを見ればいいか」を決めておく。
それだけで、チーム全体の安心感が変わります。
教え方をそろえるチェックリスト
| チェック項目 | 内容 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 教える内容を分けているか | 作業・言葉・考え方に整理して伝えている | 教え方を3つに分類できているか確認 |
| 教える順番を決めているか | 「見せる→一緒にやる→任せる」の流れがある | 指導手順が固定されているか確認 |
| 教えたあとを確認しているか | 質問・実践・チェックシートなどで理解度を測っている | 教わった側の言葉で説明できるか |
| 教える人が迷わない仕組みがあるか | 教え方を確認できる資料・ノートがある | 教える側が不安なく伝えられているか |
教え方をそろえるとは、みんなを同じにすることではありません。
“伝わる形”を決めることです。教える人が変わっても、育つ速さは変えられます。

まとめ|マニュアルを活かした教え方の3つの実践ポイント

教え方のズレを減らし、育つ仕組みを定着させる
マニュアルを正しく使えば、教える人が変わっても、伝わる内容はそろいます。ポイントは、形を整えることではなく、判断の基準をそろえることです。
そのために意識したい3つの実践ポイントを整理します。
- 教える目的をそろえる
- 決められた基準を守る
- 気づいたことは正式に提案する
この3つを意識するだけで、マニュアルは“形式”から“仕組み”に変わります。教える人の迷いが減り、育つスピードが安定します。
マニュアルは、同じ方向に進むための共通言語です。正しく使い続ければ、教育の土台が静かに整い、店も人も落ち着いていきます。
「マニュアルを活かすとは、形を合わせることではありません。同じ目的に向かって動けるようにすることです。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 本部と店舗の間でぶれない店長こそ、チームを動かす軸になります。