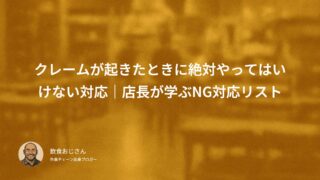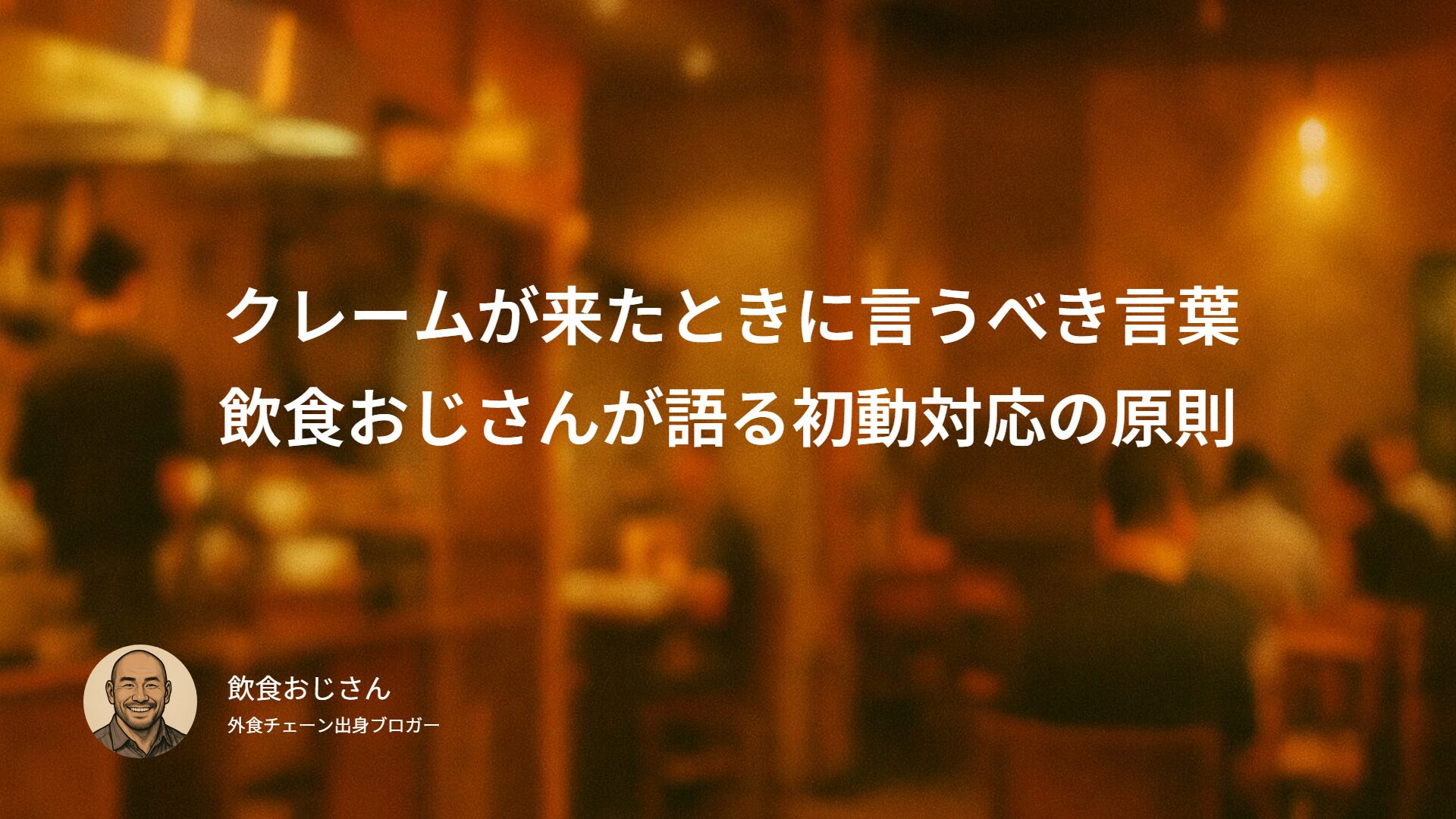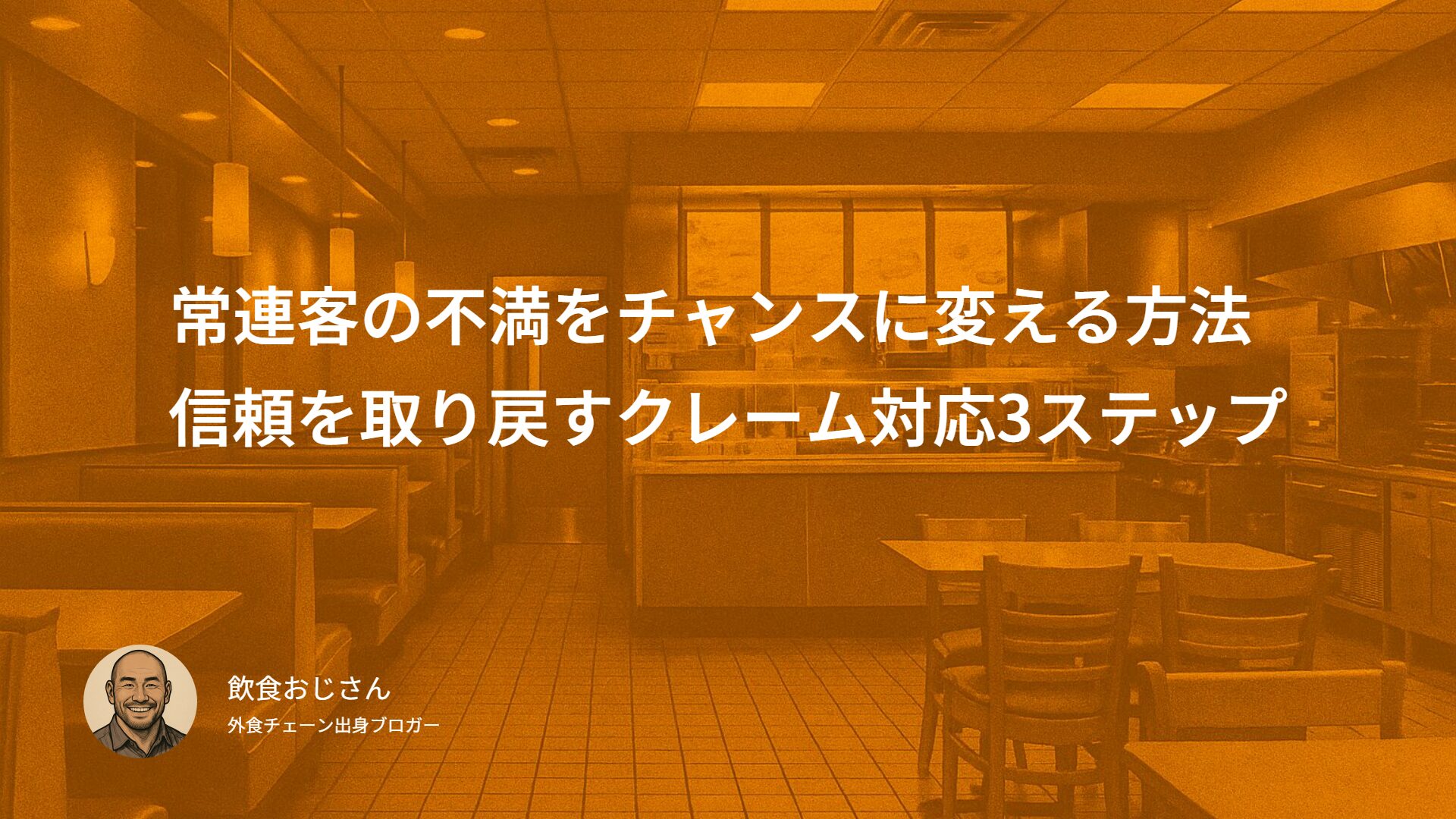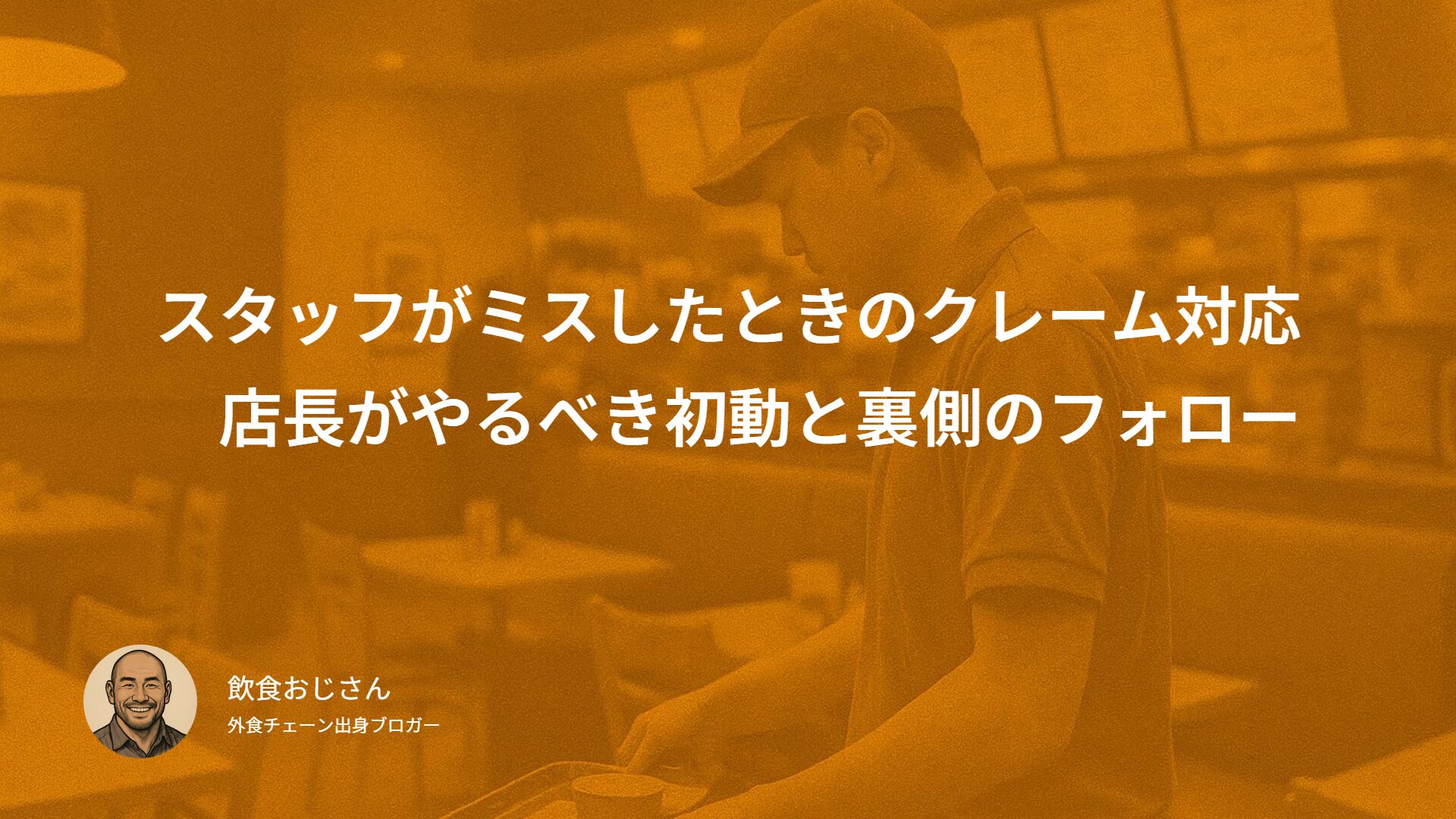「謝罪したのに余計怒られた…」飲食店で絶対使ってはいけないNGワード10選|クレーム対応で信頼を守る言葉術
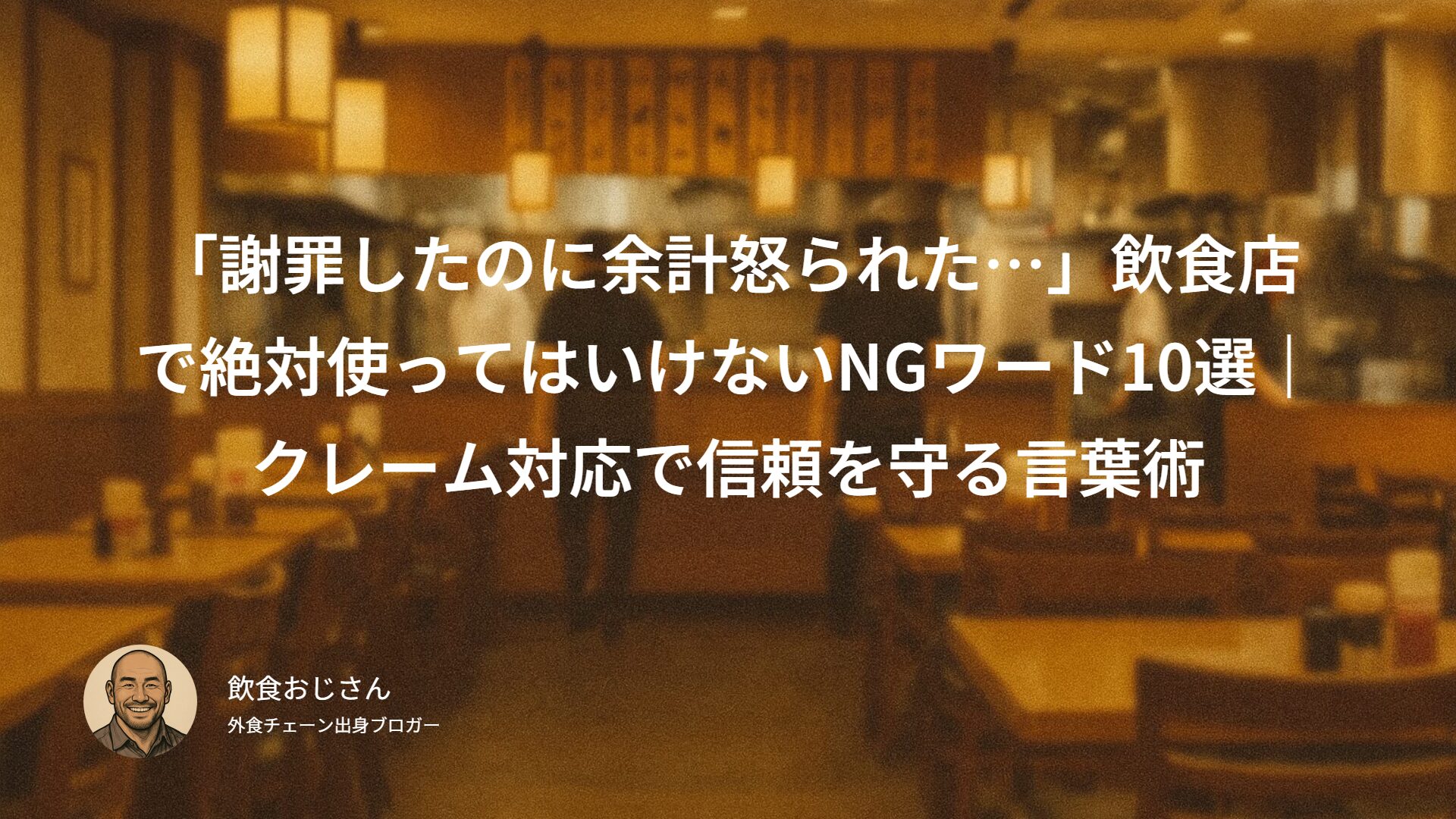
「謝ったのに、なぜかお客様の怒りが収まらない」
──そんな経験はありませんか?
クレーム対応の場面では、たった一言の言葉選びが、火に油を注ぐことがあります。
「でも」「大丈夫です」「一応〜します」など、悪気のない表現ほど誤解を招きやすいもの。気づかぬうちに相手の感情を刺激し、信頼を失うことも少なくありません。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗の運営に取り組んできました。

本記事では、飲食店でよく使われる謝罪時のNGワードと、信頼を保つための正しい伝え方を具体的に紹介します。
✅この記事を読むメリット
- お客様をさらに怒らせてしまう言葉がわかる
- 謝罪が伝わらない理由を理解できる
- 信頼を取り戻す「伝わる謝罪」の言葉づかいが身につく
「誠意が伝わる謝罪」は、気持ちではなく“言葉の設計”から始まります。最後まで読めば、接客業で使える“炎上しない謝り方”が必ず見つかります。
なぜ「謝罪」で炎上するのか

謝罪の目的が“誤解されている”
多くの店では、クレームが起きたとき「とにかく謝ればいい」と考えがちです。しかし、本来の謝罪の目的は「お客様を納得させること」ではなく、信頼を回復することです。
この“目的のズレ”が、謝罪が裏目に出る最大の原因になります。
相手が求めているのは「自分の感情を理解してもらえた」という安心であり、形式的な「申し訳ございません」ではその心に届きません。
言葉は“意図”ではなく“印象”で伝わる
「そんなつもりじゃなかった」という言葉ほど、相手の怒りを強めるものはありません。
謝罪の場では、発言の“意図”よりも“印象”が支配します。同じ言葉でも、声のトーンやタイミングによって、受け取られ方は大きく変わります。
誠意とは、相手が感じる安心の総量であり、自分の気持ちを伝えることではありません。
現代は「見られる謝罪」の時代
かつては店内で完結していたクレーム対応も、今はスマートフォンひとつで誰でも記録・発信できる時代です。
SNSや口コミサイトでは、第三者が“外側から見た印象”で判断します。
謝罪とは、相手だけでなく周囲にも伝わる「店の姿勢の表現」なのです。
謝罪が炎上につながる3つの典型
これらは一瞬で「誠意がない」と映り、店の信頼を損ないます。
謝罪は頭を下げることではありません。信頼を取り戻すための行動です。目的を誤ると、どんな言葉も相手には届きません。

お客様をさらに怒らせるNGワード集

「でも」「ただ」「一応」──弁解ワードが信頼を壊す
飲食店で多いのが、「でも」「ただ」「一応〜します」といった“弁解系ワード”。
言葉の目的は説明でも、相手には「責任を回避している」印象として届きます。
特にクレームの初期段階では、相手の感情が高ぶっており、一言の逆接が「言い訳」にしか聞こえません。
対策はシンプルで、
「自分の正しさを伝える」よりも「説明が不足していました」と自分側の不足を認める表現に変えることです。
「大丈夫です」「落ち着いてください」──軽視ワードの落とし穴
一見、優しい言葉に聞こえる「大丈夫です」「落ち着いてください」。しかし、怒っているお客様にとっては、上から目線の指示に感じられる危険があります。
この一言で「軽く扱われた」と感じる人は少なくありません。相手の感情を鎮めたいときこそ、命令形ではなく共感形を意識しましょう。
たとえば
「お気持ちを伺えてよかったです」「不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」など、相手の感情を受け止める言葉が最も効果的です。
「〇〇のせいで」「スタッフがやってしまって」──責任転嫁ワード
「担当者が…」「アルバイトが…」と説明したつもりでも、お客様には「店として責任を取らない姿勢」として映ります。
飲食店におけるクレームは、個人ではなく店舗全体の責任。誰がやったかではなく、「店としての再発防止策」を提示することが信頼回復の第一歩です。
もし事実説明が必要な場合でも、
「私たちの確認が不足しておりました」と“私たち”を主語にすることで印象がまったく変わります。
炎上を招くNGワード一覧表(改善例つき)
| NGワード | 相手に伝わる印象 | 改善表現(代替例) |
|---|---|---|
| 「でも」「ただ」 | 言い訳がましい | 「説明が不足していました」 |
| 「一応〜します」 | 投げやりに聞こえる | 「すぐに確認いたします」 |
| 「大丈夫です」 | 軽視された印象 | 「ご不安なお気持ちをお察しします」 |
| 「落ち着いてください」 | 命令・上から目線 | 「お気持ちを伺えてよかったです」 |
| 「〇〇のせいで」 | 責任逃れ | 「私たちの対応が至りませんでした」 |
| 「担当者が悪いんです」 | 内部不和の印象 | 「店として改善いたします」 |
| 「こちらも困ってます」 | 対立姿勢 | 「ご不便をおかけして申し訳ありません」 |
| 「聞いてませんでした」 | 無責任 | 「確認が行き届いておりませんでした」 |
| 「そんなつもりはありません」 | 開き直り | 「誤解を招く表現になり失礼いたしました」 |
| 「正直こちらも驚いてます」 | 軽率 | 「ご指摘ありがとうございます。確認させていただきます」 |
NGワードは“悪意の言葉”ではありません。無意識の口ぐせが信頼を損なっているだけです。気づいた瞬間から、対応は変えられます。

👉 クレームが起きた瞬間に、まず何を言うべきか迷わず対応したい方は、次の記事も参考にしてください。
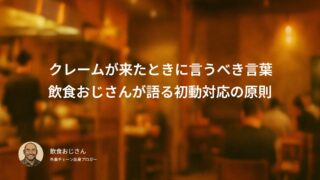
信頼を取り戻す謝罪のステップ

✅ ① 感情よりも「事実」と「共感」を先に伝える
謝罪の第一歩は、相手の感情を受け止めることです。多くの対応ミスは「言い訳が先に出てしまう」ことから起こります。
相手の怒りを鎮めるためには、感情を否定せず、共感の言葉で受け止める姿勢が必要です。
たとえば、
といった言葉が、信頼回復の土台になります。
✅ ②「責任」を明確にし、言葉で誠意を示す
謝罪には、原因を曖昧にしない姿勢が欠かせません。「担当が」「確認不足で」といった言葉の使い方ひとつで印象は大きく変わります。
大切なのは、“店として”責任を引き受ける意思を示すことです。
など、主語を“私たち”に置き換えるだけで信頼は伝わりやすくなります。責任の所在をはっきりさせることは、言い訳ではなく誠意の証です。
✅ ③ 言葉の後に「行動」で信頼を積み上げる
どんなに丁寧な言葉も、行動が伴わなければ意味がありません。謝罪の最後には、具体的な改善策と再発防止の行動を明示することが重要です。
など、実際の手順を示すことで、お客様の不安を“安心”に変えることができます。
✅ 信頼を取り戻す3つの原則
スピード:対応は早ければ早いほど誠意が伝わる
誠実さ:形式よりも、相手を思う姿勢を優先する
一貫性:謝罪後の対応まで、同じ温度で続ける
謝罪は言葉で終わるものではありません。行動を積み重ねることで、信頼は静かに戻っていきます。

信頼を取り戻す謝罪のステップ図|共感→責任→行動の流れ
まとめ|謝罪で信頼を取り戻すためのポイント整理

クレーム対応で失敗しないための3つの要点
謝罪の言葉は、使い方ひとつで印象が大きく変わります。
本記事では、謝罪がうまく伝わらない原因と、その改善の考え方を整理しました。信頼を取り戻すためには、気持ちよりも“伝え方”と“行動”の設計が重要です。
- 謝罪の目的は「信頼を回復すること」。感情ではなく行動で示す。
- 「でも」「大丈夫です」などの言葉は誤解を招きやすい。避ける習慣をつける。
- 共感 → 責任 → 行動、この順序を守ることで誠意が伝わりやすくなる。
言葉選びは一瞬の判断ですが、その影響は長く残ります。今日から「どんな言葉を使えば信頼をつなぎ直せるか」を意識してみてください。
「謝罪は、信頼を築き直すための小さな行動です。言葉を整えることは、心を整えることでもあります。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 お客様対応で焦ったときこそ、やってはいけない行動を思い出してください。こちらの記事で確認できます。