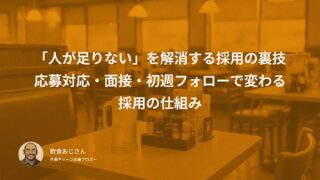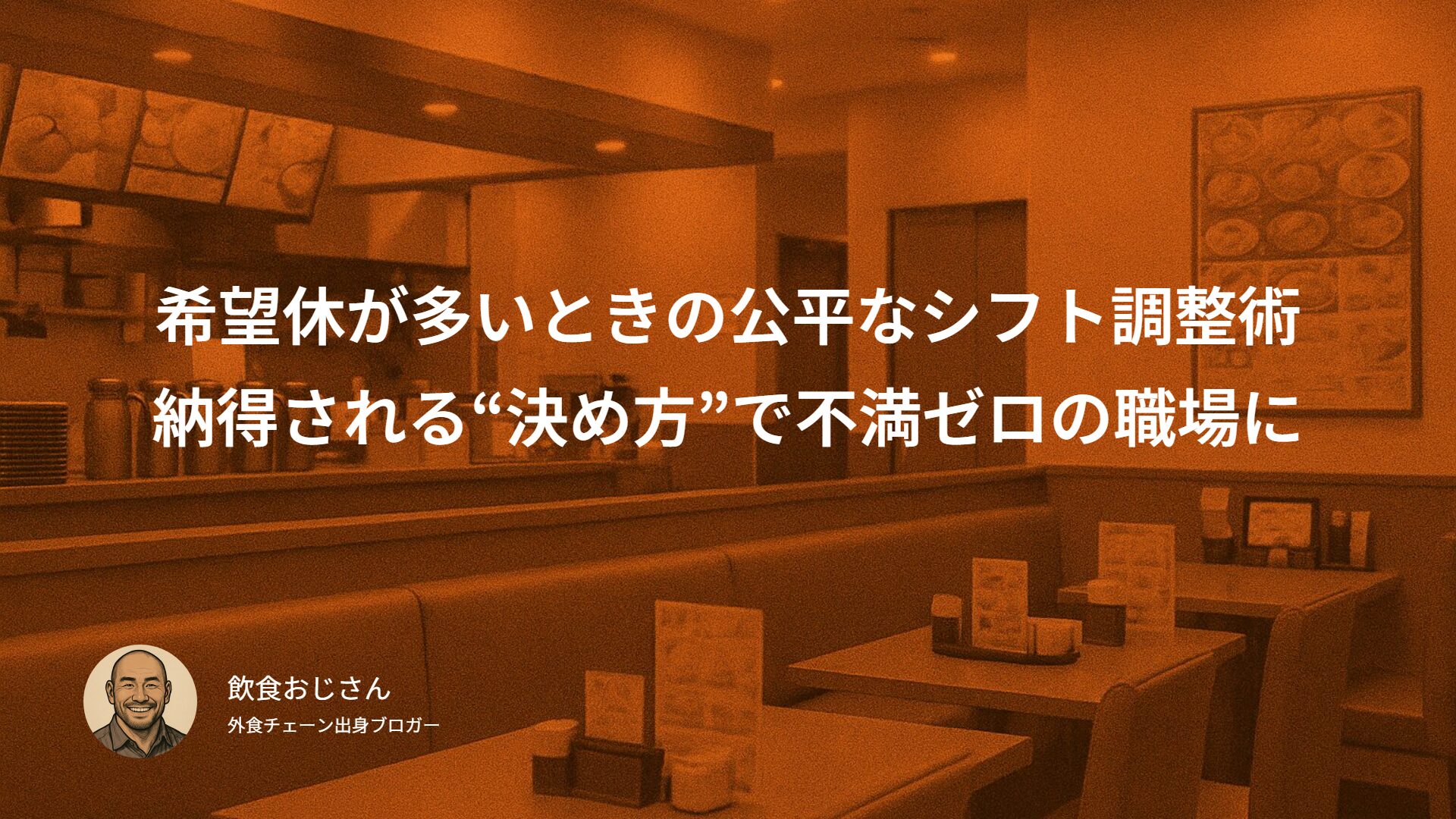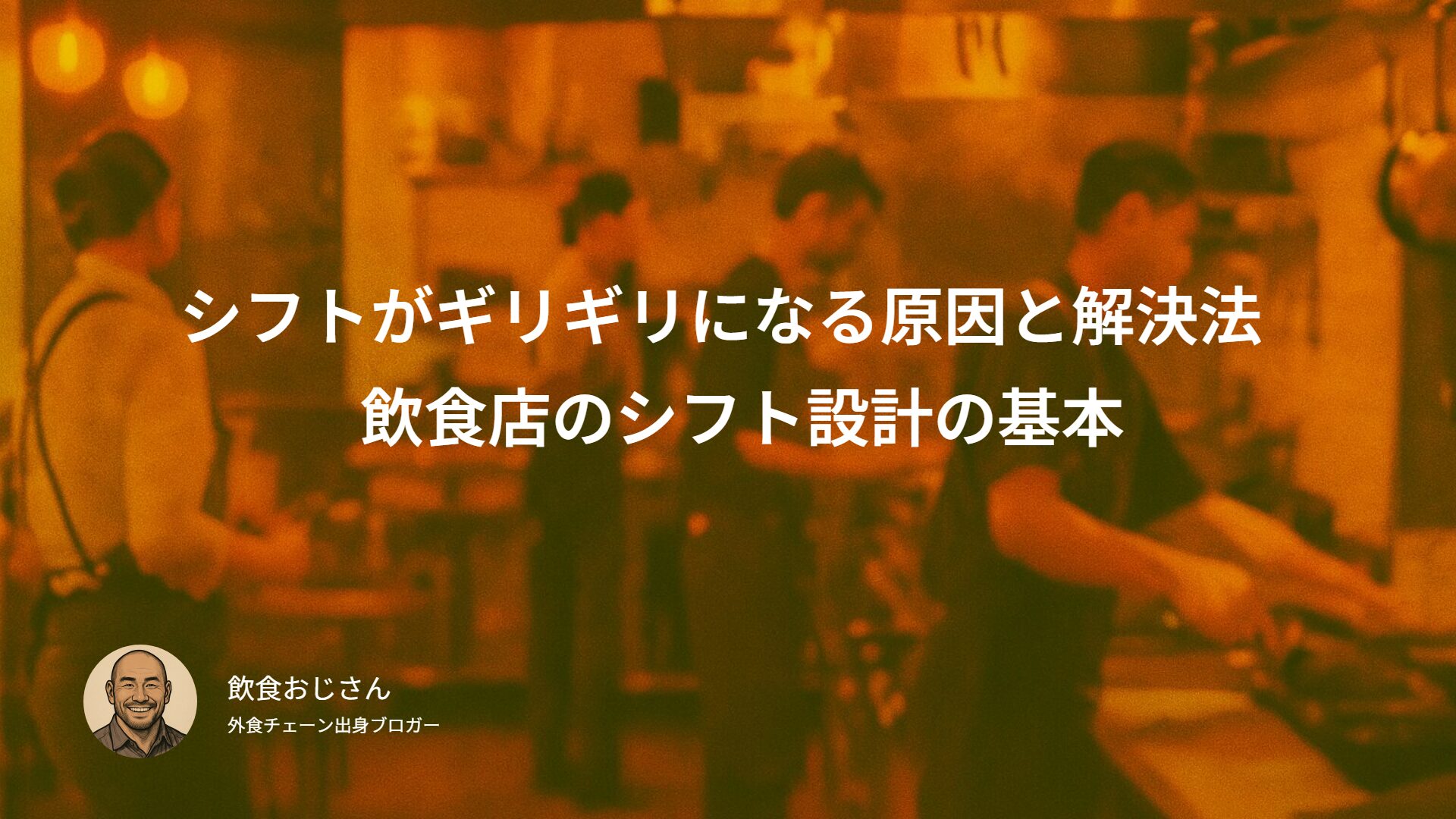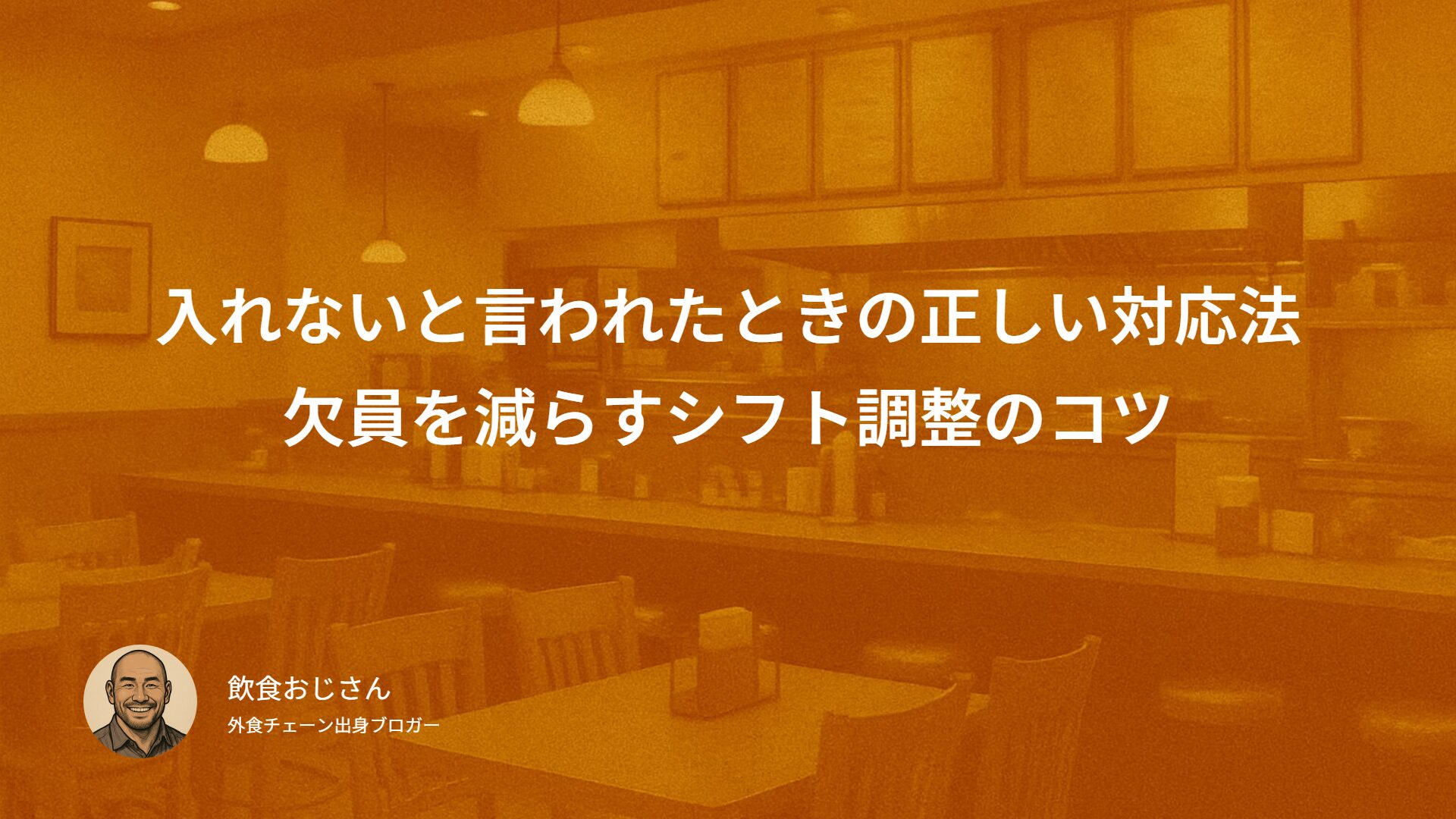繁忙期はギリギリ、閑散期は余る──飲食店シフトを安定させる3つの考え方
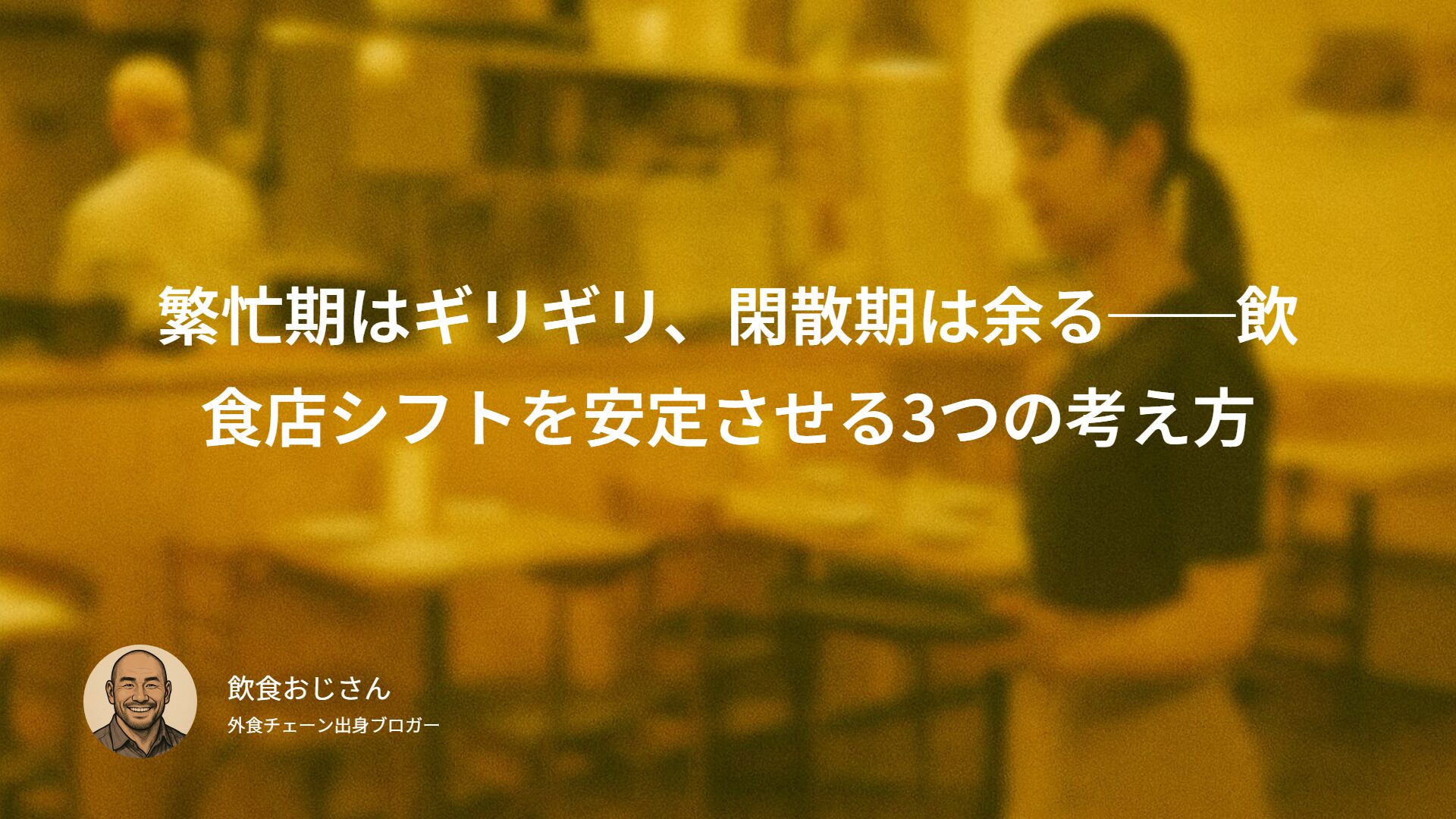
「繁忙期は毎回ギリギリ」
「閑散期は人が余ってシフト調整が大変」
そんな悩みを感じていませんか。
忙しい時期と落ち着く時期の差があるのは当たり前ですが、そのたびにシフト作りで頭を抱える店長さんは多いと思います。
おはようございます、“飲食おじさん”です。外食チェーンで10年間勤務、うち7年を店長として店舗の運営に取り組んできました。

本記事では、繁忙期と閑散期の違いを見越して、シフトを安定させる3つの考え方を紹介します。
無理なく人を配置し、スタッフの不満を減らしながら、人件費を守る方法がわかります。
✅この記事を読むメリット
- 時期ごとの忙しさに合わせたシフトの整え方がわかる
- 人件費のムダや偏りを防げる
- スタッフが納得して働ける環境をつくれる
最後まで読めば、「どうすれば忙しさの差に振り回されずに済むか」がはっきり見えてきます。
忙しい時期と落ち着く時期で起こる問題
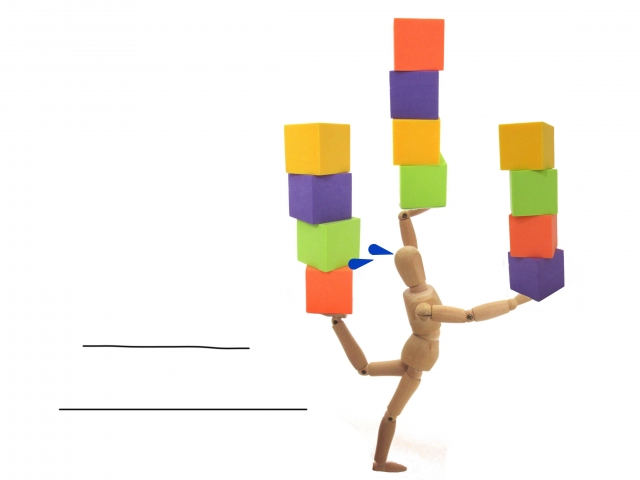
お店の一年を思い出すと、「忙しい時期」と「落ち着く時期」は必ずあります。
この差があるから、シフトづくりが難しくなるんですよね。
忙しい時期は、詰め込みすぎて疲れが残る
人を増やしてなんとか乗り切る。
でも終わったあとに残るのは「やり切った達成感」よりも、どっとした疲れ。
教える時間がなく、新人がつまずく
慣れない仕事でミスが増える
「またこのパターンか」とベテランが疲れる
落ち着く時期は、出られない不満がたまる
忙しさが落ち着くと、今度は「出勤できない」悩みが出てくる。
勤務時間が減ると、スタッフの収入も下がりやすい。
- 「最近シフト減りましたよね」
- 「もう少し入りたいんですけど」
この小さな不満が、次の繁忙期に影響することもあります。
繁忙期と閑散期の比較一覧表
| 項目 | 繁忙期 | 閑散期 | 店長が意識すべき点 |
|---|---|---|---|
| 来店数 | 多い | 少ない | 先に客数の予測を立てる |
| スタッフの稼働 | 多い・長い | 少ない・短い | シフト配分で差を調整 |
| 人件費 | 上がりやすい | 下がりやすい | 売上とバランスを取る |
| 雰囲気 | 慌ただしい | 緩みやすい | トーンをそろえる声かけ |
忙しいときも落ち着くときも、次にどうシフトを組むかを考えておく。そういう店は、慌てません。

なぜシフトが安定しないのか

シフトづくりで一番大変なのは、「人を入れるかどうか」よりもどんな考え方で決めるかです。忙しい時期と落ち着く時期の差が大きいほど、感覚や勢いで決めてしまいやすくなります。
ここでは、シフトが安定しない主な理由を三つに分けて整理します。
数字を見ているだけで使っていない
売上や来店数の記録は毎日出ていますが、それを次の計画に生かせていないお店は多いです。
「去年のこの時期は忙しかった気がする」──その程度の感覚で人を入れると、無駄が出やすくなります。
数字を“報告のため”に見るのではなく、“判断のため”に見るだけで、組み方はまったく変わります。
チェックポイント
シフト作りが人任せになっている
店長が作業に追われ、リーダーや副店長に任せっぱなしになっているケースもあります。
人によって考え方が違うため、方針がそろわず、毎回バラバラの形になる。「誰が作っても同じ基準で組める」ようにしておくことが、安定の第一歩です。
見直すポイント
人件費の見通しが後回しになっている
シフトを先に組み、あとから「今月人件費が高い」と気づくパターンは少なくありません。
人を入れる前に、売上の見通しを立てておくこと。忙しい時期と落ち着く時期で稼働のバランスを合わせるだけで、無理やムラが減ります。
数字は“見せるため”じゃなく、“使うため”に見る。ちょっと先を読むだけで、無駄な調整はぐっと減ります。

👉 シフトがいつもギリギリになってしまう状況を根本から改善したい方は、次の記事も参考にしてください。

繁忙期と閑散期に合わせたシフトの考え方

忙しい時期と落ち着く時期で差が出るのは当然です。問題は、その差をどう予測し、どう準備しておくか。
ここでは、店を無理なく動かすための三つの考え方を紹介します。
✅ ① 過去の数字を見返して次を読む
前年や前月の売上、曜日ごとの来店数を見返すだけでも、忙しくなる時期はある程度つかめます。
なんとなくの記憶ではなく、数字をざっくり確認しておくだけで「次の準備」がしやすくなります。
去年の同じ週・曜日をざっと比較しておく
イベントや天候の影響もメモしておく
忙しくなる時期を「覚えておく」より、「書き残しておく」。それだけで判断が速くなります。
✅ ② 仕事の内容ごとに人を考える
誰を入れるかではなく、どんな仕事を任せたいかを先に決めます。
ピークの時間帯は動きに慣れた人を中心に、落ち着く時間帯は新人育成の時間にする。この考え方を持つだけで、毎回ゼロから悩む必要がなくなります。
忙しい時間帯:注文・配膳・レジに経験者
落ち着く時間帯:仕込み・掃除・教育に新人
こうして「時間帯ごとの配置パターン」を決めておくと、人が入れ替わっても店の流れが乱れにくくなります。
時間帯別シフト配置の考え方(例)
| 時間帯 | 繁忙期の配置例 | 閑散期の配置例 | 店長のポイント |
|---|---|---|---|
| 開店〜昼前 | ベテラン1+新人1 | 新人中心 | 立ち上がりを丁寧に |
| 昼ピーク | 経験者中心(注文・提供) | 最少人数で対応 | 作業を分担して負担を減らす |
| 昼〜夕方 | 教育・仕込みを中心に | 教育・清掃時間に充てる | 閑散期に育成を入れる |
| 夜ピーク | フルメンバー体制 | 経験者少数で効率化 | 負担を翌日に残さない |
✅ ③ 早めに共有して納得をつくる
シフトの調整で一番揉めるのは、「知らされていないこと」。
忙しい時期も落ち着く時期も、「なぜこの形なのか」を説明するだけで、不満は減ります。
共有のコツ
- 変更や方針を早めに伝える
- 理由を数字や来店状況とセットで話す
説明できるシフトは、信頼されるシフトです。
シフトの安定は“予測”と“共有”。思いつきではなく考えて動けば、無理のないお店になります。

まとめ|繁忙期と閑散期のシフトを安定させるポイント

繁忙期と閑散期で忙しさに差があるのは当たり前です。大切なのは、その変化を見越してシフトを安定させる考え方を持つこと。
「そのときの対応」ではなく、「先を読む準備」をしておくだけで、お店の流れは落ち着きます。
飲食店のシフトを安定させる3つのポイント
- 過去の数字を見て、次の繁忙期を予測する
→ 去年の同じ時期を振り返ることで、準備の精度が上がる。 - 仕事の内容に合わせて人を配置する
→ 忙しい時間は経験者、落ち着く時間は新人育成でバランスを取る。 - シフトの方針を早めに共有する
→ 理由を話すことで、スタッフの納得と協力が得られる。
忙しい時期と落ち着く時期、どちらも「事前に考えておく」ことで差が小さくなります。
その積み重ねが、無理のないお店づくりにつながります。
「繁忙期も閑散期も、“先を読む店長”が強い。シフトを考える時間を取ることが、いちばんの節約になります。」毎日“本当に”おつかれさまです。

👉 人手不足を根本から解消できる採用の仕組みを作りたい方は、次の記事も参考にしてください。